年金繰り下げのデメリットがヤバイとネットの口コミで噂されている理由とは?
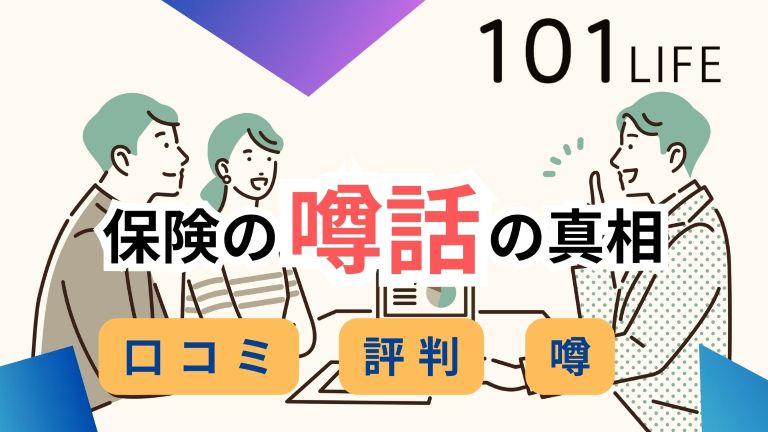
年金繰り下げ受給のデメリットを口コミと評判なども参考にわかりやすく解説
年金繰り下げ受給についてネットの口コミや評判から真相を掘り下げてみました。令和4年4月から年金繰り下げの上限年齢が70歳から75歳に引き上げられ、最大84%も年金が増額するという制度が注目を集めています。しかし同時に「繰り下げはやめたほうがいい」「デメリットがヤバイ」という声もソーシャルメディアで多く見られます。本当に年金繰り下げには落とし穴があるのでしょうか?それとも単なる誤解なのでしょうか?日本年金機構の情報や専門家の見解を元に、メリットとデメリットの両面から検証していきます。
年金繰り下げ受給とは何か?制度の基本を理解する
年金の繰り下げ受給とは、老齢基礎年金や老齢厚生年金を65歳で受け取らずに、66歳以降に受給開始時期を遅らせる制度です。通常、老齢基礎年金と老齢厚生年金は65歳から受給できますが、受給開始を遅らせることで年金額が増額されます。
2022年4月からは繰り下げの上限年齢が70歳から75歳に引き上げられました。増額率の計算式は「0.7%×65歳に達した月から繰り下げ申し出日の前月までの月数」となっており、75歳まで引き延ばした場合は84%増しの年金を受け取れることになります。つまり、たとえば65歳時点で月額20万円の年金が支給される予定だった方が75歳まで繰り下げると、月額約36.8万円に増額されるのです。
この制度改正によって、年金の繰り下げメリットに注目が集まっていますが、同時に「デメリットが大きい」という声も広がっているようです。
ネットで噂される「ヤバイ」繰り下げデメリット
早く死亡すると総受給額が減少する可能性
年金繰り下げで最も懸念されるデメリットは、「早く死亡した場合、65歳から年金を受け取った場合に比べて年金総額が少なくなる可能性がある」という点です。
具体的な試算では、70歳まで繰り下げた場合、65歳から受給した場合と比較して総受給額が逆転するのは約82歳とされています。つまり、82歳まで生きないと繰り下げのメリットが受給総額で現れないということになるのです。
あるケースでは、65歳時点で年間240万円(月額20万円)の年金を70歳から受給開始すると年間約340万円(月額28万円)になりますが、82歳前に亡くなると生涯の受給総額で損をすることになるのです。
「長生きすればするほど得になるけれど、平均寿命で考えると得にならないことも多い」というのがネットで広がる意見のようです。令和4年の日本人男性の平均寿命は81.05歳とされており、単純計算では男性の場合、繰り下げのメリットを十分に享受できない可能性があると言われています。
税金や社会保険料の負担増
2つ目のデメリットとして、繰り下げにより年金額が増加すると、税金や社会保険料の負担も増加するという問題があります。
年金の増額に伴い所得税や住民税が増えるだけでなく、健康保険料や介護保険料などの社会保険料も増加する可能性があります。「年金額の増加分がそのまま手取りとして増えるわけではない」というのは大きな誤解だと、社会保険労務士の井戸美枝さんは指摘しています。
特に課税所得が145万円前後になると、医療費の自己負担割合が上がるなど、様々な面で負担が増える可能性があると言われています。このように、増額されたように見える年金が、税金や社会保険料の増加によって相殺されてしまうリスクがあるのです。
加給年金が受け取れなくなる可能性
扶養されている配偶者がいる場合は注意が必要です。加給年金とは、年金受給者に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいる場合に加算される年金ですが、繰り下げ期間中に配偶者が65歳を迎えると、加給年金を受け取れなくなってしまいます。
「配偶者が加給年金の対象となる場合は、繰下げ受給をするか繰下げ受給をせずに加給年金を受け取るか、じっくり検討する必要がある」と専門家は指摘しています。場合によっては、加給年金の喪失分が繰り下げによる増額分を上回ることもあるようです。
医療費の自己負担割合の増加
4つ目のデメリットは、年金増額に伴う医療費の自己負担割合の増加です。
70歳以上の高齢者は医療費の負担割合が所得によって変わりますが、年金繰り下げによって収入が増えると、医療費の自己負担割合が引き上げられる可能性があります。高齢になるほど医療機関の利用頻度が高まることを考えると、この増加分は無視できない金額になることもあるでしょう。
また、高額療養費制度の上限額も所得に応じて変わるため、繰り下げによる収入増で上限額が上がり、結果として医療費負担が増加する可能性もあると言われています。
遺族年金は増額されない
繰り下げ受給による増額は遺族年金には適用されません。つまり、繰り下げ期間中に亡くなった場合、遺族に支給される遺族年金は65歳時点の金額に基づいて計算されるため、繰り下げによる増額メリットが反映されないのです。
このように、年金繰り下げには様々なデメリットがあるとネット上では指摘されています。しかし、これらの情報は正確なのでしょうか?誤解はないのでしょうか?次に、繰り下げ受給に関する誤解と真実を見ていきましょう。
繰り下げ受給に関する誤解と真実
誤解1:「ねんきん定期便」の増額率がそのまま適用される
多くの人が陥る誤解の一つは、日本年金機構から送られてくる「ねんきん定期便」に記載されている増額率がそのまま自分の年金に適用されると考えることです。
特に、在職老齢年金制度の影響を受ける会社経営者や高収入の方は注意が必要だと言われています。報酬が高く、老齢厚生年金(報酬比例部分)が全額支給停止となるような場合、何歳まで繰り下げても老齢厚生年金(報酬比例部分)は全く繰下げ増額されないことがあります。
「ねんきん定期便」に記載されているのは、65歳時の年金を70歳まで繰り下げると1.42倍に、75歳まで繰り下げると1.84倍になるという単純なイメージ図であり、実際の増額率は個人の状況によって大きく異なる可能性があります。
誤解2:繰り下げは事前に決める必要がある
「繰り下げ受給を選択するには、受給開始年齢を事前に申請・登録しなければならない」と考えている方も多いようですが、これは誤解です。
実際には、いつから受給開始するかを事前に決める必要はなく、66歳以降のお好みの時期に年金事務所等で手続きを行えば良いのです。また、請求手続きを行う前であれば受給開始時期の変更も可能です。
誤解3:支給開始年齢引上げの布石である
一部では「繰り下げ受給の上限年齢の70歳から75歳への拡大は、法定上の支給開始年齢である65歳を、70歳あるいはそれ以上の年齢に引上げるための布石ではないか」という懸念も見られますが、専門家はこれを否定しています。
むしろ、2022年4月の改正では繰上げ受給に伴う減額率が5%から4%に緩和する改正も実施されており、支給開始年齢の引上げを前提としているとは考えにくいと指摘されています。
誤解4:早く死ぬから繰り下げはやめとけという単純な議論
「早く死ぬと損をするから繰り下げはやめるべき」という議論も多く見られますが、これは年金の本質を見誤っていると指摘する専門家もいます。
公的年金は「長生きリスク」に備えるための保険であり、「長生きしても終身で受け取れる」ことこそが最も重要な特徴だという視点が欠けているとの指摘があります。つまり、繰り下げ受給は長生きした場合の保障を厚くする選択肢とも言えるのです。
繰り下げ受給が「おすすめ」される人とは?
年金繰り下げは全ての人に不向きというわけではなく、むしろ積極的に検討すべき人もいます。以下のような方には繰り下げ受給が「おすすめ」だと専門家は指摘しています。
年金額が少ない人
公的年金の加入期間が少なく元々の年金支給額が少ない人は、繰り下げ支給による増額を考慮しても、非課税の範囲内に収まる可能性が高いとされています。
具体的には、国民年金のみ加入しているフリーランスや自営業、専業主婦の期間が長い方などが該当します。これらの方々は社会保険料の負担も少なく、繰り下げ後の手取り額は加算率を乗じて算出した総額と近い値になる可能性が高いと言われています。
社会保険労務士の井戸美枝さんも、「厚生年金の加入期間がゼロか数年しかない人」に繰り下げ受給を勧めています。特に夫に扶養されていた妻は「自分の年金額が少なく、夫の死後、生計の維持が困難になるケースが多い。繰り下げ受給で自分の年金を増やしておきたい」と指摘しています。
65歳以降も働く予定の人
労働収入をはじめ、事業収入や企業年金、個人年金など何らかの方法で65歳以降の生活費を確保できる人は、支給開始時期を遅らせても不都合は生じにくいとされています。
特に、65歳の定年後も働く予定がある場合、定年後の収入で生活費をカバーしながら年金を繰り下げることで、将来の年金額を増やすことができます。
「年金を繰下げ受給で得する人」として「繰下げ期間中の生活費をまかなえる人」が挙げられており、65歳以降も働く予定がある方などは、お給料で生活費をカバーできるため繰り下げのメリットを享受しやすいと考えられます。
繰り下げ受給の「利点」を最大化する方法
長期的な視点で考える
年金繰り下げの最大の「利点」は、増額された年金を一生涯受け取れる点です。1年間受け取りを我慢すれば、一生涯にわたり1ヵ月あたりの年金額が8.4%も増額されます。
この増額率は銀行預金などと比較しても非常に高く、超低金利時代と言われる今、銀行預金で同程度の利率を目指すのは容易ではないと言われています。長期的な視点で見れば、繰り下げ受給は非常に合理的な選択肢の一つと言えるでしょう。
年金の種類ごとに繰り下げを検討する
老齢基礎年金と老齢厚生年金を別々のタイミングで繰り下げることも可能です。例えば、老齢基礎年金は65歳から受け取り、老齢厚生年金だけを繰り下げるといった選択もできます。
このように、自分の状況に応じて年金の種類ごとに受給開始時期を調整することで、繰り下げのメリットを最大化しつつデメリットを最小化することが可能です。
健康状態や家族状況を考慮する
繰り下げ受給を検討する際は、自分の健康状態や家族状況も重要な判断材料となります。健康状態に不安がある場合や、加給年金を受け取る必要がある場合は、繰り下げが適していない可能性もあります。
一方で、健康状態が良好で長生きが期待できる場合や、65歳以降も十分な収入がある場合は、繰り下げ受給のメリットを享受できる可能性が高いと言えるでしょう。
専門家の見解:個々の状況に合わせた選択が重要
社会保険労務士やファイナンシャルプランナーなどの専門家は、年金繰り下げの判断は個人の状況によって大きく異なると指摘しています。
社会保険労務士の井戸美枝さんは、「年金額はもらい始めてしまえば本人が生きている限り、そう大きく変わることはない。しかし、少子高齢化の進行や財政状況を考えると、税金や社会保険料はこれからも上がっていかざるを得ない」と指摘し、繰り下げ受給の判断には様々な要素を考慮する必要があると述べています。
また、ファイナンシャルプランナーである辻本剛士氏も、年金制度に潜む「落とし穴」について解説し、繰り下げ受給の選択には慎重な判断が必要だと指摘しています。
実際のケースから学ぶ繰り下げ受給の実態
繰り下げて後悔したケース
近藤義貴さん(仮名・74歳)は、長い将来のことを考えて年金を70歳まで繰り下げ受給することを選択しました。「65歳の時点ではまだまだ健康でしたし、長い将来のことを考えて年金を繰り下げて受給しようと決めたんです。まさかその選択が裏目に出るなんて、思ってもみませんでした」と近藤さんは語っています。
近藤さんは大学卒業後に大手電機メーカーに就職し、60歳で定年退職、その後は個人事業主として仕事を続けていました。65歳時点では健康状態も良好で、繰り下げ受給によって増額される年金に期待していたようですが、その後の状況変化によって後悔する結果となったようです。
繰り下げを検討しているケース
鈴木浩平さん(仮名・64歳)は、食品メーカーで営業職として勤務しており、65歳の定年後も同じ職場で働く予定です。65歳からは年間約240万円(月額20万円)の年金を受け取る予定でしたが、繰り下げ受給を選択することを検討していました。
しかし、鈴木さんは年金制度のある「落とし穴」に気づき、繰り下げ受給という選択を迷い始めることになります。このように、繰り下げ受給の判断は個人の状況や将来の見通しによって大きく左右されるものだと言えるでしょう。
専門家からのアドバイス:最適な判断のために
年金繰り下げを検討している方々に対して、専門家はどのようなアドバイスをしているのでしょうか?
自分の年金額を正確に把握する
まず第一に、自分の年金額を正確に把握することが重要だと言われています。「ねんきん定期便」の情報だけでなく、年金事務所で実際の試算をしてもらうことで、繰り下げによる具体的な増額を確認することができます。
特に、在職老齢年金制度の影響を受ける可能性がある場合は、年金事務所で相談することで誤解を避けることができるでしょう。
繰り下げ期間中の生活費計画を立てる
繰り下げ期間中は年金を受給できないため、その間の生活費をどのように賄うかという計画を立てることも重要です。
65歳以降も働く予定がある場合や、十分な貯蓄がある場合は繰り下げが選択肢となりますが、繰り下げ期間中の生活に不安がある場合は、予定通り65歳から受給を開始することも検討すべきでしょう。
税金や社会保険料の影響を考慮する
繰り下げにより年金額が増えると、税金や社会保険料にも影響があることを理解し、その影響を考慮に入れた判断が必要です。
課税所得が145万円前後になると様々な負担が増える可能性があるため、繰り下げによる年金増額がこの境界線を超える場合は特に注意が必要だと指摘されています。
結論:年金繰り下げは「やばくない」選択肢の一つ
ネット上では「繰り下げのデメリットがヤバイ」「繰り下げはやめたほうがいい」という声が目立ちますが、実際には一概にそう言い切れるものではありません。
年金繰り下げには確かにデメリットがありますが、同時に大きな「利点」もあります。長生きすれば一生涯増額された年金を受け取れるという点は、「人生100年時代」と呼ばれる現代において非常に重要な要素と言えるでしょう。
また、繰り下げ受給は柔軟性が高く、66歳以降のお好みの時期に年金受給を開始できるため、状況の変化に応じた対応が可能です。
最終的には、自分の健康状態、家族状況、収入見込み、貯蓄状況などを総合的に考慮し、専門家のアドバイスも参考にしながら判断することが重要です。年金繰り下げは決して「やばい」選択肢ではなく、状況によっては非常に「おすすめ」できる選択肢の一つと言えるでしょう。
特に年金額が少ない方や、65歳以降も働く予定がある方には、年金繰り下げを前向きに検討する価値があります。自分の状況に合った最適な選択をするためにも、日本年金機構や年金事務所での相談を活用し、正確な情報に基づいた判断をすることをお勧めします。
年金繰り下げはデメリットだけではなく、適切に活用すれば老後の生活をより豊かにする可能性を秘めた制度なのです。「人生100年時代」に備え、自分に合った年金受給計画を立てていきましょう。

