マイナ免許証の”デメリット”がやばいといわれているのはなぜ?
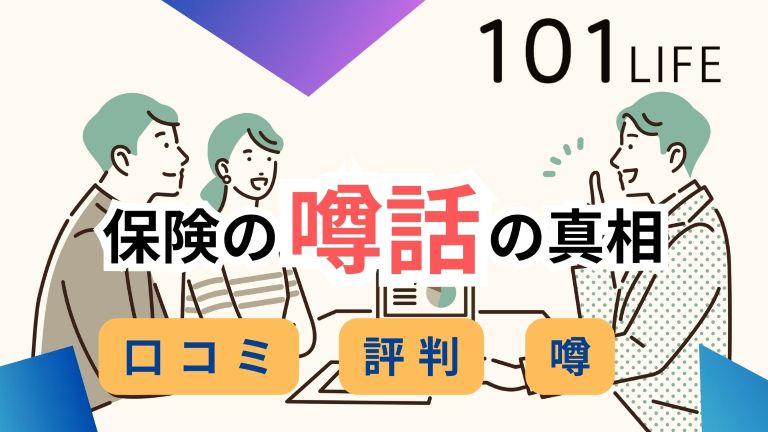
”マイナ免許証はヤバイのでやめたほうがいい”と口コミや評判で言われている原因について掘り下げて解説します
マイナ免許証は本当に”やばい”のか、デメリットとメリットから真相に迫る
マイナンバーカードと運転免許証が一体化した「マイナ免許証」についてネットの口コミや評判から真相を掘り下げてみました。2025年3月24日から運用が開始されたマイナ免許証は、「デメリットがやばい」「やめたほうがいい」といった声がネット上で多く見られています。しかし、実際のところはどうなのでしょうか?口コミで指摘されているデメリットは本当なのか、それとも誤解から生じた情報なのか、良い評判も含めて検証していきます。
マイナ免許証とは?基本的な仕組み
マイナ免許証とは、マイナンバーカードに運転免許証の機能を付加したものです。運転免許証の情報をマイナンバーカードのICチップに登録することで、1枚のカードで両方の機能を持たせることができます。2025年3月24日から運用が開始され、従来の免許証のみ、マイナ免許証のみ、両方の2枚持ちという3つのパターンから選択できるようになっています。
ネットで「やばい」と言われるデメリット
1. 紛失時のリスクが大きい
マイナ免許証に関して最も懸念されているのが、紛失した場合のリスクです。従来の運転免許証であれば、運転免許センターなどで手続きをすれば30分から1時間程度で即日再発行が可能でした。しかし、マイナ免許証の場合は、マイナンバーカードの再発行となるため、最低でも1週間、状況によっては数カ月かかる可能性があると言われています。
あるネット上の意見では「マイナカードの再発行には、概ね1ヶ月半かかります。そのため、マイナ免許証を紛失した場合などには、長期間にわたり運転できなくなる可能性があります」と指摘されています。これは、特に仕事などで日常的に車を使う人にとっては、かなり「やばい」状況に陥る可能性があるようです。
ただし、この点については一部誤解もあるようです。遠藤玲子キャスターによると「マイナ免許証は、マイナ保険証とは違って完全移行するわけではないので、免許証だけを免許センターで即日発行することも可能です」と説明されています。つまり、マイナ免許証を持っていても、紛失時には従来型の免許証を再発行してもらうことが可能なようです。
2. マイナカード更新後の問題
マイナ免許証を持つ上で特に注意が必要なのが、マイナンバーカードの更新時に生じる問題です。現行システムでは、マイナカードの有効期限が来て更新すると、ICチップにあった免許情報が新しいマイナカードに反映されないという欠点があります。
「マイナカード更新後に運転免許証の一体化の再手続きが必要」となり、「これは、更新後のマイナンバーカードのICチップは新しくなって運転免許証情報がリセット(非搭載)されているので、改めて手続きをする必要があるから」と説明されています。
さらに深刻なのは、「マイナ免許証『のみ』とした場合、マイナンバーカード更新後のICチップには運転免許証情報がリセット(非搭載)されているので、そのまま運転すると運転免許証不携帯違反になる」という点です。これは、特に注意が必要で、間違いなく「やめたほうがいい」と言われる理由の一つのようです。
ただし、この問題に関しては、「情報が自動的に引き継がれるシステムの導入は、今年秋ごろになる見通し」とも報告されています。つまり、将来的には改善される可能性があります。
3. 確認の手間が増える可能性
マイナ免許証では、券面に免許情報が表示されないため、確認に手間がかかるというデメリットがあります。「重要な免許種別や有効期限などの免許情報はCIチップに登録されており、券面では確認できません」とされています。
特に、レンタカーを借りる際などには、「マイナポータル経由で確認するか、『マイナ免許証読み取りアプリ』で確認する必要があり少し手間が増えることになりそう」という懸念があります。また、「レンタカーの場合は、マイナ免許証の免許情報を読み取る必要があります。専用アプリを予めダウンロードして、自分でその専用アプリでレンタカー屋さんに見せる必要があるということで、ひと手間かかってしまいます」という指摘もあります。
これについては、現時点では「各事業者で対応が異なり、しばらくは従来の『運転免許証』のみでの対応となるレンタカー事業者もあります」という状況のようです。つまり、移行期間中はさらに混乱が生じる可能性があります。
4. 個人情報漏洩のリスク
マイナ免許証に関する懸念として多く挙げられているのが、個人情報の漏洩リスクです。「多くの人にとって最も不安なのが、自治体側による情報の紐付けミスや、紛失・盗難による情報漏えいでしょう」と指摘されています。
また、「お金の流れと自分の免許情報がひも付き、警察に何かが吸い取られていくようで身構えてしまう」という声もあります。これは、マイナンバーカードと免許証が一体化することで、より多くの個人情報が1枚のカードに集約されることへの不安が表れています。
OHKアプリで行われたアンケートでも、「個人情報に関わるトラブルが多すぎる」など不信感を持つ人が多く見られたと報告されています。このような不安感は、マイナ免許証の採用を躊躇する大きな要因となっているようです。
5. 手続きの煩雑さ
マイナ免許証の取得や更新に関しても、いくつかの問題点が指摘されています。まず、「手続き・処理(転載,共有)にかかる時間がどの程度になるのか予測がてきていないこともあって、『事前予約制』を取る」という点です。これにより、「自分の都合で運転免許センターに行っても、その場で一体化できない」という不便さがあります。
また、「マイナ保険証と違い、マイナ免許証に係る一体化には手続き費用が発生する」という点も、おすすめしない理由として挙げられています。さらに、更新年が同じ場合に「一体化の手間と手続き費用が2回かかる」可能性もあるようです。
これらの手続き上の煩雑さも、マイナ免許証の採用を躊躇させる要因となっているのではないでしょうか。
「やばい」という評判は誤解から?
マイナ免許証に関する否定的な評判の中には、誤解から生じているものもあるようです。以下、いくつかの点について検証してみます。
1. 紛失時の対応について
先述したように、マイナ免許証を紛失した場合でも、「免許証だけを免許センターで即日発行することも可能」という情報があります。つまり、マイナ免許証だけでなく、緊急時には従来の免許証も発行できるので、完全に運転できなくなるわけではないようです。
2. 選択肢の幅について
マイナ免許証については、「従来型の免許証とマイナ免許証のどちらか、または両方を保有できる」という選択肢があります。これは「保険証と異なり、選択肢の幅を残している点で『マイナ免許証』は評価できる」とも言われています。つまり、完全に強制されるわけではなく、自分のライフスタイルに合わせて選択できる点は、「やばくない」ポイントと言えるでしょう。
3. システム改善の見通し
マイナカード更新後の免許情報リセットという問題についても、「情報が自動的に引き継がれるシステムの導入は、今年秋ごろになる見通し」という情報があります。現時点では問題があっても、今後改善される可能性があるということです。
マイナ免許証の「おすすめ」ポイント
マイナ免許証には確かにデメリットがありますが、一方で注目すべき利点もあります。以下、その主なものを見ていきましょう。
1. 住所変更手続きの簡素化
マイナ免許証最大の利点の一つが、住所変更手続きの簡素化です。「マイナ免許証に切り替えると、市区町村役場での住所・氏名変更手続きで免許証の情報も書き換えられるため、警察や運転免許センターへ行く必要はなくなります」という説明があります。
これは「転勤による引越しなどで住所変更の回数が多い人にとって、大きなメリット」となり得るでしょう。特に、従来は市区町村役場と警察の両方で手続きが必要だったものが、一ヶ所で済むようになるのは大きな時間節約になります。
2. 更新手続きの利便性向上
マイナ免許証では、「更新手数料が現在は2500円だが、マイナ免許証のみの場合、2100円になりお得になる」というメリットがあります。また、「優良運転者や軽微な違反1回のみの運転者は、免許更新時の講習をオンラインで受けられる」という利点もあります。
特にオンライン講習は、「めちゃくちゃいいじゃん。いいっすね」「こっち(運転免許試験場)来ないで済むなら」という声もあり、多くの人にとって大きなメリットになる可能性があります。
3. 将来的な利便性の向上
現時点ではいくつかの問題があるものの、将来的にはさらに利便性が向上する可能性があります。「過渡期ですよ。まだ不便が残っていますが、5年後、10年後には早く取れる、全ての所で受け入れる、そういう制度になりますから、いずれはみんな持つようになると僕は思います」という意見もあります。
デジタル化の進展に伴い、今後さまざまなサービスとの連携が進めば、より便利になる可能性が高いと言えるでしょう。
実際の利用者の声
マイナ免許証が始まったばかりということもあり、実際の利用者の声はまだ少ないですが、いくつか見てみましょう。
東京都江東区の警視庁江東運転免許試験場での取材では、「更新の手数料が安いといっても数百円レベルでしょ。マイナ保険証が終わったと思ったら免許証。わけわかんないよ」という否定的な声がある一方で、ホテルに勤務する32歳の方は「手数料も安くなり、住所変更もしやすい。オンラインで免許更新講習も受講できる」として、マイナ免許証に前向きな姿勢を示しています。
また、免許センターでの調査では、12人中「2枚持ち」は2人、「免許証のみ」が7人、「マイナ免許証のみ」を選ぶという人はわずか3人だったと報告されています。ホンダが行ったアンケートでも、「マイナ免許証に一体化する」という人は29.1%に留まっているとのことです。
これらの声からは、多くの人がまだマイナ免許証に慎重な姿勢を示している様子がうかがえます。「システムが落ち着いてからマイナ免許証を作っても遅くはない」という意見もあり、様子見の人が多いようです。
どのような人にはおすすめ?
マイナ免許証のメリットとデメリットを考慮すると、どのような人にはおすすめできるのでしょうか?
まず、頻繁に住所変更がある人には、マイナ免許証の利点が大きいといえます。市区町村役場での住所変更手続きだけで免許証の変更も同時にできるため、二重手続きの手間が省けます。
また、免許更新時の講習をオンラインで受けたい優良運転者や一般運転者にもメリットがあります。特に、運転免許センターまで遠い地域に住んでいる人にとっては、時間と交通費の節約になるでしょう。
一方で、以下のような人には現時点ではおすすめしにくい面もあります。
- 日常的に車を使う必要があり、免許証の即時再発行が必要になる可能性がある人
- レンタカーなどを頻繁に利用する人(対応が事業者によって異なるため)
- マイナンバーカードの有効期限と免許証の更新時期が近い人(手続きが二重になる可能性)
専門家の見解
マイナ免許証に関しては、専門家からもさまざまな意見が出ています。
CBCラジオの大石邦彦アナウンサーは「結論から言うと、僕のおすすめは『二刀流』か、従来の運転免許証のままか。マイナ免許証1点だけは…まだちょっと心許ないかな、という感じがいたします」と述べています。
また、SPキャスターのパックンは「過渡期ですよ。まだ不便が残っていますが、5年後、10年後には早く取れる、全ての所で受け入れる、そういう制度になりますから、いずれはみんな持つようになると僕は思います」と将来的な見通しを示しています。
CBCの生本ひなの記者は「そうした不安に対してしっかりリスクを解消すること、そしてデジタル化のメリット、例えば、行政手続きの効率化や医療・サービスの質の向上などについて納得感が持てるように伝えていく必要がありますね」と指摘しています。
結論:マイナ免許証は本当に「やばい」のか?
マイナ免許証に関するネット上の「やばい」という評判は、一部事実に基づいているものの、必ずしも全面的に当てはまるわけではないようです。確かに、紛失時の再発行の遅さやマイナカード更新時の問題、情報確認の手間などのデメリットは存在します。しかし、住所変更手続きの簡素化やオンライン講習の利用など、状況によっては大きなメリットもあります。
現時点では、自分のライフスタイルや利用状況に合わせて判断するのが最も賢明な選択と言えるでしょう。特に急いでマイナ免許証に切り替える必要はなく、「システムが落ち着いてから作っても遅くはない」という意見は理にかなっています。
また、「二刀流」(従来の免許証とマイナ免許証の両方を持つ)という選択肢も、移行期間中のリスクを軽減する方法として考慮する価値があります。特に、紛失時のリスクや事業者の対応の違いを気にする人にとっては、両方を持っておくことで万が一の際の安心感が得られるでしょう。
最終的に、マイナ免許証が「やばい」かどうかは、個人の状況やニーズによって大きく異なります。デメリットを理解した上で、自分にとってメリットがあるかどうかを判断することが重要です。また、現在の問題点の多くは今後のシステム改善によって解決される可能性があることも考慮すべきでしょう。
マイナ免許証は、デジタル化社会への移行過程にある一つの施策です。初期段階では不便や混乱があるのはある程度避けられないことかもしれません。しかし、長期的には社会全体の効率化やサービス向上につながる可能性もあります。現状では様子見という選択も十分に合理的ですが、将来的には多くの人が利用することになる可能性も高いと言えるでしょう。
実際の例としてCBCラジオの取材では、「マイナ免許証のみ」を選んだのはわずか3人だったということですが、これはまだ始まったばかりの制度であることを考えると当然かもしれません。新しいシステムが社会に定着するには時間がかかるものです。
いずれにしても、マイナ免許証が「やばい」という評判は、一部誇張されている面もあり、実際には個人の状況に応じて判断すべき問題だと言えるでしょう。デメリットを理解した上で、自分のライフスタイルに合わせて選択することが最も重要です。そして何より、今後のシステム改善や社会的な受け入れ状況を見守りながら、適切なタイミングで判断することが賢明な選択と言えるでしょう。
マイナ免許証は確かに欠点もありますが、利点も多く、将来的にはさらに便利になる可能性を秘めています。現在はまだ移行期間にあり、システムの安定性や社会的な受け入れにはもう少し時間がかかるかもしれませんが、長い目で見ればデジタル社会の一部として定着していく可能性は高いのではないでしょうか。


