マイナ保険証の”デメリット”がやばいといわれているのはなぜ?
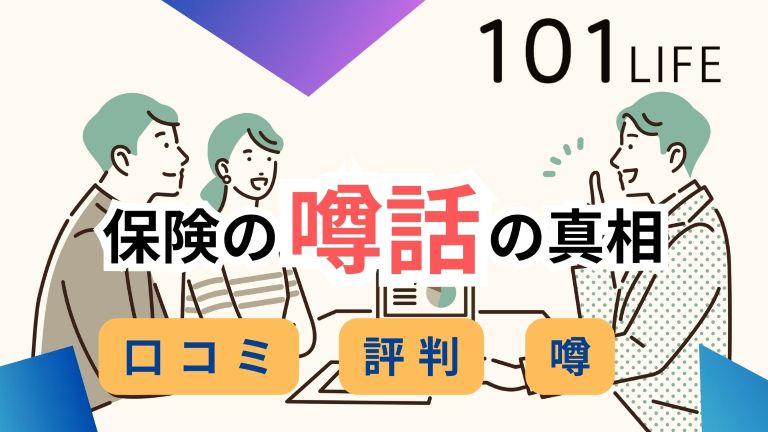
”マイナ保険証はヤバイのでやめたほうがいい”と口コミや評判で言われている原因について掘り下げて解説します
マイナ保険証は本当に”やばい”のか、デメリットとメリットから真相に迫る
マイナ保険証のデメリットと真相:口コミで「やばい」と言われている理由を徹底調査
マイナ保険証についてネットの口コミや評判から真相を掘り下げてみました。2021年10月から本格運用が始まり、2024年12月には従来の健康保険証の新規発行が廃止されるマイナ保険証。SNSやインターネット上では「やばい」「やめたほうがいい」という否定的な声が目立ちます。一方で、政府は利便性を強調し普及を推進しています。本当にデメリットばかりなのでしょうか?それとも思いこみや誤解から生まれた評判なのでしょうか?今回は口コミで語られる問題点と良い評判の両面から、マイナ保険証の真実に迫ります。
マイナ保険証とは?基本情報を確認
マイナ保険証とは、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようにしたものです。マイナンバーカードのICチップに搭載された電子証明書を利用して、医療機関や薬局での受付や本人確認を行うシステムとなっています。
2021年10月から本格運用が開始され、2024年12月2日からは従来の健康保険証の新規発行が廃止されました。ただし、その時点で有効な健康保険証は最長1年間使用でき、その後は「資格確認書」が交付されるとのことです。
重要な点として、マイナンバーカードの取得自体は任意であり、マイナ保険証の利用も強制ではありません。しかし、政府は普及を強く推進しており、様々な施策を展開しています。
ネットで噂される「やばい」デメリット
1. 「個人情報漏えいのリスクがやばい」という声
ネット上の口コミで最も多いのが、個人情報漏えいへの懸念です。東京新聞のアンケートによると、マイナ保険証を使わない理由として最も多かったのが「情報漏えいが不安」(188人)でした。
「情報漏えいも怖いし将来何に使われるかもわからないものを作りたくありません。紙の保険証を残せばいいだけのことです」(京都府50代女性)という声や、「特定個人情報を持ち歩くことに不安しかないです」(茨城県50代女性)といった意見が寄せられているようです。
また、昨年には別人の情報がひもづけられるミスが発覚したことも不安を増幅させている要因のようです。「個人情報の漏洩問題や入力間違い問題が発覚してから『使ってください』とアナウンスされても、なかなか難しいと思うのが現状です」(東京都40代女性)という意見もあります。
2. 「強制的に使わされている感じがやめとけと思う」という誤解
マイナ保険証の利用は任意であるにもかかわらず、「必須だと勘違い」して登録した人が少なくないようです。東京新聞のアンケートでは、病院や薬局で利用を勧められた人のうち、10人に1人は必須と勘違いして登録していたことが明らかになっています。
「マイナンバーカードをお持ちでしょうか?」「2024年12月2日に現行の健康保険証の発行が終了します」といった声かけが、あたかも必須であるかのような印象を与えているケースがあるようです。
「十分な説明なく保険証がなくなると脅迫的な声かけをされたこと自体が不快だった」(青森県30代男性)、「マイナカードと保険証の紐付けを法律で決められているかのような説明をしている様子にいつも、高齢者の無知を利用して詐欺のようだなあと感じていた」(福岡県70代以上女性)といった批判の声も上がっています。
3. 「使い勝手の悪さがデメリット」との評価
マイナ保険証を実際に使っている人からも、システム面での不便さを指摘する声が少なくありません。
「使うたびに4ケタの暗証番号や個人情報についてなどの承諾ボタンをおさないといけないので、急いでいるときや混雑時に実用的でない」(埼玉県の30代女性)、「マイナで受付をやったことがあるが、スムーズにいかずやり直してこりごりだ」(千葉県70代以上男性)といった不満の声が寄せられています。
また、医療データの更新の遅さも問題視されています。「マイナ保険証持ってても意味ないじゃん」と患者から不満をぶつけられた薬剤師は、「新しいデータが表示されるのは1カ月以上先なので、直近の情報を把握するには、今まで通りお薬手帳も必要になる」と説明しています。
4. 「紛失時のリスクが高い」という欠点
マイナ保険証は、紛失した場合のリスクも指摘されています。「個人情報を含むため、紛失や盗難時には悪用されるリスクがあります。また、再発行には手数料1,000円(カード再交付800円、電子証明書200円)が必要で、手続き完了までに約1か月かかります」と警告されています。
「従来の保険証は急な通院も考慮して常に財布に入れているが、マイナ保険証になったらそういう訳にはいかず面倒。また、マイナカード紛失時にも再発行に長期間かかりメリットを全く感じない」(千葉県50代男性)という声もあります。
5. 「対応していない医療機関がある」というおすすめしない理由
マイナ保険証を利用するためには、医療機関や薬局がオンライン資格確認のシステムを導入している必要があります。「未導入や導入していても機器が使えない施設では、従来の健康保険証の提示が求められるため、利用の際に事前確認が必要です」とされています。
2024年3月現在、約90%の医療機関で対応しているとされていますが、一部対応していない医療機関があるため、「マイナ保険証をお持ちの方も念の為、受診の際に健康保険証をお持ちいただくことをおすすめします」と案内されています。
6. 「マイナンバーを使うという誤解」から生じる不安
マイナ保険証に対する不安の一部は、「マイナンバーを使う」という誤解から生じているようです。実際には、マイナ保険証では12桁のマイナンバー(個人番号)は使用していません。
「マイナンバーカード」という名前から受ける印象として、このカードを使うと何でもマイナンバーに紐付いてしまうと誤解している可能性があるとの指摘もあります。
7. 「有効期限と更新の手間」という問題点
マイナンバーカード自体は10年(未成年者は5年)、電子証明書は5年の有効期限があり、この期限が切れると利用ができなくなります。「有効期限の通知書が事前に届きますので忘れずに更新するようにしましょう」と注意喚起されています。
「認知症になれば更新手続きが難しくなるのでは?」(70代女性)、「将来高齢になり自ら更新できなくなった場合、どうすればよいか知りたい」(70代男性)といった将来的な不安の声も聞かれます。
8. 「システム障害時の対応が不明確」という懸念
「オンライン資格確認と呼ばれる医療機関で使用しているシステムに不具合が出た場合に利用できないことがあります」と指摘されています。
「停電時や機械が故障した場合、医療費は全額負担になるのか」(40代女性)という疑問も寄せられており、緊急時や障害発生時の対応が不明確な点が不安要素となっているようです。
噂の真相と誤解を解く
ここまで様々なデメリットや懸念点を見てきましたが、その中には誤解から生じているものもあります。真相を整理してみましょう。
1. マイナンバー使用に関する誤解
マイナ保険証ではマイナンバー(12桁の個人番号)自体は使用していません。利用されるのはICチップ内の電子証明書です。病院などの窓口では、医療機関のスタッフが患者のマイナンバーを知ることはできない仕組みとなっています。
2. 強制・必須化の誤解
マイナンバーカードの取得自体が任意であり、マイナ保険証の利用も強制ではありません。現行の保険証が使えなくなっても、マイナ保険証を登録していない人には「資格確認書」が交付されます。これは従来の保険証とほぼ同様のもので、申請不要で交付され、最長5年間有効とされています。
3. 情報漏えいリスクへの対策
情報漏えいへの懸念は理解できますが、マイナ保険証のシステムには様々なセキュリティ対策が施されています。顔認証や暗証番号による本人確認、データの暗号化などが行われており、安全性への配慮がなされているようです。ただし、「ひも付けミス」のような人為的ミスへの不安は残りますので、慎重な運用が求められるでしょう。
4. 対応医療機関の拡大
2023年4月からは、すべての医療機関や薬局でシステム導入が義務付けられており、対応施設は着実に増加しています。現在では90%以上の医療機関で対応しているとされており、今後さらに拡大していくと予想されます。
「やばくない」マイナ保険証のメリットと利点
否定的な口コミが目立つ一方で、マイナ保険証には確かな利点もあります。ここからは、実際に使うことで得られるメリットを見ていきましょう。
1. 迅速な医療手続きで待ち時間短縮
マイナ保険証を利用することで、受付での手続きがよりスムーズに進むようになります。「マイナ保険証を提示するだけで、システムが自動的に必要な情報を読み取るため、受付担当者が手動で情報を入力する手間が省けます。患者は長い時間待たされることなく、速やかに診療を受けることができます」とされています。
「私は救命センターで事務をしていますが、マイナ保険証の患者さんは自分で顔認証やパスワードにより保険登録をしてくれるので事務としては楽になりました」(埼玉県10代男性)という医療現場からの声もあります。
2. 手続きなしで高額療養費制度を利用可能
医療費が高額になった場合に利用できる高額療養費制度について、マイナ保険証があれば手続きが簡素化されます。「従来は、窓口で限度額以上の支払いを抑えるため、事前に役所で限度額適用認定証の書類申請が必要でした。しかし、マイナ保険証を利用すれば、申請手続きや窓口での一時的な費用負担が不要になります」。
「事前に限度額適用認定証等の交付を受けなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。また、限度額適用認定証等の更新手続きも不要になります」と案内されており、手続きの簡素化による利便性向上は大きなおすすめポイントと言えるでしょう。
3. 健康管理に役立つデータ閲覧
「自分が処方された薬や特定健診の情報が、マイナポータルでいつでも見ることができます」。自分の健康状態を把握し、管理するためのツールとしても活用できるのがマイナ保険証の利点です。
「個人的には処方されている薬が多いので、その管理には便利だと思う」(鳥取県40代女性)、「薬手帳が持参してない場合 便利だと感じた」(埼玉県60代女性)といった体験談も寄せられています。
4. 確定申告の簡素化でやばくない使い勝手
マイナ保険証を利用すると、確定申告時の医療費控除の申請が簡単になります。「マイナポータルとe-Taxを連携することで、医療費控除のデータを自動入力できるようになります。医療費の領収書の管理が不要になるほか、データ入力の手間が省けるのが大きなメリットです」。
「医療費控除の確定申告を行うとき、マイナポータルで連携した医療費通知情報を使うことで自動入力できます。医療費通知(医療費のお知らせ)や医療費の領収書などから集計する手間がかからないため、確定申告が簡単になります」と説明されており、特に年末の確定申告時期には大きな負担軽減となるでしょう。
5. 転職や引っ越し時の利便性
「従来の健康保険証は、就職や転職、引っ越し時に更新手続きを行い、新しい健康保険証が届くまで待つ必要がありました。マイナンバーカードを保険証として使う場合、医療保険者への手続きが済んでいれば、新しい健康保険証の到着を待たずに、医療機関・薬局で健康保険証として利用できます」。
転職や引っ越しが増えている現代において、新しい保険証が届くまでの空白期間なく医療サービスを利用できる点は非常に便利と言えるでしょう。
6. 医療費の軽減効果
「政府は国民のマイナンバーカードの保険証利用を促すため、マイナ保険証を利用し診療情報の提供に同意した場合に、従来の健康保険証よりも医療費が安くなるように診療報酬を改定しています」。
具体的には、初診時に従来の健康保険証を使用した場合の自己負担額が3割負担で9円程度であるのに対し、マイナ保険証では3円程度と安くなる場合があるようです。金額は小さいものの、長期的に見れば医療費の節約につながる可能性があります。
マイナ保険証の効果的な活用と注意点
マイナ保険証を最大限に活用するための方法と、デメリットを回避するための注意点をまとめてみましょう。
1. 紛失対策
マイナンバーカードの紛失は大きなリスクとなりますので、日常的に持ち歩く場合は細心の注意が必要です。専用のカードケースを使用する、貴重品と一緒に保管するなどの対策が考えられます。また、紛失時の連絡先や手続き方法を事前に確認しておくことも重要です。
2. 併用の知恵
医療データが1カ月以上遅れて更新される点を考慮すると、お薬手帳との併用が望ましいでしょう。直近の処方情報はお薬手帳で確認し、過去の長期的なデータはマイナ保険証のシステムで確認するという使い分けができます。
3. 有効期限の管理
マイナンバーカード自体と電子証明書の有効期限を把握し、更新時期が近づいたら早めに手続きを行うことが大切です。特に電子証明書は5年ごとの更新が必要ですので、期限切れにならないよう注意しましょう。
4. システム障害時の備え
システム障害や停電時など、マイナ保険証が使えなくなる可能性もゼロではありません。緊急時の対応方法について、かかりつけの医療機関に事前に確認しておくと安心です。また、現行の保険証または資格確認書を持参しておくことも一つの対策となるでしょう。
まとめ:マイナ保険証は本当に「やばい」のか?
マイナ保険証についてネット上で「やばい」「やめたほうがいい」と噂される理由と、実際のメリットを検証してきました。
確かに情報漏えいの懸念、紛失時のリスク、システム面での不便さなど、いくつかの欠点があることは否定できません。特に、カードリーダーの操作が高齢者にとって難しい場合があることや、医療データの更新が遅いといった点は、改善の余地があるでしょう。
一方で、高額療養費制度の簡便化、確定申告の簡素化、転職時の便利さなど、「やばくない」便利な利点も多数あります。また、「マイナンバーを使う」「必須化されている」といった誤解に基づく不安も少なくないことがわかりました。
最終的には、個人の価値観や生活スタイルによって、マイナ保険証の利便性とリスクのバランスは異なってくるでしょう。ただ、今後さらに普及が進み、システムも改善されていくことが予想されますので、完全に拒絶するよりも、メリットとデメリットを正しく理解した上で、自分に合った使い方を選択することがおすすめです。
政府の情報提供が不十分で誤解を招いている面もありますが、デジタル社会における医療サービスの効率化という観点では、マイナ保険証には大きな可能性があると言えるでしょう。利点をうまく活用しながら、注意点にも目を配り、賢く利用していくことが重要なのではないでしょうか。
マイナ保険証は「やばい」のではなく、まだ発展途上の制度であり、今後の改善によってより便利なツールになっていくことが期待されます。個人情報保護の強化やシステムの使いやすさの向上など、ユーザーの声を反映した改善が進むことで、より多くの人に利用されるサービスになることを願っています。
(注:この記事は2025年4月時点の情報に基づいています。制度変更等により内容が変わる可能性がありますので、最新情報をご確認ください。)


