雇用保険被保険者番号の調べ方をわかりやすく解説
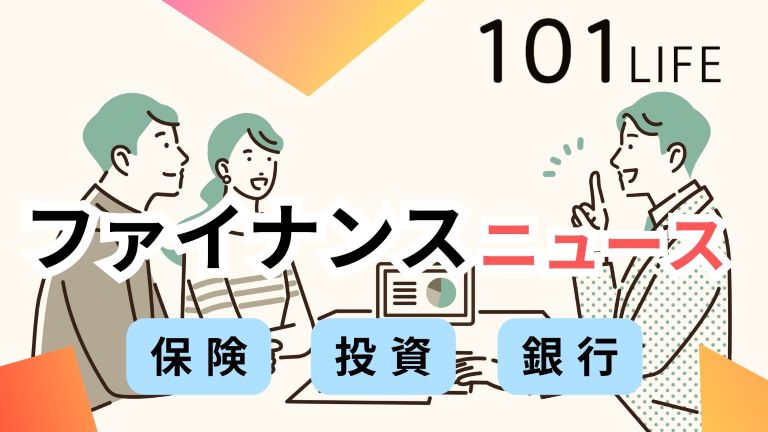
雇用保険被保険者番号の調べ方を徹底解説
失業給付や転職に必要な情報を知る方法
雇用保険被保険者番号は、転職時や失業給付を受ける際に必要となる大切な番号です。しかし、普段はあまり使用する機会がないため、いざ必要になった時に「どこで確認できるのか」「紛失してしまった場合はどうすればよいのか」と困ってしまう方も多いのではないでしょうか。この記事では、雇用保険被保険者番号とは何か、どのような場面で必要になるのか、そして調べ方や紛失時の対処法について詳しく解説します。転職活動中の方や、失業給付の申請を考えている方は、ぜひ参考にしてください。
雇用保険被保険者番号とは
被保険者一人につき固有の番号
雇用保険被保険者番号とは、雇用保険に加入している被保険者一人ひとりに付与される固有の番号です。この番号は、雇用保険に初めて加入するときに発番されます。
具体的には、「4桁-6桁-1桁」の合計11桁で構成される番号となっています。例えば「1234-123456-1」のような形式です。この番号は、雇用保険に関連する様々な手続きや申請の際に必要となるため、非常に重要な情報と言えます。
なお、1981年7月6日以前に雇用保険に加入した方には、「上段6桁・下段10桁」の16桁の番号が割り振られていることもあります。その場合は、下段の10桁に「0」を足した数字が雇用保険被保険者番号となります。
基本的に一生同じ番号を使用する
雇用保険被保険者番号の大きな特徴として、一度発番されると、転職しても番号は変わらず、原則、一生使うことになるという点が挙げられます。つまり、会社を何度変わっても、基本的には同じ番号を使い続けることになります。
これは、雇用保険の被保険者期間を通算するために重要な仕組みです。同一の番号で管理することで、複数の会社での雇用期間を合算し、失業給付などの給付要件を正確に判断することができるのです。
パート・アルバイトの方でも、雇用保険の加入条件(1週間の所定労働時間が20時間以上、31日以上の雇用見込みがあるなど)を満たしていれば被保険者番号が付与されます。
雇用保険被保険者番号が記載されている書類
雇用保険被保険者証
雇用保険被保険者番号は、主に「雇用保険被保険者証」で確認することができます。雇用保険被保険者証とは、適用事業所の雇用保険に加入していることを証明するものです。
入社した際、適用事業所の所轄ハローワークにて加入手続きを行うと交付されます。ここには、その事業所における取得年月日、被保険者名、被保険者番号、被保険者の生年月日などが記載されています。
雇用保険被保険者証は、映画のチケットのような形状をしており、厚紙に個人情報や被保険者番号などが記載されています。通常は入社時に会社から交付されますが、会社で保管されていることも多いため、退職時に初めて受け取るケースも少なくありません。
離職票
もう一つの確認方法として、「離職票」があります。離職票とは、会社を退職した後に退職者に交付されるもので、ハローワークにて求職し、失業の給付を受けるときに必要な書類です。
会社は退職日の翌日から10日以内に手続きし、退職者に交付しなければなりません。離職票には、その会社での資格取得年月日、離職年月日、直近の賃金、離職理由などが記載されており、退職者が基本手当(失業等給付の求職者給付)を受ける際の支給額を決定する元になる情報です。
離職票の最上段にある「被保険者番号」という項目で、雇用保険被保険者番号を確認することができます。
マイナポータル
マイナンバーカードを持っている方が、在籍している会社や、これまで在籍していた会社にマイナンバーを届け出ている場合は、マイナポータルで雇用保険に関する手続きの履歴(資格取得・喪失など)を確認することができます。そこには雇用保険被保険者番号の情報も含まれています。
雇用保険被保険者番号が必要になるケース
雇用保険被保険者番号は、いくつかの重要な場面で必要となります。それぞれのケースについて詳しく見ていきましょう。
転職時の雇用保険加入手続き
転職して新しい会社で雇用保険の加入手続きをする際に、雇用保険被保険者番号が必要になります。前の会社から交付された雇用保険被保険者証を一度提出し、返却された後は自分で保管するのが一般的です。書類がなくても、雇用保険被保険者番号がわかれば、それだけで手続きすることも可能です。
通常は、転職先から雇用保険被保険者証の提示を求められます。原本がない場合はコピーでも提出できますし、入社日までに紙面で用意できない場合は、必要な情報を担当者に伝えることで対応可能なケースもあります。
失業保険(基本手当)の申請
退職後に次の仕事が決まっていない場合は、住所を管轄するハローワークで求職の申し込みと失業保険の受給資格の決定を受けます。その際に、前の会社から送られてきた離職票を提出し、そこに記載されている雇用保険被保険者番号で手続きを進めることになります。
失業保険を受給するには条件もあり、一般的には離職する前2年間で雇用保険への加入期間が通算12か月以上あること、就職する意思と能力がある事などがあげられます。
教育訓練給付金の申請
「教育訓練給付」は、一定の条件を満たす在職中の人や離職した人が、指定の教育訓練講座を自己負担で受講したときに、かかった経費の一部についてハローワークから給付金を受けられる制度です。具体的には、厚生労働大臣が指定する講座を受講・修了した際に、受講費用の一部(最大50%、年間上限40万円)が支給されます。
この給付の申請は自身ですることになるため、雇用保険被保険者番号の確認が必要となります。雇用保険に3年(初回は1年)以上加入している在職中の人や離職をした人が対象です。
育児・介護休業給付、高年齢雇用継続給付
「育児休業給付」や「介護休業給付」、また60歳以降の労働者に賃金の減額分を一部補填する「高年齢雇用継続給付」を受けるときは、いずれも雇用保険被保険者番号を使用してハローワークへ申請します。
ただし、これらの手続きは一般的には会社が行うため、被保険者が手続きを行うケースは少ないでしょう。
特別支給の老齢厚生年金の請求
「特別支給の老齢厚生年金」とは、一定の条件を満たせば、65歳よりも早く老齢厚生年金を受給できる制度です。請求する時は、雇用保険との併給調整をするために、雇用保険被保険者番号を証明する書類(雇用保険被保険者証など)が必要になります。
この手続きも自身でするものなので、書類の準備が必要です。
雇用保険被保険者番号の調べ方
それでは、具体的に雇用保険被保険者番号を調べる方法について解説します。
雇用保険被保険者証で確認する
最も一般的な方法は、雇用保険被保険者証で確認する方法です。雇用保険被保険者証の中段にある「被保険者番号」という項目から確認することができます。
退職した際に会社から雇用保険被保険者証を受け取っていれば、そこで確認できます。在職中の場合は、会社が保管していることもありますので、必要に応じて会社に問い合わせると良いでしょう。
離職票で確認する
退職後に会社から受け取る「離職票」でも、雇用保険被保険者番号を確認できます。離職票の最上段にある「被保険者番号」という項目に記載されています。
離職票は、退職した日の翌日から10日以内に元の会社がハローワークで手続きをしなければならないことになっています。手続きが済むと、「離職票-1」「離職票-2」が発行され、通常は退職後2週間〜1カ月ほどで会社から送られてきます。
ただし、失業給付の手続きを行うと離職票は手元に残りませんので注意が必要です。
マイナポータルで確認する
マイナンバーカードを持っている人で、会社にマイナンバーを届け出ている場合は、マイナポータルで雇用保険の手続き履歴を確認することができます。そこには雇用保険被保険者番号も含まれています。
会社に確認する
雇用保険被保険者番号は、在職中であれば勤務先が把握しているので、会社に直接確認するのが早道です。離職した人は、以前働いていた会社に問い合わせるという方法もあります。
ハローワークで照会する
雇用保険被保険者証も離職票もなく、被保険者番号がわからない時は、ハローワークにて被保険者証の再発行ができます。また、会社が雇用保険加入の手続きを行う際に、所轄ハローワークに照会することも可能です。その場合、前職の会社名、所在地、被保険者期間、本人確認できるものなどが必要です。
雇用保険被保険者証を紛失した場合の再発行方法
雇用保険被保険者証を紛失した場合でも、再発行することが可能です。いくつかの方法について詳しく見ていきましょう。
ハローワークの窓口で申請
雇用保険被保険者証を紛失した場合、居住地を管轄するハローワークで再発行してもらうことができます。窓口なら、即日無料で再発行が可能です。
手続きには以下のものが必要になります。
- 前に働いていた会社の正式名称、住所と電話番号
- 本人確認書類(運転免許証、健康保険証、パスポートなど)
- 印鑑
ハローワークに行き、「雇用保険被保険者証再交付申請書」に必要事項を記入して提出します。申請が受理されると、数日〜1週間程度で新しい雇用保険被保険者証が発行されますが、即日発行される場合もあります。
電子申請(e-GOV)で申請
インターネットを通じてe-GOVで電子申請することも可能です。ただし、電子署名の取得などに費用がかかる場合もあります。
郵送で申請
郵送でも申請することができます。必要書類を郵送して手続きを行う方法ですが、切手代などの費用がかかります。
事業主による再発行手続き
事業主(会社)が従業員に代わって再発行手続きを行うことも可能です。この場合、「雇用保険関係各種届書等再作成・再交付申請書」を使用します。ただし、この書類には「雇用保険被保険者証」が選択肢として明記されていないため、空白部分に「雇用保険被保険者証」と記載して提出する必要があります。
雇用保険被保険者番号に関する注意点
複数の被保険者番号を持っている場合の統合
雇用保険被保険者証が手元になく、前職の加入の有無について確認しないまま、取得区分を「新規」として加入手続きすると、新しい被保険者番号が発番されます。結果として、複数の番号を持ってしまうことになります。
1つの番号に統合しなければ、基本手当(失業等給付の求職者給付)などを受ける際、複数の会社の被保険者期間が通算されないため、本来より少ない給付日数となるなど、本人に不利益となってしまいます。
被保険者番号を統合するためには、「雇用保険被保険者資格取得・喪失届等訂正・取消願」を所轄ハローワークに提出します。その際、被保険者証や被保険者番号がわかる書類を添付します。
番号が変わるケースについて
雇用保険被保険者番号は、基本的には変わりませんが、以下のようなケースでは変わる可能性があります。
- 雇用保険から外れて7年以上経過した場合:雇用保険から外れて最後の離職日から7年経過すると、この雇用保険被保険者番号は失効し利用できなくなります。つまり、専業主婦/主夫、フリーランスなどに転身してから7年以上経てから雇用保険に入り直すと、別の新しい番号を受け取ることになります。
- 再発行時に変わるケース:雇用保険被保険者証を紛失したなどの理由で、新たに雇用保険被保険者証を発行した場合に、例外として番号が変わるケースがあります。
雇用保険被保険者証の保管の重要性
雇用保険被保険者証は、転職や失業給付の申請など様々な場面で必要となります。しかし、普段はあまり使う機会がないため、紛失してしまうリスクもあります。
万が一被保険者番号が確認できず、新しい被保険者証を発行することになった場合、それまでの加入年数のデータは引き継がれない可能性があります。加入期間が少なくなるため、失業等給付の申請条件を満たさない、受給内容が変わるなどの可能性があります。
このため、雇用保険被保険者証は紛失しないよう大切に保管しておくことが重要です。また、原本を提出する前にはコピーを取って保管しておくとよいでしょう。
よくある質問(FAQ)
Q: 転職したら雇用保険被保険者番号は変わりますか?
A: 基本的に、雇用保険被保険者番号は転職しても変わりません。一度発番されると、転職しても番号は変わることなく、原則、一生使うことになります。ただし、雇用保険から外れて最後の離職日から7年経過すると、この番号は失効し利用できなくなります。
Q: アルバイトやパートでも雇用保険被保険者番号はありますか?
A: はい、アルバイトやパートなどの非正規雇用でも、雇用保険の加入条件(1週間の所定労働時間が20時間以上、31日以上の雇用見込みがある、学生ではない)を満たしていれば雇用保険に加入でき、雇用保険被保険者番号が割り振られます。自分が雇用保険に加入しているかわからない場合は、給与明細の「雇用保険」欄を確認するか、加入条件を満たしているかセルフチェックしてみましょう。
Q: 雇用保険被保険者証を紛失した場合、転職先ではどうすればよいですか?
A: 雇用保険被保険者証を紛失した場合でも転職先での手続きは可能です。以下の対応が考えられます。
- ハローワークで再発行する:最寄りのハローワークで雇用保険被保険者証を再発行してもらい、それを転職先に提出する。
- 転職先に相談する:転職先の担当者に状況を説明し、どのような情報が必要か確認する。前職の会社名や所在地など基本情報があれば、ハローワークでの照会が可能な場合もある。
- 前職の会社に問い合わせる:以前働いていた会社に雇用保険被保険者番号について問い合わせる方法もある。
Q: 複数の雇用保険被保険者番号を持っている場合はどうすればよいですか?
A: 複数の雇用保険被保険者番号を持っている場合は、番号を統合する手続きが必要です。そうしないと、失業等給付を受ける際に雇用保険の加入期間が通算されず、不利益を被る可能性があります。在職中の場合は会社を通じて、離職中の場合はハローワークで「雇用保険被保険者資格取得・喪失届等訂正・取消願」を提出して統合手続きを行いましょう。
まとめ
雇用保険被保険者番号は、雇用保険に加入する個人に割り振られる11桁の固有番号で、転職や失業給付の申請など様々な場面で必要となる重要な情報です。この番号は、雇用保険被保険者証や離職票で確認することができ、基本的には一生同じ番号を使い続けます。
紛失した場合も、ハローワークでの再発行手続きが可能ですので、安心してください。ただし、雇用保険から外れて7年以上経過すると番号が失効する可能性がありますので注意が必要です。
また、複数の被保険者番号を持っている場合は統合の手続きが必要です。統合しないと、失業等給付を受ける際に不利益を被る可能性があります。
転職や失業給付の申請など、人生の重要な局面で必要となる雇用保険被保険者番号。この記事を参考に、ご自身の番号を確認し、大切に保管しておいてください。いざという時に慌てずに済むよう、雇用保険被保険者証のコピーを取るなど、事前の準備も忘れずに行いましょう。


