変額保険は”やめたほうがいい”といわれているのはなぜ?
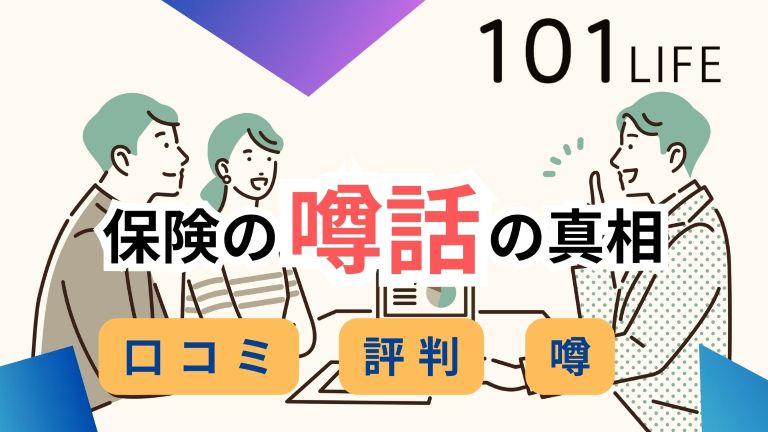
”変額保険はヤバイのでやめたほうがいい”と口コミや評判で言われている原因について掘り下げて解説します
変額保険は本当にやめたほうがいいのか、デメリットとメリットから真相に迫る
変額保険が「やばい」「やめたほうがいい」という噂についてネットの口コミや評判から真相を掘り下げてみました。近年、資産形成への関心が高まる中で、保険と投資の要素を兼ね備えた変額保険は、さまざまな意見が飛び交う商品となっているようです。本記事では、変額保険の仕組みを理解した上で、悪い評判とその背景、そして良い評判まで幅広く検証し、この保険商品の実態に迫ります。
変額保険とは
変額保険は、保険料を株式や債券などで運用し、その実績に応じて保険金や解約返戻金の額が変動する保険商品です。一般的な定額保険とは異なり、投資性が強い特徴を持っています。
変額保険の基本的な仕組み
変額保険は、生命保険と投資信託を組み合わせたような商品であると言われています。契約者が支払った保険料の一部は「特別勘定」によって運用され、その運用実績によって将来受け取る金額が変動します。
変額保険には主に以下の種類があるようです。
- 有期型(養老保険):一定期間を保障するタイプ
- 終身型(終身保険):保障が一生涯続くタイプ
- 変額個人年金保険:将来の年金受取額が運用実績によって変動するタイプ
重要な点として、変額保険では死亡保険金は最低保証されますが、解約返戻金や満期保険金には最低保証がない場合が多いとされています。
「やばい」「やめたほうがいい」と言われる理由
ネット上では、変額保険について「やばい」「やめたほうがいい」という声が見られます。その主な理由を見ていきましょう。
1. 元本割れのリスクがある
変額保険の最も大きな批判点として、元本割れのリスクがあることが挙げられています。運用実績が振るわない状態で解約をしたときや満期を迎えたとき、払い込んだ保険料の総額を下回る「元本割れ」を起こすリスクがあるようです。
特に、加入してから短期間で解約した場合、「解約控除」と呼ばれる手数料が発生して、元本割れを起こすケースも少なくないと言われています。解約控除は、一般的に契約から10年以内に解約した場合に発生する手数料で、解約するタイミングが早いほど、解約返戻金から高い金額が差し引かれるとのことです。
2. 経済環境・景気に影響されやすい
変額保険は、景気に影響されやすい側面があると指摘されています。デフレ期に株式相場が下落して運用成績が悪くなった場合、保険金や解約返戻金の受取額が目減りする恐れがあるようです。
リーマンショックのような不景気が訪れると、市場全体の株価が下がり、特別勘定の運用に悪影響を及ぼす可能性があるとされています。特に、満期や解約のタイミングで景気が悪化した場合、必要な時に十分な資金が得られないリスクがあることが指摘されています。
3. 商品が複雑でわかりにくい
変額保険は一般的な生命保険と比べて、商品の仕組みが複雑でわかりにくいため「やめたほうがいい」と言われることもあるようです。
投資の知識がない方にとっては仕組みが難しく感じられるかもしれません。実際に、2019年度に国民生活センターに寄せられた特定生命保険(変額保険や外貨建て保険など)に関する相談件数は321件にのぼるとの報告もあります。
4. 手数料が高い
変額保険では、手数料が23~26%ほどかかるという試算があるようです。これは良心的な投資信託の約400倍の費用になると指摘されています。
手数料の高さは資産運用の効率を下げる要因となり、純粋な資産形成目的であれば他の金融商品の方が効率的ではないかという意見もあるようです。
5. 受け取れる金額が確定しない
変額保険は市場の動きに左右されるため、将来もらえるお金の額が確定していないという点も批判されています。
教育費用や住宅購入費用などの計画的な貯蓄を目的としている場合、受け取れる金額が変動するため使いにくいという意見もあるようです。将来のライフイベントに向けた確実な資金準備を望む場合は、定額の保険商品や預貯金の方が適しているという見方もあります。
変額保険のメリット・良い評判
一方で、変額保険には以下のようなメリットや良い評判もあるようです。
1. 保障と資産形成の両立
変額保険の大きな利点として、死亡保障の機能を備えながら資産形成もできる点が挙げられています。
契約期間中に万が一のことがあった場合には、死亡保険金や高度障害保険金などを受け取れ、さらに解約時には解約返戻金を受け取れるため、保障と資産形成を両立できるのがメリットだと言われています。
2. 死亡保険金は最低保証される
変額保険では、運用実績に関わらず死亡保険金は最低保証されるという特徴があります。
運用実績が悪くても、契約時に決めた最低保証額を下回ることはなく、万が一の備えを確保しながら、運用による収益が期待できるのは、変額保険ならではのメリットとされています。
3. インフレ対策になる
変額保険は、定額保険と比べてインフレ対策になるというメリットもあるようです。
総務省統計局の2023年12月分の消費者物価指数によると、日本の物価上昇率は昨年同月比で2.6%上昇しており、銀行の預金金利や定額保険の返戻率を年率換算したものと比べて10倍以上の率になっているとのことです。
変額保険で運用をすることで、運用成果によってはインフレによる資産の目減りを抑えられる可能性があると考えられています。
4. 税制上のメリット
変額保険には税制上のメリットもあるようです。生命保険料控除により税金の負担が軽減される点が挙げられています。
例えば、変額保険をはじめとした一般生命保険の保険料を年間8万円を超えて支払っている場合、所得税が課税所得から4万円、住民税が課税所得から2万8,000円差し引かれるとのことです。
また、変額保険では途中で運用商品を変更した場合でも、満期まで非課税とされています。NISA以外で投資した株や投資信託のように、売却益に20.315%の税金が発生することはないようです。
5. 相続対策として有効
変額保険は相続対策としても有効である可能性があります。
亡くなったときに、遺族に残されるのが銀行預金や投資信託だと相続税がかかりますが、保険金であれば一定額まで非課税となります。変額保険による運用がうまくいった場合、死亡保険金が増加することもあるので、保険金が定額の保険よりも、インフレリスクなどに対応できる可能性があると指摘されています。
変額保険が向いている人・向いていない人
変額保険について、どのような人に向いているのか、また向いていないのかを見ていきましょう。
向いている人の特徴
検索結果によると、以下のような人に変額保険が向いているとされています。
- 経済的な余裕がある人
- 保障だけでなく長期的な資産運用を望む人
- 余剰資金で運用できる人
- 相続対策が必要な人
- 投資の知識があり、リスクを理解している人
- 資産運用に時間をかけられない人
特に、変額保険は「余剰資金」で運用することが推奨されているようです。万が一運用がうまくいかなかった場合でも、日々の生活や将来のライフプランに与える影響を最小限に抑えることができるからだと考えられています。
向いていない人の特徴
一方で、以下のような人には変額保険が向いていないとされています。
- 投資のリスクを理解していない人
- 確実な返戻額を求める人
- 短期間での解約を予定している人
- 教育費や住宅購入など、計画的な貯蓄が必要な人
- 死亡保障が不要な単身者
変額保険はやばくないという見方
変額保険については「やばい」という評判がある一方で、この商品を正しく理解すれば「やばくない」という見方もあるようです。
変額保険の特徴をよく理解しておけば、ある程度対処・カバーできるデメリットばかりなので、必要以上に不安を感じる必要はないという意見もあります。
また、資産運用の世界ではリスクとリターンは比例するとされています。リスクが小さい一般的な生命保険は、得られるリターンも少ないという側面があるようです。
将来に向けた資産形成を目的として変額保険に加入する場合は、「元本割れするリスクがある」ことは受け入れなければならない事実の一つであるという見方もあります。
さらに、元本割れリスクはドルコスト平均法を活用することである程度軽減できるとも言われています。平準払い(月払い・年払いなど)の変額保険であれば、自然とドルコスト平均法を実践できるメリットがあるようです。
2025年現在の変額保険事情
2025年の現在、投資環境の好転やインフレを背景に、変額保険への注目が高まっているようです。
2025年2月の時点では、「はなさく生命」の新商品がランキングの上位に入るなど、生命保険各社の新商品投入が相次いでいるとのことです。
一方で、保険のプロからは「変額保険そのものをお薦めしない」という声も多いようです。長期の資産形成の第1選択肢は、税制優遇やコストの面でiDeCo(個人型確定拠出年金)やつみたてNISA(少額投資非課税制度)の活用を考えた方が無難だという意見もあるようです。
変額保険のおすすめポイント
変額保険を検討する際のおすすめポイントをいくつか紹介します。
1. 長期的な視点で考える
変額保険は長期的な視点で考えることがおすすめです。保険のプロの中には「長期的に加入できるのであれば素晴らしい商品だと思っています」という意見もあります。
特に、平準払い(月払いや年払い)で長期間にわたって保険料を支払うことで、ドルコスト平均法の効果が期待できるとされています。これにより、市場の変動による影響を平準化できる可能性があるようです。
2. 信頼できる保険会社やプランナーを選ぶ
変額保険に加入する際は、信頼できる保険会社やプランナーを選ぶことが重要だとされています。商品内容をしっかりと説明してくれるプランナーとの出会いが、変額保険を活用する上での鍵となるようです。
3. 資産配分を考慮する
変額保険の中には、複数の特別勘定から運用先を選べるものもあるようです。国内外の株式や債券など、収益性の高い商品で運用することも可能とされており、効率よく資産形成ができる点も魅力と言われています。
自分のリスク許容度や年齢に合わせた資産配分を考慮することが、変額保険を活用する上でのポイントとなるでしょう。
まとめ:変額保険は理解して活用すれば有効な選択肢
変額保険は「やばい」「やめたほうがいい」という評判がある一方で、正しく理解して適切に活用すれば、保障と資産形成を両立できる有効な選択肢と言えるかもしれません。
変額保険の最大の利点は、死亡保障を確保しながら資産運用もできる点です。また、インフレ対策や税制上のメリットもあり、長期的な視点で考えれば魅力的な商品であると言えるでしょう。
一方で、元本割れのリスクや手数料の高さ、商品の複雑さなどのデメリットもあります。これらを十分に理解した上で、自分のライフプランや資産状況に合わせて検討することが重要です。
変額保険は全ての人におすすめできる商品ではありませんが、経済的な余裕があり、長期的な視点で資産形成と保障を両立させたい人にとっては、検討する価値のある商品だと言えるでしょう。
最終的には、変額保険は「やばい」商品ではなく、正しく理解して適切に活用すれば、資産形成の選択肢の一つとして考えることができるのではないでしょうか。自分の状況や目的に合わせて、専門家に相談しながら検討することをおすすめします。

