保険証緑が”やばい”といわれているのはなぜ?
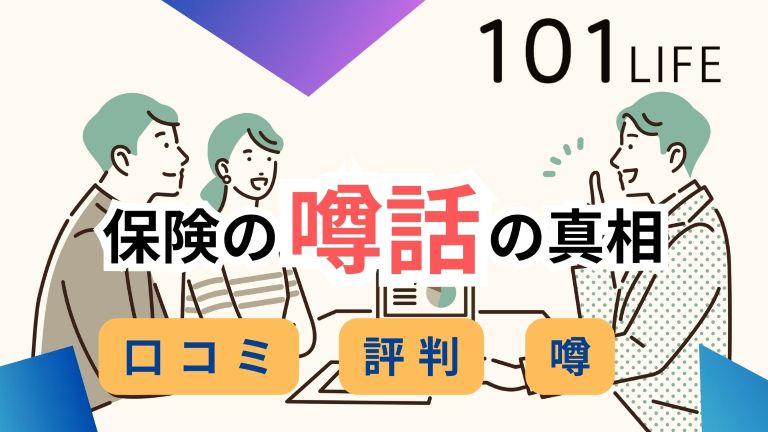
”緑色の保険証がやばい”と口コミや評判で言われている原因と真相について掘り下げて解説します
保険証の色、特に「緑色の保険証がやばい」という噂についてネットの口コミや評判から真相を掘り下げてみました。病院や薬局で提示する機会の多い健康保険証ですが、その色にはさまざまな種類があり、時に色によって特定の状況や立場が判断できるという噂が広がっているようです。本記事では、緑色の保険証に関する噂の真偽や、それに対する評判、そして保険証の色が持つ本当の意味について詳しく解説していきます。
保険証の色の種類と一般的な意味
健康保険証には様々な色がありますが、これらの色は一体何を意味しているのでしょうか。まずは、保険証の色の種類と一般的にどのような意味があるとされているのかを見ていきましょう。
保険証の色の基本的な分類
保険証の色は、加入している健康保険の種類によって異なることが多いとされています。一般的には以下のような色分けがあるようです。
- 青・水色・オレンジ: 協会けんぽ(全国健康保険協会管掌健康保険)
- 赤・ピンク: 組合管掌健康保険(組合保険)
- 黄色: 共済組合(公務員)
- 灰色・緑・ピンク・赤・紫: 国民健康保険
- 紫・黄色・緑: 後期高齢者医療制度
しかし、この色分けは絶対的なものではなく、保険者によって独自に決められているため、必ずしもこの通りではないことに注意が必要です。
保険証の色が意味するもの
保険証の色自体には法律的・制度的な意味はないとされています。色が異なっている背景としては発行元や加入する保険の種類を判別しやすくする目的があると考えられます。
保険証の色が異なる主な理由としては、以下のようなものが挙げられます。
- 発行元(保険者)による違い
- 保険証の種類や役割を区別するため
- 国保組合ごとにデザインが異なるため、色もさまざま
- 運用上の管理をしやすくするため
また、保険証は更新時期や制度変更に応じてデザインが変更されることもあるようです。
緑色の保険証の正体
緑色の保険証は、一体どのような人が持っているのでしょうか。検索結果から浮かび上がってくる緑色の保険証の正体について見ていきましょう。
後期高齢者医療制度との関連
緑色の保険証は、主に後期高齢者医療制度に加入している方が持っていることが多いとされています。後期高齢者医療制度は、75歳以上の方、または65歳~75歳未満で一定の障害があり障害認定を受けた方が対象となっています。
具体例として、藤枝市では2023年8月1日から2024年7月31日までの後期高齢者医療の保険証は「緑色」になると案内されています。以前は「藤色」の保険証が使用されていたようですが、新しい期間では緑色に変更されたことがわかります。
国民健康保険の場合も
ただし、緑色の保険証は必ずしも後期高齢者医療制度だけではなく、国民健康保険においても使用されていることがあるようです。国民健康保険は各市町村によって発行されており、自治体ごとに色が異なることがあります。
したがって、緑色の保険証を持っているからといって、必ずしも後期高齢者医療制度に加入しているとは限らないのです。
“緑の保険証がやばい”と噂される理由
インターネット上では「緑の保険証がやばい」という噂が散見されるようですが、これはどのような理由から生まれたのでしょうか。
年齢や健康状態への連想
緑色の保険証が主に後期高齢者医療制度で使用されていることから、「緑色=高齢者」という連想が生まれやすいと考えられます。高齢者は医療費の負担が大きくなりやすいという一般的なイメージから、「やばい」と表現されることがあるのかもしれません。
また、検索結果では「黄色の保険証がやばい」という噂について触れられていますが、これは公務員という職業への社会的評価に関連しているようです。同様に、「緑の保険証=後期高齢者」という認識から何らかの評価や先入観が生じている可能性があります。
負担割合の違い
後期高齢者医療制度の保険証では、一部負担金の割合(1割、2割、3割)が記載されています。これは医療機関で支払う際の自己負担額に直結するため、「やばい」と表現される一因になっている可能性があります。
例えば、藤枝市の情報によると、後期高齢者医療制度では住民税の課税所得に応じて一部負担金の割合が決まり、「現役並み所得者」は3割負担、「一般2」は2割負担、「一般1」や「低所得」は1割負担となっています。
保険証の色に関する誤解と真相
保険証の色をめぐっては、さまざまな誤解が存在するようです。ここでは、そうした誤解と実際の真相について整理してみましょう。
誤解①:保険証の色で職業や年収がわかる
「保険証の色で職業や年収が分かる」という話を耳にしたことがある方もいるかもしれませんが、これは誤解であるとされています。
確かに、大企業の社員は組合健保(黄色・赤色・ピンク)に加入していることが多く、自営業やフリーランスの人は国保(緑・灰色・紫)に加入していることが多いという傾向はあるかもしれません。しかし、これはあくまで傾向であり、実際には同じ保険制度に加入していても年収は人によって異なるため、保険証の色だけで職業や年収を特定することはできないのです。
誤解②:緑色の保険証は全て後期高齢者のもの
前述の通り、緑色の保険証は主に後期高齢者医療制度で使用されることが多いですが、国民健康保険においても緑色が使用されることがあります。そのため、緑色の保険証を持っているからといって、必ずしも後期高齢者医療制度に加入しているとは限りません。
誤解③:保険証の色にランク付けがある
保険証の色によって「ランク」があるという誤解も存在するようですが、これも事実ではありません。保険証の色は発行元が独自に決めているもので、全国的な統一ルールもないため、色でランクを判断することは不可能なのです。
緑色の保険証に関する良い評判
緑色の保険証、特に後期高齢者医療制度の保険証には、実際にはさまざまな利点があるとされています。
医療費の負担軽減
後期高齢者医療制度では、所得に応じて一部負担金の割合が決められ、低所得者には負担軽減の措置が設けられています。例えば、「低所得1・2」に該当する方には「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付され、医療費の自己負担額に上限が設けられています。
自己負担額の上限設定
後期高齢者医療制度では、外来のみの場合と外来+入院の場合で自己負担限度額が設定されています。例えば、「一般1」区分(他の区分に該当しない人)の場合、外来のみだと月額18,000円(年間上限額144,000円)、外来+入院の場合は月額57,600円が上限となります。
このように、後期高齢者医療制度は高齢者の医療費負担を軽減するための様々な仕組みが整えられているのです。
マイナンバーカード移行と今後の展望
保険証は今後、マイナンバーカードへの移行が進められています。藤枝市の情報によると、令和6年(2024年)12月2日から保険証は発行されなくなるとのことです。
マイナ保険証への移行
令和6年12月2日以降は、保険証として利用登録したマイナンバーカード(マイナ保険証)を利用することになります。マイナ保険証を保有していない方には、申請なしに「資格確認書」が交付される予定です。
ただし、12月2日時点で手元にある有効な保険証は、12月2日以降も最長令和7年(2025年)7月31日まで使用可能とされています。
廃止されるものと交付されるもの
令和6年12月2日以降、廃止されるものは以下の通りです。
- 保険証
- 減額認定証
- 限度額認定証
一方、令和6年12月2日以降に随時交付されるものとしては「資格確認書」が挙げられています。
保険証の色に関する正しい理解
保険証の色は、保険者が独自に決定しているものであり、職業や年収などの個人の属性を判断するものではありません。しかし、ある程度の傾向はあるため、「青・水色は協会けんぽ」「黄色は公務員」「緑・紫は後期高齢者医療制度」といった一般的な認識が広まっているようです。
重要なのは、保険証の色だけで人を判断しないことです。保険証の色はあくまで保険者の便宜上のものであり、その人の価値や状況を示すものではありません。
まとめ
「緑色の保険証がやばい」という噂は、主に緑色の保険証が後期高齢者医療制度と関連していることから生まれた誤解である可能性が高いようです。実際には、後期高齢者医療制度の保険証は緑色が多いものの、国民健康保険でも緑色が使用されることがあり、色だけで判断することはできません。
また、保険証の色で職業や年収が分かるという誤解も存在しますが、これも事実ではないとされています。保険証の色は保険者が独自に決めているもので、全国的な統一ルールもないため、色でランクを判断することは不可能なのです。
今後は保険証自体がマイナンバーカードに統合される予定であり、令和6年12月2日以降は保険証の発行が停止されるようです。ただし、既に手元にある保険証は令和7年7月31日まで使用可能とされています。
保険証の色についての噂や評判に惑わされず、正確な情報に基づいて理解することが大切です。緑色の保険証であれ、他の色の保険証であれ、それぞれの保険制度には独自の役割と意義があります。そして何より、保険証の色で人を判断するのではなく、一人ひとりを尊重する姿勢が求められているのではないでしょうか。
健康保険制度は私たちの生活を支える重要な社会基盤の一つです。その仕組みを正しく理解し、必要な時に適切に利用できるよう、正確な情報を得ることが大切です。緑色の保険証に限らず、どの保険証も私たちの健康と生活を守るための大切なツールであることを忘れないようにしましょう。


