貯蓄型保険が”やばい”といわれているのはなぜ?
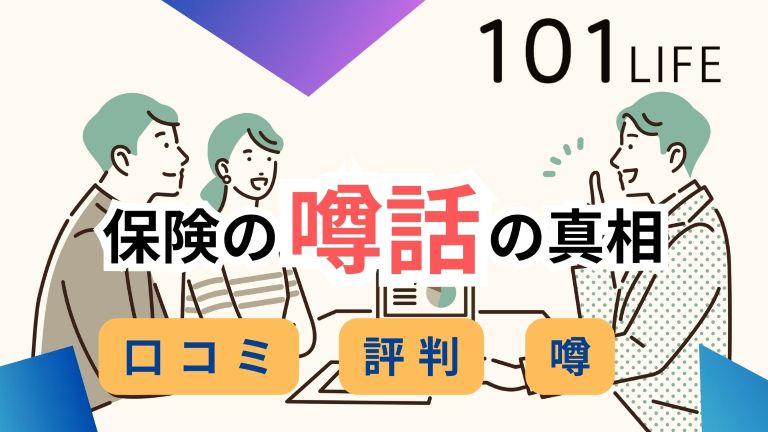
”貯蓄型保険がやばい”と口コミや評判で言われている原因と真相について解説
貯蓄型保険についてネットの口コミや評判から真相を掘り下げてみました。近年、「貯蓄型保険はやばい」という見方が広がっているようですが、一方で根強い人気を持つ金融商品でもあります。この記事では、貯蓄型保険が「やばい」と言われる理由と、その評判が誤解から生じていないかを多角的に検証し、メリットとデメリットを詳細に解説していきます。
貯蓄型保険とは何か?その基本的な仕組み
貯蓄型保険とは、万一の保障機能と貯蓄機能を兼ね備えた保険商品のことを指します。具体的には終身保険や養老保険、学資保険、個人年金保険などが貯蓄型保険に分類されるようです。
貯蓄型保険の特徴は、契約期間中に何も起こらなくても、解約時に解約返戻金を、満期を迎えた場合には満期保険金を受け取ることができる点にあります。つまり、掛け捨て型保険とは異なり、支払った保険料の一部が将来的に戻ってくる仕組みとなっているのです。
貯蓄型保険の仕組みは以下のように理解することができます。
- 保険料の一部が保障のための「掛け捨て部分」になる
- 残りの部分が将来のための「積立部分」になる
- これにより、死亡・高度障害などのリスクに備えつつ、貯蓄も同時に行える
この仕組みにより、「保障と貯蓄を一度に解決できる」という点が、貯蓄型保険の大きな特徴となっているようです。
貯蓄型保険が”やばい”と言われる5つの理由
では、なぜ貯蓄型保険が「やばい」と言われているのでしょうか。検索結果からは、主に以下の5つの理由が指摘されています。
1. 資産形成手段としての効率の悪さ
貯蓄型保険は資産形成の手段として効率が悪いと言われています。例えば、「貯蓄型保険はほとんどの商品が年利回り1%以下」と指摘されています。低金利時代においては、この数字はさらに低くなることもあるようです。
例として、15年払いで払込期間終了直後の返戻率が100.5%の保険商品の場合、年率換算すると約0.03%にしかならないという分析もあります。これは定期預金の年利よりも低いケースが多く、資産を増やす目的であれば効率的とは言えないと指摘されています。
2. 途中解約時の元本割れリスク
貯蓄型保険は、契約途中で解約すると払い込んだ保険料よりも少ない金額しか返ってこない「元本割れ」を起こすリスクがあります。
例えば、保険期間が終身、保険料払込期間20年の死亡保険に加入し、10年目に解約をすると、解約返戻金は払込保険料の累計額を下回る可能性が高いと言われています。
特に外貨建て保険や変額保険では、「保険関係費用」や「解約控除」などの手数料がかかるため、契約後に短期間で解約をすると、大きく元本割れするリスクがあるようです。
3. 資金の流動性の低さ
貯蓄型保険は、基本的に支払った保険料を自由に引き出すことができないという問題があります。
急な出費が必要になった場合、保険から一部だけ引き出すことはできず、全額解約する必要があります。その場合、先述の通り元本割れのリスクがあるため、資金計画に影響を与える可能性があるのです。
契約者貸付という制度を利用することもできますが、これには保険商品よりも高い金利(一般的に3〜8%)がかかり、返済が滞れば保険契約自体が失効する場合もあると指摘されています。
4. 商品の複雑さとわかりにくさ
貯蓄型保険、特に変額保険や外貨建て保険などは、商品の仕組みが複雑でわかりにくいという問題があります。
変額保険は、生命保険と投資信託を組み合わせたような商品で、契約者が運用リスクを負うため、運用次第で保険金や解約返戻金などが変動します。これにより、投資の知識がない方にとっては理解が難しい面があるようです。
実際に、2019年度に国民生活センターに寄せられた特定生命保険(変額保険や外貨建て保険など)に関する相談件数は321件にのぼったという報告もあります。
5. 保険料の高さと付加保険料の存在
貯蓄型保険は掛け捨て型と比較して保険料が高く設定されています。
保険料は「純保険料」と「付加保険料」に分けられ、付加保険料は会社の維持費や利益に当たる部分です。この付加保険料の分だけ、純粋な保障や貯蓄に回らない費用が発生しているのです。
「掛け捨て保険+積立」が貯蓄型の保険の実態であり、掛け捨て部分の保険料と貯蓄部分の保険料、さらに付加保険料が含まれているため、割高感は否めないとの指摘もあります。
「貯蓄型保険はやばい」という評判の誤解
一方で、貯蓄型保険の評判には誤解も含まれている可能性があります。検索結果からは以下のような点が指摘されています。
「実質保険料なし」という誤解
貯蓄型保険、特に終身保険などでは「返戻率が100%を超えるため、実質保険料なしで保障が得られる」という説明がされることがあります。
例えば、ある保険会社の終身保険では、35歳男性が60歳までに保険料を払い込む場合、払込総額が810万円程度で、60歳時の解約返戻金が約875万円になるケースがあります。これを見ると「実質的な保険料負担なし」と考えがちですが、この考え方には誤解があると指摘されています。
実際には、保険料には付加保険料(会社の維持費や利益)が含まれており、また長期間の資金拘束による機会損失も考慮する必要があるようです。
「貯金と同じ」という誤解
貯蓄型保険を「貯金の代わり」と考える人も多いようですが、これも誤解だとの指摘があります。
貯蓄型保険の仕組みは、保険会社が預かった保険料を運用し、その運用益から保険金を支払うというものです。しかし、保険会社は慎重な運用を行う必要があり、さらに付加保険料という経費もかかるため、単純な貯蓄と比べて効率が悪くなる場合が多いとされています。
貯蓄型保険の良い評判と利点
貯蓄型保険にはもちろん良い評判もあります。検索結果からは以下のような利点が挙げられています。
1. 保障と貯蓄の両立
貯蓄型保険の最大の利点は、万一の場合の保障がありながら貯蓄もできるという点です。
特に、一生涯の死亡保障を準備したい方や将来に向けた貯蓄に保険を活用したい方には、貯蓄型保険が選択肢となりうると言われています。
2. 税制上のメリット
貯蓄型保険には生命保険料控除という税制上のメリットがあります。
支払った保険料は生命保険料控除の対象となるため、節税効果も考慮すると銀行預金よりも高い利回りでお金を積み立てることができる場合もあるようです。
3. 安心感と資金の安全性
一部の貯蓄型保険商品は、元本保証で定期預金よりも高い金利を得られる場合もあります。
例えば、明治安田生命の「じぶんの積立」は、10年間の満期前に解約した場合でも返戻率100%以上をキープしており、「元本割れ」が起きないという特徴があります。これにより安心感や資金の流動性で優れていると評価されています。
4. ライフイベントに合わせた資金準備
学資保険や個人年金保険などは、特定のライフイベント(子どもの教育資金や老後資金など)に合わせて計画的に資金を準備できるという利点があります。
決まった時期に確実に資金を用意したい場合には、貯蓄型保険が選択肢となりうると言われています。
貯蓄型保険が向いている人、向いていない人
検索結果から、貯蓄型保険が向いている人と向いていない人の特徴も見えてきます。
貯蓄型保険が向いている人
- 一生涯の死亡保障を準備したい方
- 将来に向けた貯蓄に保険を活用したい方
- 保険料控除の枠が余っている方
- お金を絶対に減らしたくない方(元本保証の商品の場合)
- 計画的に特定のライフイベントに向けて資金を準備したい方
貯蓄型保険が向いていない人
- すぐにお金が必要な人(解約返戻金は早期解約だと払い込んだ保険料を大幅に下回るため)
- 保険料を抑えて大きな保障を持ちたい人(掛け捨て型の方が同じ保障額なら保険料が安い)
- 効率的に資産形成をしたい人(投資などの方が効率的な場合が多い)
- 流動性の高い資産を持ちたい人(急な出費に対応しづらい)
貯蓄型保険の代わりに検討すべき選択肢
貯蓄型保険の代わりに検討すべき選択肢としては、以下のようなものがあるようです。
1. 掛け捨て型保険と投資の組み合わせ
掛け捨て型保険で必要な保障を確保しつつ、余った資金を投資に回すという方法が提案されています。
掛け捨て型保険は貯蓄型保険よりも保険料が安いため、同じ保障額なら差額を投資に回すことで、より効率的な資産形成が可能になる可能性があるとされています。
2. NISA(少額投資非課税制度)などの活用
保険以外の金融知識が豊富なファイナンシャルプランナー(FP)は、貯蓄型保険よりもNISAなどの「保険以外」の方法を勧めることが多いようです。
NISAは一定の投資額について非課税となる制度で、長期的な資産形成に適しているとされています。
3. 預貯金や定額保険の活用
手堅く計画的にライフイベントに備えたい場合は、預貯金や定額保険などの活用も選択肢として挙げられています。
特に、景気変動に左右されにくい安定した資金確保が必要な場合には適しているとされています。
貯蓄型保険を選ぶ際のポイント
もし貯蓄型保険を検討する場合は、以下のポイントを確認することが重要だと言われています。
1. 返戻率と実質利回りの確認
貯蓄型保険を資産形成の観点から評価する場合は、単に返戻率だけでなく、年率換算した実質利回りを確認することが重要です。
例えば、返戻率100.5%でも、それが15年かけて達成される場合、年率換算すると約0.03%にしかならないことがあるため、注意が必要とされています。
2. 解約返戻金の推移を確認
貯蓄型保険は契約期間中の解約返戻金の推移が重要です。
特に、契約初期の解約返戻金は払込保険料を大きく下回ることが多いため、その推移を確認し、自分のライフプランに合っているかを検討する必要があるとされています。
3. 保険と投資の役割分担を明確に
保険は保障のため、投資は資産形成のためと役割分担を明確にすることが重要だと言われています。
保険に投資の役割を求めすぎると、どちらの目的も十分に達成できない可能性があるとの指摘もあります。
4. 自分のニーズとライフプランに合わせた選択
最終的には、自分のニーズやライフプランに合わせた選択が重要です。
手厚い保障が必要でなるべく保険料を抑えたい方やライフステージに応じた見直しをしたい方には掛け捨て保険が、一生涯の死亡保障を準備したい方や将来に向けた貯蓄に保険を活用したい方には貯蓄型保険が向いているとされています。
具体的な貯蓄型保険商品の例と評判
検索結果からは、具体的な貯蓄型保険商品の例とその評判も見られます。
明治安田生命「じぶんの積立」
「じぶんの積立」は明治安田生命が販売する積立保険で、以下のような特徴があるようです。
- 月掛保険料5,000円を一口として最大4口(20,000円)の保険料を5年間積み立て、10年間の保険期間満了後に「満期保険金」として受け取れる
- 10年間の満期前に解約した場合でも返戻率100%以上をキープしており、「元本割れ」が起きない
- 支払う保険料は生命保険料控除の対象になるため、節税効果も考慮すると銀行預金よりも高い利回りでお金を積み立てることができる
- 加入に医師の診断書や健康状態の告知は不要
この商品は「解約時のデメリットがなく、節税メリットも大きい」と評価されており、家計の貯金方法の1つとしてチェックしておきたい貯蓄型保険だとの評価もあります。
ジブラルタ生命のドル建て保険
ジブラルタ生命のドル建て保険については、批判的な見方も見られます。
- 「お金の預け先をドル建て保険に代えるだけで銀行より増える」「ただ貯金しているだけでは勿体無い」といった勧誘文句があるが、実際には保障面・貯蓄面どちらにもメリットがない可能性がある
- 保障は「かけすて」、貯蓄はNISAなど「保険以外」にするだけで、ドル建て保険より優れた無駄のない備えができるとの指摘もある
貯蓄型保険を巡る金融庁の警告
検索結果からは、金融庁が外貨建て保険などの貯蓄型保険について警告を出しているとの情報も見られます。
特に、解約返戻金が少ない、インフレに勝てない、低金利の罠など、貯蓄型保険が資産形成において不利な理由があると指摘されているようです。
まとめ:貯蓄型保険の真相
貯蓄型保険は「やばい」と言われる一方で、一定の利点も持つ金融商品です。その真相をまとめると:
- 貯蓄型保険は「掛け捨て保険+積立」の構造を持っており、純粋な貯蓄や投資と比べると効率性では劣る場合が多いと言われています。
- 資産形成を主目的とするなら、投資など他の方法の方が効率的である可能性が高いようです。
- しかし、保障と貯蓄を両立させたい場合や税制上のメリットを活用したい場合には選択肢となりうるとされています。
- 商品選びの際は、返戻率だけでなく実質利回りや解約返戻金の推移、契約内容をしっかり確認することが重要と言われています。
- 何よりも自分のニーズやライフプランに合わせた判断が最も重要だと指摘されています。
貯蓄型保険が「やばい」か否かは、一概には言えず、個人の状況や目的によって大きく異なるようです。大切なのは、貯蓄型保険の特性をよく理解した上で、自分の目的に合った金融商品を選択することではないでしょうか。
保険は保障のため、投資は資産形成のため、と役割分担を明確にしつつ、自分のライフプランに合わせた総合的な資産管理を考えることが重要だと言えるようです。
(注:この記事の情報は検索結果に基づいており、個別の状況によっては当てはまらない場合があります。実際の商品選択に際しては、専門家への相談をおすすめします。)

