保険証の黄色が”やばい”といわれているのはなぜ?
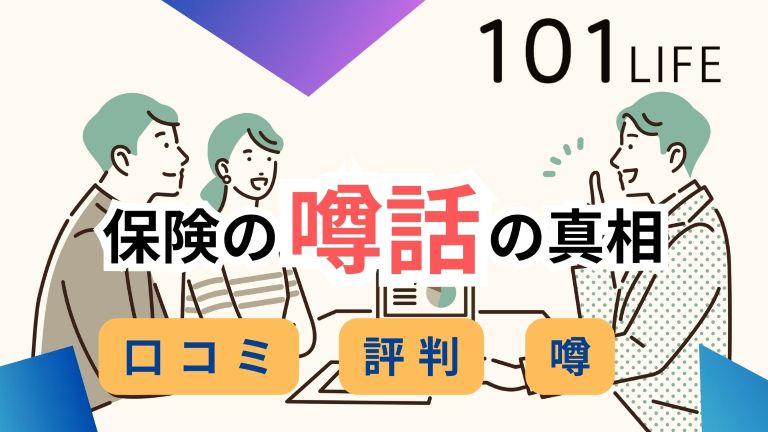
”黄色の保険証がやばい”と口コミや評判で言われている原因と真相について解説
保険証の色、特に「黄色の保険証がやばい」という噂についてネットの口コミや評判から真相を掘り下げてみました。病院や薬局で提示する機会の多い健康保険証ですが、その色にはさまざまな種類があり、時に色によって職業や年収が判断できるという誤解が広がっているようです。本記事では、保険証の色に関する噂の真偽や、黄色の保険証に対する評判、そして保険証の色が持つ本当の意味について詳しく解説していきます。
保険証の色の種類と一般的な意味
健康保険証には様々な色がありますが、これらの色は一体何を意味しているのでしょうか。まずは、保険証の色の種類と一般的にどのような意味があるとされているのかを見ていきましょう。
保険証の色の基本的な分類
保険証の色は、加入している健康保険の種類によって異なることが多いとされています。一般的には以下のような色分けがあるようです。
- 青・水色・オレンジ: 協会けんぽ(全国健康保険協会管掌健康保険)
- 赤・ピンク: 組合管掌健康保険(組合保険)
- 黄色: 共済組合(公務員)
- 灰色・緑・ピンク・赤・紫: 国民健康保険
- 紫・黄色・緑: 後期高齢者医療制度
しかし、この色分けは絶対的なものではなく、保険者によって独自に決められているため、必ずしもこの通りではないことに注意が必要です。
青・水色・オレンジの保険証
青色や水色、オレンジ色の保険証は、主に協会けんぽ(全国健康保険協会管掌健康保険)に加入している方が持っていることが多いようです。
協会けんぽは、元々は政府によって運営されていた健康保険組合でしたが、平成20年(2008年)に民営化し、現在は全国健康保険協会として運営されています。加入者は全国約207万社の中小企業で働く従業員やその家族で、保険制度適用者の約3割を占める大きな健康保険組合だと言われています。
色の変遷としては、政府により運営されていた時代はオレンジ色の保険証でしたが、平成20年の協会けんぽ設立に伴い、水色の保険証に切り替えられたようです。そのため、オレンジ色の保険証を持っている方は、より長く当該健康保険組合に加入している可能性があるとされています。
赤・ピンクの保険証
赤色やピンク色の保険証は、組合管掌健康保険(組合保険)に加入している方が持つことが多いと言われています。
組合保険は、700人以上の従業員を抱える企業、もしくは合計で3000人以上の従業員がいる複数企業が独自の健康保険組合を運営しているものです。主に大企業とそのグループ会社で働く従業員と、その家族で構成されていると言われています。
ただし、国民健康保険に加入している方の保険証も赤やピンクが多いとされており、国民健康保険は各自治体が保険証を発行しているため、色が統一されていないことに注意が必要です。
黄色の保険証
黄色の保険証は、多くの国家・地方公務員の方が持っているとされています。これは共済組合と呼ばれる、公職に就いている方が加入する保険であり、正確には保険証ではなく「組合員証」と呼ばれるものです。呼び方は異なりますが、その役割は大きく変わらないようです。
共済組合には以下のような種類があるとされています。
- 国家公務員共済組合
- 地方公務員共済組合
- 警察共済組合
- 私立学校共済組合
- 日本私立学校振興・共済事業団
他の保険証でも黄色が使われていることがありますが、多くの場合は公務員が持つ保険証(組合員証)が多いため、黄色=公務員である可能性は高いと言えるでしょう。
灰色・緑・ピンク・赤・紫の保険証
灰色や緑、ピンク、赤、紫などの保険証は、主に国民健康保険に加入している方が持っているとされています。国民健康保険は各市町村によって発行されており、自営業の方や会社を退職した方などが加入していることが多いようです。
国民健康保険は各自治体が発行しているため、地域や年によって色が異なることがあり、種類が豊富で見分けることが難しくなっていると言われています。
紫・黄色・緑の保険証
紫色や黄色、緑色の保険証は、後期高齢者医療制度に加入している方が持っていることが多いとされています。後期高齢者医療制度は、75歳以上の方、または65歳~75歳未満で一定の障害があり障害認定を受けた方が対象となっています。
黄色の保険証が”やばい”と噂される理由
インターネット上では「黄色の保険証がやばい」という噂が広がっているようですが、これはどのような理由から生まれたのでしょうか。
公務員という職業への社会的評価
黄色の保険証が「やばい」と噂される背景には、公務員という職業に対する社会的な評価や印象が関係していると考えられます。
公務員は一般的に「安定した職業」「給料が良い」「福利厚生が充実している」というイメージを持たれていることが多いようです。そのため、黄色の保険証=公務員=安定・高収入というイメージが広がり、「やばい」(良い意味で優れている)と噂されるようになった可能性があります。
しかし、実際には公務員の給与水準は職種や地域、経験年数によって大きく異なり、必ずしも民間企業よりも高いわけではないとされています。また、共済組合に加入している公務員でも、黄色以外の色の保険証を持っている場合もあるようです。
保険証の色と職業の関連性
保険証の色と職業には一定の関連性があると言われていますが、それは絶対的なものではありません。例えば、黄色の保険証を持っていても公務員とは限らず、自治体の国民健康保険でも黄色を採用しているケースがあるようです。
健康保険の種類が異なっても色が同じなケースもあることから、職業も特定できない可能性があると言われています。そのため、保険証の色だけで職業を特定することはできず、黄色の保険証=公務員というのは必ずしも正確ではないようです。
色によるマウントの可能性
保険証の色によって「マウントを取られた経験がある」という意見もあるようです。これは、保険証の色によって加入者の職業や収入レベルが判断できると誤解されていることから生じている可能性があります。
しかし、先述の通り、保険証の色だけでは年収や職業のランクを判断することはできないとされています。保険証の色は保険者が独自に決定しているものであり、法律的・制度的な意味はないと言われています。
保険証の色に関する誤解
保険証の色に関しては、多くの誤解が広がっているようです。ここでは、よくある誤解について検証してみましょう。
誤解1: 保険証の色で年収がわかる
「保険証の色で年収がわかる」という噂がありますが、これは誤りとされています。色だけで年収や職業を特定することはできないと言われています。
同じ健康保険に加入していても、年収の高い、低いは分からないとされています。例えば、同じ黄色の保険証を持つ公務員でも、新人からベテラン、一般職から管理職まで様々な立場の人がいるため、年収には大きな差があると考えられます。
誤解2: 保険証の色で企業のランクがわかる
「保険証の色で企業のランクがわかる」という噂もありますが、これも誤りとされています。保険証の色だけでは、加入者の勤務先企業のランクを判断することはできないようです。
保険証の色は保険者が独自に決定しているものであり、特に企業のランクを示すように設計されているわけではないとされています。例えば、同じ組合管掌健康保険に加入していても、企業の規模や業績は様々であるため、保険証の色からそれを判断することはできないと考えられます。
誤解3: 保険証が水色だと底辺
「保険証が水色だと底辺」という噂もありますが、これも誤りとされています。水色の保険証は協会けんぽに加入している人が持つことが多く、協会けんぽは日本で最も加入者の多い健康保険組合の一つとされています。
「保険証が水色だと底辺なの?」という質問に対して、「保険証の色でその人の年収や職業がバレるのでは?と思っている人もいますが、保険証が水色でもやばいことは一切ありません。職業や年収は保険証の色で判断することはできません」と回答されています。
保険証から読み取れる情報と読み取れない情報
保険証からはどのような情報が読み取れ、どのような情報が読み取れないのでしょうか。
保険証から読み取れる情報
保険証からは、主に以下のような情報が読み取れるとされています。
- 保険者の種類: 保険証の表面に記載されている「保険者」の欄から、加入している健康保険の種類(協会けんぽ、組合健保、共済組合、国民健康保険など)を知ることができます。
- 被保険者番号: 保険証に記載されている「被保険者番号」からは、その人の会社での地位が判断できる場合があると言われています。
- 保険者番号: 保険証に記載されている「保険者番号」からは、保険者のおおよその種類がわかるとされています。
保険証から読み取れない情報
一方、保険証からは以下のような情報は読み取れないとされています。
- 年収: 保険証の色や記載内容からは、その人の年収を特定することはできないとされています。
- 職業のランク: 保険証からは、その人の職業のランクや社会的地位を判断することはできないとされています。
- 企業のランク: 保険証からは、その人の勤務先企業のランクや規模を判断することはできないとされています。
今後の保険証の取り扱い
現在、健康保険証は大きな変革期にあるようです。今後の保険証の取り扱いについて見ていきましょう。
マイナンバーカードへの移行
2023年秋以降、健康保険証は新規発行されなくなり、代わりにマイナンバーカードを「マイナ保険証」として利用することになると言われています。
健康保険証の発行終了以降は、その時点で持っている健康保険証の有効期限(最長令和7年12月1日)まで使用可能とされています。もし、保険証の色で職業や年収が推測されるのではと不安に思う方は、早めにマイナンバーカードへ切り替えるといいのではないかと提案されています。
マイナンバーカードは見た目が同じなので、使用時に加入している健康保険が周囲へ知られる可能性は低いとされています。利用方法は、マイナンバーカードを所持していれば、医療機関の利用時に専用の機械に読み込ませて登録するだけとのことです。
マイナンバーカードがない場合の対応
マイナンバーカードを持っていない場合の健康保険の利用方法については、資格確認システムに対応した医療機関では「資格確認書」や「健康保険証利用登録済証」などの書類を受付で提示することで、これまでと同様に保険適用で受診することができると言われています。
保険証の色に関する正しい理解
保険証の色についての正しい理解を持つことは、不必要な誤解や偏見を避けるために重要です。以下では、保険証の色に関する正しい理解について解説します。
保険証の色は保険者が独自に決定している
保険証の色は、保険者が独自に決定しているとされています。全国で統一された基準がないため、各保険者が独自に色を決めていると言われています。
色を変えている理由としては、以下のようなものが挙げられています。
- 種類によって色を変えている
- 更新手続きをわかりやすくするために色を変えている
保険証の色には法律的・制度的な意味はない
保険証の色自体には、法律的・制度的な意味はないとされています。色が異なっている背景としては、発行元や加入する保険の種類を判別しやすくする目的があると考えられていますが、色によって医療費の負担や制度が変わるわけではないとされています。
保険証の色が変わる理由
保険証の色は、以下のような理由で変わることがあるとされています。
- 世帯主の勤務先が変わった場合: 自分の世帯主の勤務先が変わることで、家族全員の保険証の色が、それまでと全く違う色に変わることはごく普通にあることだとされています。
- 転居や年齢などの要因: 転居で市区町村が変わる場合や、高年齢になり「後期高齢者医療保険」へと移行する場合にも、保険証の色が変わることがあると言われています。
- 保険を切り替えた場合: 何かの理由で保険を切り替えた場合にも、保険証の色が変わることがあるとされています。
まとめ:黄色の保険証が”やばい”という噂の真相
黄色の保険証が「やばい」と噂される理由について詳しく調査してきましたが、その真相はどうなのでしょうか。
結論から言うと、黄色の保険証が特別に「やばい」(優れている、または問題がある)ということはないようです。黄色の保険証は主に公務員が加入する共済組合で発行されることが多いとされていますが、それ以外の健康保険組合でも黄色の保険証が発行されることがあるようです。
また、保険証の色だけでは、その持ち主の年収や職業、社会的地位を判断することはできないとされています。保険証の色は保険者が独自に決定しているものであり、特別な意味を持つわけではないと言われています。
最終的には、保険証の色に対する噂や偏見は誤解から生まれたものであり、保険証の色で人を判断することは適切ではないと言えるでしょう。
今後は、健康保険証からマイナンバーカードへの移行が進み、保険証の色による区別もなくなっていくとされています。マイナンバーカードは見た目が同じなので、使用時に加入している健康保険が周囲へ知られる可能性は低くなるとされています。
健康保険制度は私たちの生活を支える重要な社会保障制度の一つです。保険証の色で人を判断するのではなく、健康保険制度そのものの理解を深め、適切に活用していくことが大切ではないでしょうか。
健康保険証の色に関する誤解や偏見がなくなり、すべての人が安心して医療サービスを受けられる社会になることを願っています。

