”ソフトバンクグループの株価がやばい”と話題に – 2025年4月7日
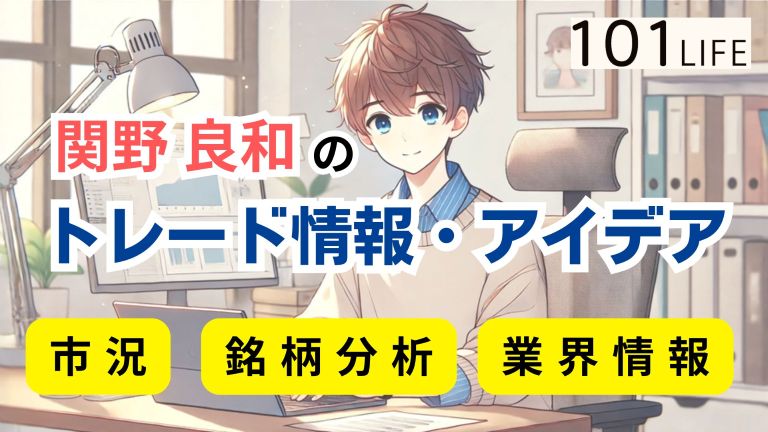
ソフトバンクグループの株価が「やばい」と言われる背景を徹底調査
ソフトバンクグループ(9984)の株価下落についてネットの口コミや評判から真相を掘り下げてみました。2025年4月7日現在、市場全体の急落とともにソフトバンクグループの株価にも注目が集まっています。実際のところ、この株価動向にはどのような背景があるのでしょうか。
最近の株価動向と市場環境
2025年4月7日の東京株式市場では、日経平均株価が前営業日比2644円00銭安の3万1136円58銭と大幅に3日続落しました。この全体的な下落相場の中で、ソフトバンクグループの下げも目立っているようです。
実際に4月4日時点では、ソフトバンクグループの株価は6700円台まで下落しており、これは東京市場が暴落した昨年8月5日以来の低水準だったと報告されています。さらに遡ると、3月11日には一時、前日比408円(5.05%)安の7659円まで下落し、2024年9月9日以来半年ぶりの安値を付けていたことがわかります。
このような状況から、SNSや投資掲示板などでは「ソフトバンクグループの株価がやばい」という声が広がっているようです。
株価下落の主な要因
この株価下落には、いくつかの要因が絡んでいると考えられます。
1. 米国ハイテク株との連動性
ソフトバンクグループは米国ハイテク株との連動性が高いため、米国市場の悪化が直接的に影響していると言われています。特に、米国のナスダック指数が前日比で約6%急落した影響を大きく受けたとの分析もあります。
2. 投資ファンド事業への懸念
ソフトバンクグループが運営する投資ファンド事業の業績に対する逆風が強まっているとの懸念から売り圧力が高まっているようです。世界的なテクノロジー株の調整局面では、同社の投資ポートフォリオへの不安が広がりやすい傾向にあります。
3. 個人投資家の動向
信用買いを入れていた個人投資家の持ち高解消の動きも下げに拍車をかけているとの見方があります。相場の急変時には、このような投資家心理の変化が株価に大きく影響することがあるようです。
4. トランプ関税リスク
市場全体としては、トランプ関税リスクへの警戒感も影響しているようで、7日の東京市場では99%の銘柄が下落するという極めて厳しい状況となりました。
ソフトバンクグループの構造的な課題
株価が長期的に伸び悩む背景には、同社の財務構造に関する懸念点も指摘されています。
自己資本比率の低さ
ソフトバンクグループの自己資本比率は15.3%(2024年3月期)と、同業他社と比較して著しく低い水準にあります。同じ通信大手であるNTT(33.3%)やKDDI(37.1%)と比べると半分以下であり、この点がソフトバンクグループ株式のデメリットとして挙げられることが多いようです。
自己資本比率が低いということは、借入金への依存度が高いことを意味し、金利変動リスクや財務健全性への懸念から「投資をやめとけ」というアドバイスをする投資家も少なくないようです。
アナリストの見方と目標株価
一方で、市場のプロフェッショナルであるアナリストたちの評価は興味深い対照を示しています。
株式市場のアナリストコンセンサスでは、2025年4月3日時点で「買い」という判断が示されています。その内訳は、強気買い9人、買い2人、中立4人となっており、多くのアナリストがまだソフトバンクグループ株に対して前向きな見方をしているようです。
平均目標株価は11,384円で、4月4日の株価(6,656円)からは約58.71%の上昇余地があるとの予想となっています。ただし、最近1週間で目標株価は11,860円から11,384円へと下方修正されており、見通しがやや慎重になっていることもうかがえます。
投資家の口コミや評判
ネット上の掲示板やSNSでは、ソフトバンクグループの株価に関して様々な意見が交わされています。
「配当金目当てで買った人たちには厳しい状況ですね。もう少し下がるかも」という懸念の声がある一方で、「ここまで踏ん張ったとも言えるけど、期待外れという声も多いです」という評価も見られます。
また、「長期的にはまだ魅力的だと思うけど、今は買い増しを控えたほうがいいかも」という慎重な意見も多く、短期的な値動きに対する不安感が支配的なようです。
こうした声からは、ソフトバンクグループ株式は短期的には厳しい状況にあるものの、長期投資先としての可能性はまだ残されているという見方が読み取れます。
ソフトバンクグループの利点と課題
おすすめできる点
ソフトバンクグループの投資先としての利点は、以下のような点にあるとされています。
- 安定した配当金政策
- 「Beyond Carrier」戦略による新分野への挑戦
- AIやテクノロジー分野への積極投資による将来的な成長性
懸念される欠点
一方で、投資する際に考慮すべき欠点としては:
- 自己資本比率の低さ(15.3%)
- 高い借入金依存度による財務リスク
- 米国ハイテク株との連動性による変動リスクの高さ
これらの点が、「ソフトバンクグループ株はやめたほうがいい」という意見の根拠となっているようです。
社債投資の選択肢
株価が不安定な状況下では、同社が発行する社債も投資家の関心を集めています。ソフトバンクグループの個人向け社債は、他社の社債と比較して相対的に高利回りであるため、発行から数時間で売り切れる人気銘柄として知られています。
しかし、社債についても「ソフトバンク社債への投資は危険」という声もあり、株式同様に投資判断には慎重さが求められているようです。
結論
2025年4月7日現在のソフトバンクグループの株価下落は、主に米国市場の影響や全体的な市場環境の悪化によるものと考えられます。アナリストはまだ長期的には前向きな見方をしていますが、自己資本比率の低さなど構造的な課題も無視できません。
投資判断を行う際には、自身のリスク許容度や投資目的を明確にし、市場動向を注視することが重要と言われています。短期的にはリスクが高まっている状況ですので、新規投資や買い増しを検討する場合には、慎重な姿勢が求められるでしょう。
ただし、長期的な視点では成長性や配当政策を評価する声も多く、一概に「おすすめしない」とは言えない状況です。投資家それぞれの投資戦略や目的に合わせた判断が必要なようです。

