「DOE(ディーオーイー)」って何? できるだけわかりやすく解説
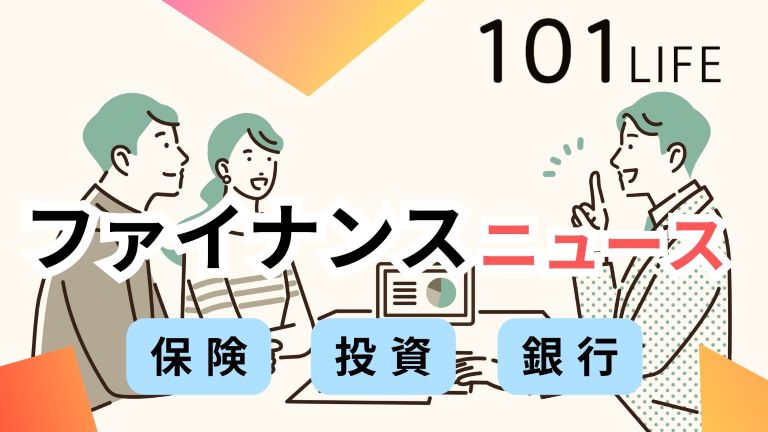
株主資本配当率(DOE)とは?計算方法と意味や投資判断に活用する方法について具体的に解説します
近年、日本企業の株主還元への姿勢が変化し、株主重視の経営が進む中で注目を集めている指標が「DOE(Dividend on Equity ratio)」、日本語では「株主資本配当率」です。東証が「資本コストや株価を意識した経営」を上場企業に要請してから約2年が経過し、従来の配当性向に代わる新たな株主還元指標としてDOEを採用する企業が急速に増えています。2025年4月には大手物流企業のニッコンホールディングスがDOE4%以上を目安とする方針を発表するなど、直近でも多くの企業がDOEを重視した株主還元策を打ち出しています。DOEは企業が株主資本に対してどれだけ配当を支払っているかを示す指標であり、企業の株主還元に対する姿勢を評価する上で重要な尺度となっています。投資判断において配当の安定性や企業の株主還元への積極性を見極める際に、DOEは非常に有用な指標と言えるでしょう。
この記事でわかること
- DOEとは何か、その計算方法と意味について理解できる(株主資本に対する配当金の割合を示す重要指標)
- 従来の配当性向とDOEの違いと、なぜ企業がDOEを採用するようになったのかがわかる(安定性と株主還元姿勢の明確化)
- 業種別のDOE平均値や、投資判断に活用する方法について学べる(業界ごとの基準値と投資戦略への応用)
- 最新の企業事例から、DOEを活用した株主還元戦略のトレンドを把握できる(具体的な企業の取り組み例)
DOEの基本概念と計算方法
DOE(Dividend on Equity ratio)は、株主資本配当率と呼ばれ、企業が株主資本に対してどれだけの配当を支払っているかを示す財務指標です。計算式は非常にシンプルで、「DOE(%) = 配当金支払額 ÷ 株主資本」です。
例えば、ある企業の年間配当金支払額が100億円、株主資本が2,000億円の場合、DOEは5%(100億円÷2,000億円×100)となります。この5%という数値は、株主が投下した資本に対して毎年5%の利回りで配当を受け取っていることを意味します。
もう一つの計算方法として、「DOE = 配当性向 × ROE(自己資本利益率)」という式もあります。これは、当期純利益に対する配当の割合(配当性向)と、株主資本に対する当期純利益の割合(ROE)の掛け算で表されます。つまり、DOEは企業の収益性(ROE)と株主還元の積極性(配当性向)の両方を反映した指標と言えるのです。
株主資本とは具体的に何を指すのかも理解しておきましょう。株主資本は、貸借対照表の「純資産の部」のうち、株主が出資した「資本金」に加え、「資本剰余金」「資本準備金」「利益剰余金」「利益準備金」などで構成されます。これは企業が株主から調達した資金や、事業活動で得た利益のうち社内に留保している部分の合計であり、返済義務のない企業の自己資金です。
【用語解説】資本剰余金と利益剰余金 資本剰余金とは、株主から払い込まれた資金のうち資本金に組み入れられなかった部分や、自社株式の売却益などから構成されます。一方、利益剰余金は企業活動によって生み出された利益のうち、配当などで社外に流出せず、社内に蓄積された部分を指します。これらの合計が株主資本の大部分を占めており、DOEの計算では分母となる重要な要素です。
DOEと配当性向の違い
従来、企業の配当方針を表す指標としては「配当性向」が一般的でした。配当性向は「配当金支払額 ÷ 当期純利益」で計算され、企業が稼いだ利益のうちどれだけを株主に還元するかを示す指標です。
しかし、配当性向には大きな欠点があります。当期純利益は企業業績や一時的な特別損益などによって年度ごとに大きく変動することがあります。例えば、ある年に業績が好調で当期純利益が倍になれば、同じ配当性向を維持するために配当も倍増する必要があります。逆に、業績が悪化して当期純利益が半減すれば、配当も半減することになります。
これに対してDOEは、比較的安定している株主資本を基準にしているため、短期的な業績変動に左右されにくいという特徴があります。株主資本は積み上げられてきた内部留保などを含むため、急激に変動することは少なく、DOEを指標とすることで安定した配当政策を実行しやすくなります。
例えば、ある企業が「配当性向30%」を掲げている場合、当期純利益が100億円なら配当総額は30億円、利益が200億円に増えれば配当も60億円に増える計算です。一方、同じ企業が「DOE3%」を掲げている場合、株主資本が1,000億円であれば、業績に関わらず配当総額は30億円となります。
積水化学工業では、「DOE3%以上」を株主還元方針に掲げており、2023年度には4.2%を達成しています。このように、DOEを採用することで、投資家は企業の配当方針の安定性や一貫性を評価しやすくなるのです。
【用語解説】配当性向 配当性向とは、企業が稼いだ当期純利益のうち、どれだけの割合を配当として株主に還元するかを示す指標です。「配当性向(%) = 配当金総額 ÷ 当期純利益 × 100」で計算されます。例えば配当性向が40%の企業は、利益の40%を株主に配当として分配し、残りの60%を社内に留保していることになります。日本企業の平均的な配当性向は約30%程度とされています。
DOEの目安と業種別の平均値
DOEの水準を評価する際、どの程度の数値が「良い」とされるのでしょうか。2023年時点での全業種の中央値(目安)は約2.2%とされています。しかし、業種によって適正水準は大きく異なります。
業種別の平均値(2023年)を見ると、サービス業が4.0%、情報・通信業が3.8%と高い水準にある一方、鉄鋼業は2.0%、繊維製品は1.7%と低めの水準にあります。これは業種ごとの投資需要や成長性の違いを反映しています。例えば、設備投資が多く必要な製造業では、内部留保を厚くする必要があるため、DOEは低めになる傾向があります。
特に高いDOEを誇る企業の例としては、アパレルのネット通販サイト「ZOZOTOWN」を運営するZOZOが挙げられます。ZOZOは過去3期の平均DOEが31.2%に達し、日本企業の中でトップクラスの高水準を維持しています。これは同社が高いROE(自己資本利益率)を実現し、効率的に利益を生み出していることの表れでもあります。
DOEの水準を評価する際には、単に数値の高低だけでなく、以下の点も考慮する必要があります。
- 同業種内での相対的な位置づけ
- 企業の成長段階(成長企業は再投資のためDOEが低めになることもある)
- 過去からのDOEの推移傾向
- 企業が公表している目標DOE値との比較
株式会社ユニリタのように「DOE4.5%」(2024年3月期)を達成している企業は、業界平均を上回る株主還元を行っていると評価できるでしょう。
【用語解説】ROE(自己資本利益率) ROE(Return On Equity)は、株主資本に対してどれだけの当期純利益を生み出したかを示す指標です。「ROE(%) = 当期純利益 ÷ 株主資本 × 100」で計算されます。ROEが高いほど、株主から預かった資本を効率的に使って利益を生み出していることになります。日本企業の平均的なROEは8%前後とされていますが、米国企業は平均で15%程度と言われており、日本企業の資本効率の改善が課題となっています。
最近の企業動向:DOE採用の広がり
近年、日本企業の間でDOEを株主還元指標として採用する動きが加速しています。これは2023年に東京証券取引所(東証)が上場企業に対して「資本コストや株価を意識した経営」を要請したことが大きなきっかけとなっています。
2025年4月4日には、ニッコンホールディングスが株主還元方針の新たな指標としてDOEを導入することを発表しました。同社はDOE4%以上をメドとし、2026年3月期から適用する方針です。また、2029年3月期までの4年間で約400億円の自社株買いを実施することも明らかにしており、積極的な株主還元姿勢を示しています。
キリンホールディングスも、「配当性向よりも安定的かつ持続的な配当を実施」するという理由から、2025年12月期からDOE5%以上を目安とした配当方針を掲げています。
大林組は中期経営計画2022において「自己資本配当率(DOE)5%程度」を目安とした普通配当を行う方針としています。同社は「自己資本配当率(DOE)の目安は、利益水準の中長期的な改善傾向に合わせて見直していきます」と述べており、継続的な株主還元の強化を目指しています。
企業がDOEを採用する主な理由としては、以下の点が挙げられます。
- 安定配当の実現:業績変動に左右されにくい配当政策の実現
- 株主還元姿勢の明確化:資本効率を意識した経営姿勢のアピール
- 投資家からの評価向上:特に海外の機関投資家はDOEを重視する傾向がある
- 資本効率の改善:適正な自己資本水準の維持と余剰資金の有効活用
株主還元策としては、配当だけでなく自社株買いもDOEを高める方法として活用されています。自社株買いは株主資本を減少させる効果があるため、結果的にDOEを引き上げることになります。このように、DOEは企業の資本政策全体を考える上での重要な指標となっているのです。
【用語解説】自社株買い 自社株買いとは、企業が市場で自社の株式を買い戻すことです。自社株買いには、株価の下支え効果、1株当たりの価値の向上(EPS増加)、株主還元の強化などの目的があります。自社株買いによって自己株式が増加すると、実質的に発行済株式数が減少し、1株当たりの株主価値が高まります。また、買い戻した株式を消却することで、株主資本が減少し、DOEを高める効果もあります。
DOEに基づく投資戦略
投資家にとって、DOEは企業の株主還元姿勢を評価する上で重要な指標となります。DOEを活用した投資戦略にはどのようなものがあるのでしょうか。
日本アジア証券グループの分析によると、「DOEが4%以上」の企業に投資する戦略は、長期的に見て有効性が高いことが示されています。また、「DOEが4%以上で配当利回りが3%以上」という2つの条件を組み合わせた戦略は、さらに安定したパフォーマンスを示す傾向があるとされています。
配当利回りとDOEの関係は以下の式で表されます。 配当利回り = DOE ÷ PBR(株価純資産倍率)
この式からわかるように、同じDOEでも、PBRが低い(割安な)企業ほど配当利回りは高くなります。つまり、DOEと配当利回りの両方が高い企業は、株主還元に積極的で、かつ株価が割安である可能性が高いということです。
実際の投資戦略としては、以下のようなアプローチが考えられます。
- 高DOE企業への長期投資:DOEが業界平均を上回る企業に長期投資する
- DOEと配当利回りのダブルスクリーニング:両方の指標が高い企業を選別する
- DOEの上昇トレンドに注目:DOEが継続的に上昇している企業を選ぶ
- DOE目標を新たに導入した企業への投資:株主還元強化の意図を持つ企業に着目する
ただし、DOEだけで投資判断を行うのではなく、企業の成長性や財務健全性なども総合的に評価することが重要です。高DOEを維持するために過剰な借入を行っている企業や、必要な成長投資を怠っている企業には注意が必要です。
また、DOEは成長性よりも安定性を重視する指標であるため、短期的な値上がり益を狙うよりも、長期的な安定配当を重視する投資家に適した指標と言えるでしょう。
【用語解説】PBR(株価純資産倍率) PBR(Price Book-value Ratio)は、株価が企業の1株当たり純資産(=株主資本)の何倍であるかを示す指標です。「PBR = 株価 ÷ 1株当たり純資産」で計算されます。PBRが1倍を下回る場合は、株価が会計上の解散価値を下回っていることを意味し、割安と判断される場合があります。一方、成長性の高い企業では、将来の期待を織り込んでPBRが高くなる傾向があります。
DOEを開示する決算情報の探し方
投資家がDOEの情報を入手するには、どうすれば良いのでしょうか。DOEは企業の決算短信に掲載されています。
決算短信は、企業が四半期や通期の決算発表時に公表する最も速報性の高い財務情報です。東京証券取引所の定めるフォーマットに沿って作成され、サマリー情報と添付資料から構成されています。
DOEの情報は、決算短信のサマリー情報部分に記載されています。具体的には「配当の状況」という項目で、「純資産配当率(連結)」または「株主資本配当率(連結)」として表示されています。IFRS(国際財務報告基準)を採用している企業の場合は、「親会社所有者帰属持分配当率(連結)」という項目名で記載されることもあります。
例えば、ZOZOの2024年3月期決算短信では、「純資産配当率(連結)」という項目でDOEが開示されており、20%以上の高いDOEを維持していることがわかります。
決算短信は各企業のIRウェブサイトや、東京証券取引所のウェブサイト(TDnet)で公開されています。また、各種金融情報サービスやアプリでも、DOEを含む財務指標を簡単に確認することができます。
なお、決算短信は決算日から45日以内(望ましくは30日以内)に公表することが求められており、企業の最新の財務状況を知る上で重要な情報源となっています。
【用語解説】決算短信 決算短信は、上場企業が決算内容を開示するために作成する書類です。東京証券取引所の規則に基づき、決算が確定したら「直ちに」公表することが義務付けられています。サマリー情報(業績ハイライト、配当状況、業績予想など)と添付資料(経営成績・財政状態の概況、財務諸表など)で構成されます。投資判断に重要な影響を与える情報として、投資家に広く活用されています。
DOEを高める企業戦略
企業がDOEを高めるには、具体的にどのような戦略があるのでしょうか。主に以下の2つのアプローチがあります。
1. 分子(配当金支払額)を増やす方法
最も直接的な方法は、配当金を増やすことです。企業が増配を行えば、DOEは上昇します。例えば、積水化学工業は株主還元方針として「DOE3%以上」を掲げており、2023年度には配当を増やしてDOE4.2%を達成しています。
配当を増やすための原資を確保するには、企業の収益力向上が必要です。そのため、事業の選択と集中、高付加価値事業への投資、コスト削減などの経営改善策が重要となります。
また、企業によっては特別配当を実施することで、一時的にDOEを高めるケースもあります。ユニリタでは2020年3月期に普通配当に加えて特別配当2円を実施し、DOEを4.4%まで高めました。
2. 分母(株主資本)を減らす方法
もう一つの方法は、株主資本を圧縮することです。その代表的な手段が自社株買いです。企業が市場から自社株式を買い戻すことで、株主資本は減少し、結果的にDOEは上昇します。
例えば、ニッコンホールディングスは2025年4月4日に、2029年3月期までの4年間で約400億円の自社株買いを実施する方針を発表しています。自社株買いの資金源として、同社は「政策保有株式や不動産などの資産売却」を検討していると説明しています。
また、買い戻した自社株式を消却することで、より直接的に株主資本を減少させる効果があります。積水化学工業は2023年度に800万株の自己株式を消却しており、こうした取り組みもDOE向上に寄与しています。
ただし、DOEを高めるために過度に株主資本を減らすことは、企業の財務基盤を弱める恐れがあります。そのため、企業は成長投資と株主還元のバランスを考慮しながら、適切な資本政策を実行する必要があります。
【用語解説】政策保有株式 政策保有株式とは、純投資目的ではなく、取引関係の維持・強化などを目的として企業が保有する他社の株式のことです。日本企業の多くは従来、取引先や関連会社の株式を持ち合う形で政策保有株式を多く保有していましたが、近年はコーポレートガバナンス改革の流れを受けて、政策保有株式の縮減が進められています。政策保有株式を売却することで得た資金を株主還元に充てる企業も増えています。
日米企業のDOE比較と日本企業の課題
日本企業と米国企業のDOEを比較すると、興味深い違いが見えてきます。日本の主要企業(TOPIX構成企業)のDOE平均値は約3%程度であるのに対し、米国の主要企業(S&P 500構成企業)は約6%と、約2倍の開きがあります。
この差が生じる背景には、日米の企業文化や資本政策の違いがあります。興味深いことに、配当性向(当期純利益に対する配当の割合)では日米とも約30%と同水準です。それにもかかわらずDOEに大きな差があるのは、以下の2つの要因が考えられます。
- 内部留保の差:日本企業は米国企業に比べて内部留保が多い傾向にあります。つまり、株主資本(分母)が相対的に大きくなり、DOEが低くなりやすい構造があります。
- 自社株買いの差:米国企業は積極的に自社株買いを行い、株主資本を圧縮する傾向が強いのに対し、日本企業は自社株買いの規模が小さい傾向にあります。
日本企業の課題としては、過剰な内部留保の有効活用と資本効率の向上が挙げられます。東証の市場改革により、企業には資本コストを意識した経営が求められるようになっています。その結果、多くの企業がDOEを重視した株主還元策を打ち出しはじめていますが、まだ米国企業の水準には及びません。
今後、日本企業には以下のような取り組みが期待されます。
- ROE向上を通じたDOEの改善
- 適切な水準での自己資本の維持と余剰資金の株主還元
- 成長投資と株主還元のバランスの取れた資本戦略
これらの取り組みが進むことで、日本企業の株式市場における評価の向上につながると期待されています。
【用語解説】内部留保 内部留保とは、企業が獲得した利益のうち、配当などで社外に流出せずに社内に蓄積された資金のことです。主に利益剰余金として貸借対照表に計上されます。内部留保は企業の安定性を高め、将来の投資や不測の事態に備える役割がありますが、過剰な内部留保は資本効率を低下させ、DOEを引き下げる要因ともなります。近年は「眠った内部留保」の活用が課題とされ、成長投資や株主還元への振り向けが求められています。
DOEを活用する際の注意点
DOEは有用な指標ですが、投資判断に利用する際には以下の点に注意する必要があります。
成長段階による違い
成長初期の企業や積極的に事業拡大を図っている企業では、利益を内部留保して再投資に充てる傾向があります。そのため、DOEが低くても必ずしも株主軽視ではなく、長期的な企業価値向上を図る戦略である可能性があります。
例えば、成長企業であるAmazonは長年無配当政策を維持し、すべての利益を事業拡大に投資してきました。このような企業はDOEが低いものの、株価上昇による株主価値の向上を実現しています。
業種特性の考慮
前述のように、DOEの適正水準は業種によって大きく異なります。製造業のように設備投資が多く必要な業種では、内部留保を厚くする必要があるため、DOEは低めとなる傾向があります。一方、サービス業や情報・通信業のように設備投資が少ない業種では、DOEが高い傾向にあります。
投資判断を行う際には、単純にDOEの高低だけで評価するのではなく、同業他社との比較や業界平均値との比較が重要です。
財務健全性とのバランス
DOEを高めるために過度な配当や自社株買いを行うと、企業の財務基盤が弱体化する恐れがあります。特に、借入金を増やして配当を行うケースでは、将来的な財務リスクが高まる可能性があります。
投資家としては、DOEだけでなく、自己資本比率や負債比率などの財務健全性指標も併せて確認することが重要です。例えば、積水化学工業は「D/Eレシオ0.5以下の場合には総還元性向50%以上を確保」としており、財務健全性を考慮した株主還元方針を明示しています。
短期的な投資には不向き
DOEは長期的な視点での投資判断に適した指標であり、短期的な株価上昇を狙う投資スタイルには不向きかもしれません。DOEが高い企業への投資は、「安定的な配当収入を得ながら長期保有する」という投資スタイルと相性が良いと言えるでしょう。
【用語解説】D/Eレシオ D/Eレシオ(Debt Equity Ratio)は、負債と株主資本の比率を示す財務指標です。「D/Eレシオ = 有利子負債 ÷ 株主資本」で計算されます。この値が低いほど財務的に安全と判断され、一般的に1.0(100%)以下が望ましいとされています。D/Eレシオが高い企業は、借入依存度が高く財務リスクが大きいと評価される傾向にあります。株主還元策を検討する際に、D/Eレシオは財務健全性を判断する重要な指標となります。
まとめ:投資判断にDOEを活かす方法
DOEは、企業の株主還元姿勢を評価する上で非常に有用な指標です。従来の配当性向と比較して業績変動に左右されにくく、安定した株主還元政策を表すことができるという特徴があります。
東証の市場改革をきっかけに、多くの日本企業がDOEを採用するようになっており、今後もこの傾向は続くと予想されます。ニッコンホールディングスやキリンホールディングスなど、最近もDOEを導入する企業が増えています。
投資判断にDOEを活かす際のポイントをまとめます。
- 業種特性を考慮する:業種ごとの平均DOEを把握し、相対的な評価を行いましょう。サービス業や情報・通信業は高め(4%前後)、製造業は低め(2%前後)という傾向があります。
- 他の指標と組み合わせる:DOEだけでなく、配当利回りやPBR、ROEなどの指標も併せて分析することで、より総合的な投資判断が可能になります。特に「DOEが高く、配当利回りも高い」銘柄は要注目です。
- 中長期的な視点で評価する:DOEは短期的な株価変動よりも、中長期的な株主還元の安定性を示す指標です。インカムゲイン(配当収入)を重視する長期投資家に適した指標と言えるでしょう。
- DOEの変化に注目する:DOEの絶対値だけでなく、過去からの変化傾向も重要です。DOEが上昇傾向にある企業は、株主還元を強化している可能性があります。
- 企業の成長段階を考慮する:成長企業はDOEが低くても、将来的な成長のための投資を優先している可能性があります。企業のライフステージに応じた評価が必要です。
株式投資では、企業の成長性、収益性、安定性など様々な側面からの分析が重要です。DOEはその中でも特に「株主還元の安定性」を評価する指標として活用できます。日本企業のコーポレートガバナンス改革が進む中、DOEの重要性は今後さらに高まると考えられます。
最後に、日本企業のDOEは米国企業と比較するとまだ低い水準にありますが、株主還元の強化を図る企業が増えていることは、日本の株式市場にとって前向きな変化と言えるでしょう。投資家としては、こうした変化を的確に捉え、投資判断に活かしていくことが重要です。

