「FVTPL」って何? できるだけわかりやすく解説
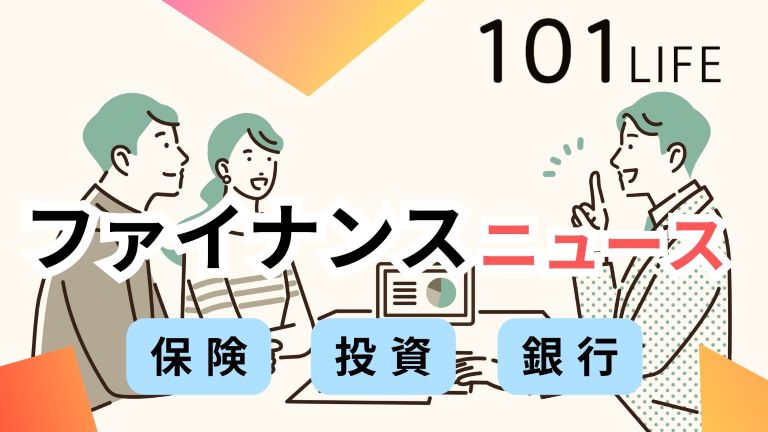
FVTPLとは?基本的な意味など金融商品会計の重要な概念をわかりやすく解説
企業の財務諸表を読み解く上で避けて通れないのが、国際財務報告基準(IFRS)における金融商品の分類方法です。特に「FVTPL(エフブイティーピーエル)」という略語は、投資家から経理担当者まで幅広いビジネスパーソンにとって重要な概念となっています。この「Fair Value Through Profit or Loss(純損益を通じた公正価値)」という会計処理方法は、企業の収益や資産評価に大きな影響を与えるものです。グローバル化が進む現代のビジネス環境において、多くの日本企業もIFRSを採用し、FVTPLによる会計処理を行っています。本記事では、このFVTPLの概念から実務での応用まで、金融の専門知識がない方にもわかりやすく解説していきます。
この記事でわかること
- FVTPLの基本的な意味と、企業会計における役割について理解できます。
- 国際会計基準における金融商品の分類方法としてのFVTPLの位置づけがわかります。
- FVTPLが企業の財務諸表にどのような影響を与えるのか、具体例を通じて学べます。
- 日本企業のFVTPL活用事例から、実務での適用状況を知ることができます。
- 投資家や企業の財務担当者として知っておくべきFVTPLの重要ポイントを理解できます。
FVTPLの基本概念:定義と意味を理解する
FVTPLとは「Fair Value Through Profit or Loss(純損益を通じた公正価値)」の略称で、国際財務報告基準(IFRS)における金融資産や金融負債の分類・測定方法の一つです。簡単に言えば、金融商品を「公正価値(市場価値)」で評価し、その価値の変動を企業の「純損益(利益または損失)」に直接反映させる会計処理方法を指します。
FVTPLに分類された金融資産や負債は、毎期末に時価評価され、前期末からの価値の変動額が当期の損益計算書に計上されます。例えば、ある企業が保有する株式がFVTPL区分に分類されている場合、株価が上昇すれば評価益として利益に加算され、下落すれば評価損として利益から減算されることになります。
この処理方法の最大の特徴は、資産価値の変動が即座に企業の業績に反映される点にあります。これにより投資家は企業が保有する金融資産の現在価値をより透明に把握することができますが、一方で企業の損益が市場の変動に左右されやすくなるというデメリットも存在します。
【用語解説】公正価値(Fair Value): 公正価値とは、測定日に市場参加者間の秩序ある取引において、資産を売却するために受け取るであろう価格または負債を移転するために支払うであろう価格のことです。簡単に言えば「今その資産を売ったらいくらになるか」を示す価値であり、多くの場合は市場価格を参照して決定されます。公正価値の測定は、金融商品の実態を財務諸表により正確に反映させることを目的としています。
IFRS第9号における金融商品の分類体系とFVTPLの位置づけ
国際財務報告基準(IFRS)第9号「金融商品」では、金融資産を主に3つのカテゴリーに分類しています。その中でFVTPLは特徴的な位置づけにあります。IFRS第9号における金融資産の分類体系を理解することで、FVTPLの役割がより明確になるでしょう。
3つの主要分類カテゴリー
- 償却原価で測定する金融資産:契約上のキャッシュ・フローを回収することを目的とした事業モデルの中で保有され、かつ契約条件により元本と利息のみの支払いが特定の日に生じる金融資産。
- その他の包括利益を通じた公正価値で測定する金融資産(FVTOCI):契約上のキャッシュ・フローの回収と売却の両方を目的とする事業モデルの中で保有される金融資産、または当初認識時に取消不能な選択をした資本性金融商品への投資。
- 純損益を通じた公正価値で測定する金融資産(FVTPL):上記の2つのカテゴリーに該当しない全ての金融資産。
FVTPLは基本的に「その他」のカテゴリーという位置づけであり、償却原価やFVTOCIの条件を満たさない金融資産は原則としてFVTPLに分類されます。例えば、トレーディング目的で保有している株式や債券、デリバティブなどがこれに該当します。
分類決定のプロセス
金融資産の分類は、次の2つのテストに基づいて決定されます。
- 事業モデル・テスト:企業がどのように金融資産を管理しているか(キャッシュ・フローの回収を目的としているか、売却を目的としているかなど)。
- キャッシュ・フローの特性テスト:契約上のキャッシュ・フローが、特定の日に元本および元本残高に対する利息の支払いのみで構成されているか(元本と利息のみのキャッシュ・フロー、略してSPPI:Solely Payments of Principal and Interest)。
例えば、金利がコモディティ価格や株価に連動して決定される金融商品は、SPPIテストに合格せず、FVTPLに分類されることになります。
【用語解説】その他の包括利益(OCI: Other Comprehensive Income): その他の包括利益とは、伝統的な損益計算書では捉えられない包括的な利益の構成要素を指します。具体的には、有価証券の未実現損益、為替換算調整額、年金債務調整額などが含まれます。FVTOCIに分類された金融資産の公正価値変動は、この「その他の包括利益」に計上され、直接的には当期の純損益には影響しません。これにより、短期的な市場価格の変動が企業の報告利益に与える影響を軽減する効果があります。
FVTPLに分類される金融商品の特徴と具体例
FVTPLに分類される金融商品には、どのような特徴があり、具体的にはどのような商品が該当するのでしょうか。ここでは、典型的なFVTPL対象商品と、その分類理由について掘り下げていきます。
FVTPLに分類される主な金融商品
- デリバティブ:先物、オプション、スワップなどのデリバティブ商品は、ヘッジ会計が適用される場合を除き、原則としてすべてFVTPLとして処理されます。
- トレーディング目的の有価証券:短期的な価格変動を利用して利益を得ることを目的として保有する株式や債券は、FVTPLに分類されます。
- 複合金融商品:元本と利息以外の要素(例:コモディティ価格や株価に連動する部分)を含む複合的な金融商品は、その特性からFVTPLに分類されることが多いです。
- 資本性金融商品(株式等):企業が保有する他社の株式などの資本性金融商品は、FVTOCIを選択しない限り、FVTPLに分類されます。
- 一部の投資ファンド持分:ルック・スルー・アプローチを適用した際に、原資産プールが特定の要件を満たさない投資ファンドの持分もFVTPLに分類されます。
分類の判断基準と具体例
三井物産の事例では、「投資した結果の資産の売却、あるいは例えば上場のようなキャピタルイベントがあって利益が出る場合、これをFVTPLと言っており、一過性の収益に見えますが、我々としては実業の一環だと思っています」と説明されています。これは企業が戦略的に行う投資活動からの収益がFVTPLとして認識される例を示しています。
また、金融商品の契約条件も重要な判断要素となります。例えば、「金利更改日に1カ月LIBORを3カ月間適用する場合、金利にレバレッジ指標が組み込まれている場合」などは、元本と利息の関係が修正されるケースとして、その影響度によってはFVTPLに分類される可能性があります。
SBIホールディングスの財務諸表では、「FVTPLで測定すると指定した金融負債から生じる収益」として3,944百万円が計上されており、企業の収益構成の一部を形成していることがわかります。
【用語解説】ルック・スルー・アプローチ: ルック・スルー・アプローチとは、投資ファンドやトランシェなどの組成商品について、表面上の契約条件だけでなく、その裏付けとなる原資産のキャッシュ・フロー特性まで透過的に分析する手法です。IFRS第9号では、証券化商品などの分類にあたり、最終的な原資産プールの特性まで遡って検討することが求められており、この分析が行えない場合には、FVTPLに分類しなければならないとされています。
FVTPLと他の分類方法の違い:測定と損益認識の観点から
金融商品の会計処理方法は、その分類によって大きく異なります。ここでは、FVTPLと他の主要な分類方法である「償却原価」および「FVTOCI」を比較し、それぞれの特徴と違いについて解説します。
測定方法の違い
- FVTPL(純損益を通じた公正価値):
- 当初認識:公正価値で測定
- 事後測定:毎期末に公正価値で再測定
- 変動の認識:公正価値の変動はすべて純損益(P/L)に直接計上
- 償却原価(Amortized Cost):
- 当初認識:公正価値で測定
- 事後測定:実効金利法を用いた償却原価で測定
- 変動の認識:利息収益や減損損失は純損益に計上、市場金利変動による価値変動は認識しない
- FVTOCI(その他の包括利益を通じた公正価値):
- 当初認識:公正価値で測定
- 事後測定:毎期末に公正価値で再測定
- 変動の認識:公正価値の変動はその他の包括利益(OCI)に計上
特に注目すべきは、FVTPLとFVTOCIの違いです。どちらも公正価値で測定するという点では同じですが、その変動額の認識先が異なります。FVTPLは変動を直接純損益に反映するのに対し、FVTOCIは変動をOCIに計上し、純損益への影響を緩和します。
具体的な事例による比較
たとえば、ある企業が100億円で株式を取得し、期末には110億円の価値になったとします。
- FVTPLの場合:
- B/Sでは時価の110億円で計上
- P/Lでは評価益10億円を当期の損益に計上
- FVTOCIの場合:
- B/Sでは時価の110億円で計上
- 評価益10億円はOCIに計上され、純損益には影響しない
- 資本性金融商品がFVTOCIに指定された場合、将来売却時に売却益もOCIに計上され、純損益には計上されない(ノンリサイクリング)
- 償却原価の場合:
- 株式は償却原価測定の対象外ですが、例えば債券が償却原価区分の場合、市場価値の変動にかかわらず、取得価額を基に実効金利法で算出した金額で計上
楽天グループの資料によれば、「金利は契約上金利で計算、利息をP/Lに計上」するという特徴がFVTPLの金融商品にあります。また、三菱HCキャピタルのように「FVTPLの金融資産に分類しております。当初認識後、公正価値で測定し、その事後的な変動は純損益として認識しております」と明確に処理方法を定めている企業も多く見られます。
【用語解説】実効金利法: 実効金利法とは、金融資産または金融負債の償却原価を計算し、関連する期間にわたり利息収益または利息費用を配分する方法です。この方法では、金融商品の将来の予想キャッシュ・フローを、金融商品の当初の正味帳簿価額まで正確に割り引く利率(実効金利)を用います。これにより、金融商品の寿命にわたって一定の利回りが認識されることになります。日本基準では利息法と定額法の両方が認められていますが、IFRSでは実効金利法のみが認められています。
公正価値オプション:FVTPLへの自発的指定
IFRS第9号では、特定の条件下で、本来は他のカテゴリーに分類される金融資産や金融負債を企業の判断でFVTPLに指定することができる「公正価値オプション」が用意されています。この制度がどのように機能し、企業にどのようなメリットをもたらすのかを見ていきましょう。
公正価値オプションの概要
公正価値オプションとは、本来は償却原価またはFVTOCIで測定される金融資産や負債を、企業の任意でFVTPLに指定できる選択肢です。ただし、この選択は当初認識時にのみ行うことができ、いったん指定すると取り消すことはできません。
指定の条件
公正価値オプションを適用するには、以下のような条件を満たす必要があります。
- 会計上のミスマッチの解消・大幅削減:資産と負債が異なる測定基準で評価されることによる会計上のミスマッチを解消または大幅に削減する場合。
- 金融商品グループの管理:金融資産や金融負債のグループ(またはその両方)が、文書化されたリスク管理戦略に従って管理・評価されている場合。
例えば、ある金融資産と金融負債が密接に関連しているにもかかわらず、一方は償却原価で測定され、他方は公正価値で測定されると、損益の認識タイミングが合わず、経済的実態を適切に表さない可能性があります。このような場合に公正価値オプションを使用することで、両者を同じ基準で測定できるようになります。
自己の信用リスクの取扱い
IFRS第9号の特徴的な点として、金融負債を公正価値オプションでFVTPLに指定した場合、公正価値変動のうち企業自身の信用リスクの変動による部分はOCIに計上し(リサイクリング禁止)、それ以外の変動はP/Lに計上するという特別なルールがあります。ただし、この処理が会計上のミスマッチを生じさせる場合には、すべての変動をP/Lに計上することになります。
これは、企業の信用状態が悪化して負債の公正価値が下がった場合に、従来のルールでは利益が計上されるという直感に反する結果が生じるのを防ぐための規定です。
日本企業の適用事例
株式会社LIFULLの会計方針によれば、「金融資産及び金融負債は当初認識時において公正価値で測定しております。純損益を通じて公正価値で測定する金融資産(以下、「FVTPLの金融資産」という。)及び純損益を通じて公正価値で測定する金融負債(以下、「FVTPLの金融負債」という。)は当初認識時の公正価値に直接帰属する取引費用を純損益で認識しております」と説明されています。
また、伊藤忠エネクスの金融資産についても、「FVTOCI の代わりに公正価値オプションを当初認識時に利用できる」という記述が見られ、公正価値オプションが実務で活用されていることがわかります。
【用語解説】会計上のミスマッチ: 会計上のミスマッチとは、経済的には関連する資産と負債が異なる測定基準で評価されることにより、損益の認識タイミングや金額に不整合が生じる状況を指します。例えば、変動金利の貸付金(償却原価で測定)と、それをヘッジするための金利スワップ(公正価値で測定)の組み合わせでは、金利変動時に損益認識のタイミングが合わなくなります。公正価値オプションを適用して両者をFVTPLで測定することで、このようなミスマッチを解消することができます。
FVTPLが企業の財務諸表に与える影響
FVTPLによる測定は、企業の財務諸表にどのような影響を与えるのでしょうか。ここでは、損益のボラティリティ、情報開示の透明性、そして投資家への影響という観点から検討します。
損益のボラティリティへの影響
FVTPLに分類された金融商品は、その公正価値の変動が直接純損益に反映されるため、市場価格の変動が大きい場合、企業の報告利益も大きく変動する可能性があります。
例えば、三井物産では「FVTPL をどう予算化するか、どう皆様にお伝えするかという点で工夫の余地はありますが、我々の実業の一部とご理解頂ければと思います」と説明しており、FVTPLによる収益の予測可能性の課題を認識しています。
一方、銀行セクターでは「IFRS第9号の従来の要求事項と比較して、償却原価測定の事業モデルのテストにパスしないためFVTPLで測定されていた資産が、[新基準では別のカテゴリーに分類される可能性があり]銀行における純損益のボラティリティが低減」する可能性も指摘されています。
開示要件と透明性
IFRS第7号「金融商品:開示」では、FVTPLに分類された金融商品について特別な開示が求められています。例えば、
- FVTPLに指定した金融資産及び金融負債の性質
- FVTPLの指定基準、公正価値オプションの適用によりFVTPLに指定した場合には、要件をどのように満たしているのかの説明
- FVTPL区分の金融負債の帳簿価額(公正価値)と満期時の要支払額との差額の開示
これらの開示要件により、投資家はFVTPLに分類された金融商品のリスクとリターンをより明確に理解することができます。
実際の企業財務への影響例
SBIホールディングスの2023年度第2四半期報告書によれば、「FVTPLで測定すると指定した金融負債から生じる収益」が3,944百万円計上されています。これは企業の収益の一部を構成する重要な要素となっています。
また、暗号資産交換業などを行う事業セグメントでは、前年同期に12,781百万円の損失だったものが、当期は674百万円の税引前利益となったと報告されています。このような変動は、FVTPLで測定される暗号資産の価格変動が業績に大きな影響を与えた可能性を示唆しています。
三井物産では、「マーケットの事情やキャピタルイベントへの個社の戦略対応が様々なシナリオの下で行われますので、FVTPLを期首で予算化するのは困難です。長い年月の中で当社のトラックレコードを見た際に、平均すると基礎収益の一部を成しているという形で見て頂ければと思います」と述べられており、FVTPLによる収益が長期的には安定した収益源となり得ることを示しています。
【用語解説】ボラティリティ: ボラティリティとは、金融市場において価格や利益率などの変動性を表す指標です。高いボラティリティは大きな価格変動を意味し、リスクの高さを示します。FVTPLに分類された金融商品は、市場価格の変動が直接企業の損益に反映されるため、特に市場が不安定な時期には企業の報告利益のボラティリティを高める要因となります。投資家や経営者は、このボラティリティをどう評価し管理するかが重要な課題となります。
日本企業におけるFVTPLの活用事例
日本企業においても、IFRSを採用する企業が増えるにつれて、FVTPLの活用事例が増えています。ここでは、実際の日本企業がどのようにFVTPLを活用しているのかを見ていきましょう。
金融セクターにおける活用
SBIホールディングス:2023年度第2四半期累計期間の財務諸表では、「FVTPLで測定すると指定した金融負債から生じる収益」として3,944百万円を計上しています。また、暗号資産事業セグメントでは、前年同期の12,781百万円の損失から当期は674百万円の税引前利益へと業績が改善しており、FVTPLで測定される暗号資産の価格変動が業績に影響していることがうかがえます。
三菱HCキャピタル:「当初認識後、公正価値で測定し、その事後的な変動は純損益として認識しております」とFVTPLの金融資産の測定方法を明確に定めています。リース事業を中心とする同社では、2018年度に証券化商品への投資やインフラ投資など多様な金融商品を扱っており、FVTPLによる測定が重要な役割を果たしていると考えられます。
商社・事業会社における活用
三井物産:「投資した結果の資産の売却、あるいは例えば上場のようなキャピタルイベントがあって利益が出る場合、これをFVTPLと言っており、一過性の収益に見えますが、我々としては実業の一環だと思っています」と述べています。また、「会社全体ではポートフォリオ効果により毎年一定の収益を出す形で取り組んでいます」とし、長期的な視点でFVTPL収益を捉えていることがわかります。
株式会社LIFULL:同社の2019年度の連結財務諸表では、「FVTPLの金融資産」および「FVTPLの金融負債」の会計処理について明確に規定しています。当初認識後、FVTPLの金融資産は公正価値で測定し、公正価値の変動から生じる評価損益、配当収益及び利息収益は純損益で認識すると説明しています。
FVTPLが企業戦略に与える影響
FVTPLによる測定は、単なる会計処理以上の意味を持ちます。三井物産のケースでは、FVTPLによる収益を「実業の一環」と位置づけ、投資・売却のサイクルを通じた価値創造を事業戦略の重要な一部としています。
また、企業買収や資本提携の際にも、FVTPLの適用は重要な考慮事項となります。株式会社LIFULLは2019年にMitula Group Limitedを買収しましたが、このような買収に伴う資産評価においてもFVTPLの測定方法が適用されることがあります。
企業はFVTPLによる損益のボラティリティを管理しながらも、その透明性と即時性のメリットを活かした経営戦略を構築していることがわかります。
【用語解説】キャピタルイベント: キャピタルイベントとは、企業の資本構成や価値に重大な変化をもたらす出来事を指します。具体的には、IPO(新規株式公開)、M&A(合併・買収)、増資、自社株買い、株式分割などが含まれます。三井物産の説明にあるように、投資先企業の上場などのキャピタルイベントによって発生する利益は、FVTPLとして認識されることがあります。このような一時的に見える収益も、戦略的な投資活動の結果として企業の基礎収益の一部を形成していると捉えることができます。
ビジネスパーソンがFVTPLを理解する意義
FVTPLは一見すると会計技術の一つに過ぎないように思えますが、現代のビジネスパーソンがこの概念を理解することには、様々な意義があります。特に、財務諸表を読み解く力、投資判断への影響、そしてグローバルビジネスの理解という観点から、FVTPLの知識は重要です。
財務諸表を読み解く力の向上
FVTPLを理解することで、企業の財務諸表をより深く分析できるようになります。例えば、
- 利益の質:FVTPLによる収益が多い企業は、市場変動に左右される可能性が高く、利益の安定性を評価する際に注意が必要です。
- 隠れたリスクの発見:FVTPLで測定される金融商品のリスク特性を理解することで、財務諸表の数字だけでは見えない潜在的なリスクを発見できます。
- 企業間比較:異なる会計基準や測定方法を採用している企業を比較する際に、FVTPLの影響を考慮することで、より正確な比較が可能になります。
投資判断への影響
投資家や金融アナリストにとって、FVTPLの理解は投資判断において重要な要素となります。
- 短期的な業績変動の解釈:FVTPLによる評価損益が大きい場合、一時的な市場変動による影響なのか、根本的なビジネスモデルの問題なのかを見極める必要があります。
- 業績予測の精度向上:「FVTPLを期首で予算化するのは困難」と三井物産が述べているように、FVTPLの性質を理解することで、企業の業績予測をより現実的に行えるようになります。
- リスク評価:FVTPLに分類される金融商品の種類と量を把握することで、企業が抱えるリスクプロファイルをより正確に評価できます。
グローバルビジネスにおける共通言語
IFRSはグローバルな会計基準として多くの国で採用されており、FVTPLの理解はグローバルビジネスを理解する上での共通言語となります。
- 国際的な取引の理解:海外企業との取引や提携において、会計処理の違いによる誤解を防ぐことができます。
- キャリア発展:国際的な金融機関や企業で働く際に、FVTPLを含むIFRSの知識は重要なスキルとなります。
- 財務報告の変化への対応:「IFRS第9号の従来の要求事項と比較して…銀行における純損益のボラティリティが低減」するなど、会計基準は進化し続けています。FVTPLの基本概念を理解することで、こうした変化にも柔軟に対応できるようになります。
【用語解説】利益の質: 利益の質(Earnings Quality)とは、報告された利益の持続可能性、予測可能性、ボラティリティなどを評価する概念です。高品質な利益は、営業活動から安定的に生み出される現金を伴うもので、将来も持続する可能性が高いとされます。一方、FVTPLによる評価益のように、市場変動に左右される一時的な利益は、質が低いと判断されることがあります。投資家は単に利益の金額だけでなく、その質を評価することで、より長期的な投資判断を行うことができます。
まとめ:FVTPLの重要ポイントと今後の展望
本記事では、国際財務報告基準(IFRS)における金融商品の分類・測定方法の一つである「FVTPL(純損益を通じた公正価値)」について解説してきました。ここで重要なポイントを整理し、今後の展望についても触れていきましょう。
FVTPLの重要ポイント
- 基本概念と位置づけ:
- FVTPLは「Fair Value Through Profit or Loss(純損益を通じた公正価値)」の略称で、金融商品を公正価値で測定し、その変動を直接純損益に反映させる会計処理方法です。
- IFRS第9号では、金融資産は主に「償却原価」「FVTOCI」「FVTPL」の3つに分類され、FVTPLは他の2つのカテゴリーに該当しない金融資産が分類される「その他」のカテゴリーという性格も持っています。
- 分類の判断基準:
- 事業モデル・テスト(企業がどのように金融資産を管理しているか)と、キャッシュ・フローの特性テスト(契約上のキャッシュ・フローが元本と利息の支払いのみで構成されているか)の2つに基づいて分類が決定されます。
- デリバティブ、トレーディング目的の有価証券、複合金融商品などがFVTPLに分類されることが多いです。
- 公正価値オプション:
- 特定の条件下で、本来は償却原価やFVTOCIで測定される金融資産・負債を企業の判断でFVTPLに指定できる「公正価値オプション」が存在します。
- 会計上のミスマッチを解消・大幅削減する場合などに活用されます。
- 財務諸表への影響:
- FVTPLによる測定は、市場価格の変動が直接純損益に反映されるため、企業の報告利益のボラティリティを高める可能性があります。
- 一方で、投資家に対しては資産価値をより透明に開示することができるというメリットもあります。
- 日本企業の活用事例:
- SBIホールディングス、三井物産、三菱HCキャピタル、株式会社LIFULLなど多くの日本企業がFVTPLを活用しています。
- 三井物産のように、FVTPLによる収益を「実業の一環」と位置づけ、長期的な視点で捉える企業もあります。
今後の展望
FVTPLを含む金融商品の会計処理は、今後も進化し続けると考えられます。特に以下の点について注目が必要です。
- デジタル資産への適用: 暗号資産やデジタルトークンなどの新しい資産クラスに対して、FVTPLがどのように適用されるかは今後も議論が続くでしょう。SBIホールディングスの例にあるように、暗号資産事業はすでにFVTPLの影響を受けています。
- 日本基準とIFRSの収斂: 日本においても、国際的な会計基準との整合性を高める動きが続いており、今後もFVTPLを含むIFRSの考え方が日本の会計実務に影響を与えていくと考えられます。
- 非財務情報との統合: ESG(環境・社会・ガバナンス)情報など非財務情報の重要性が高まる中、FVTPLで測定される金融商品と、これらの非財務要素がどのように関連づけられるかも注目点です。
FVTPLは単なる会計技術ではなく、企業の財務戦略や投資判断に大きな影響を与える重要な概念です。グローバル化が進む現代のビジネス環境において、FVTPLの理解は財務的素養の重要な一部となっています。本記事を通じて、FVTPLに関する基本的な知識と実務への応用について理解を深めていただければ幸いです。


