持株会のメリットとデメリットを比べてみた結果!
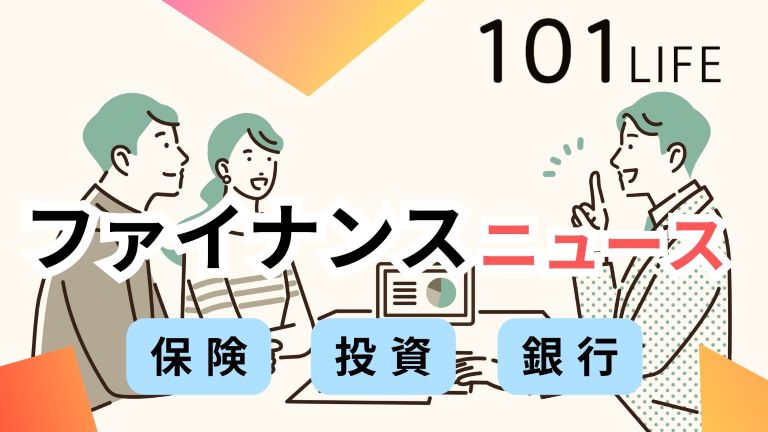
”やめたほうがいい”、”やめとけ”という意見も、従業員持株会のメリットとデメリット:口コミと評判から探る真相
従業員持株会についてネットの口コミや評判から真相を掘り下げてみました。近年、多くの企業で導入されている従業員持株会は、収入とは別の資産形成手段として注目されていますが、その実態はどうなのでしょうか。東京証券取引所の調査によれば、2023年3月末時点で上場企業の約8割が導入しており、加入者数は約311万人に上るとされています。この記事では、従業員持株会の基本的な仕組みから、従業員と企業それぞれの視点でのメリット・デメリット、そして「持株会はやめとけ」と言われる理由まで徹底解説します。
従業員持株会の基本的な仕組み
従業員持株会とは、企業の従業員が一定の金額を拠出して、自社の株式を購入・保有するための制度です。この制度は、従業員の資産形成支援や企業への帰属意識を高めるなどの目的で導入されています。
基本的な仕組みは以下の通りです。
- 拠出金の徴収:従業員(会員)から毎月の給与や賞与から一定額が天引きされ、それが拠出金となります。
- 株式の購入:持株会がこの拠出金を原資として、定期的(通常は月1回程度)に自社株を市場から購入します。
- 持分の配分:購入した株式は、各会員の拠出金額に応じて持分が配分されます。
- 配当金の受取:株式から生じる配当金は、持株会を通じて会員に配分されます。
持株会を通して購入した株式は、個人名義ではなく持株会名義で管理されることになります。そのため、株式の売却を希望する場合は、持株会から個人の証券口座への移管といった手続きが必要になるのです。
また、多くの企業では「奨励金」という制度を設けており、従業員が拠出した金額に対して一定割合(一般的に5~10%程度)の金額を企業が上乗せすることで、より多くの株式を購入できるようにしています。
従業員持株会の2つの制度タイプ
持株会には、「従業員持株会型ESOP信託」と「株式給付型ESOP」という2つの制度タイプが存在します。これらは日本版ESOPとも呼ばれています。
従業員持株会型ESOP信託:信託受託者が企業から一括で株式を購入し、持株会は信託受託者から株式を決まった価格で購入します。信託終了時の損失は企業が負担するため、従業員は市場変動のリスクを抑えられます。
株式給付型ESOP:退職時または在職中に、自社株が従業員へ報酬として付与される制度です。
どちらも福利厚生制度ですが、前者は従業員が資金を拠出する投資であり、後者は企業からの報酬という違いがあります。
従業員側から見たメリット
従業員持株会には、従業員にとって様々なメリットがあるとされています。ここでは主な利点について解説します。
奨励金が付与される
従業員持株会の最も大きなおすすめポイントの一つが「奨励金」です。奨励金とは、従業員が自社株を購入する際に、企業が一定割合の金額を上乗せし、その分多くの株式を購入できる仕組みです。
持株会を導入している企業の約9割が奨励金制度を採用しており、一般的には拠出金の5~10%が上乗せされるケースが多いようです。例えば、毎月1万円を拠出した場合、奨励金が10%であれば実際には1万1千円分の株式を購入できることになります。
奨励金は従業員持株会への加入促進において強いけん引力を持つため、多くの企業が導入しているとされています。
少額から株式購入が可能
通常、株式市場では株式は100株単位(1単元)での取引が基本となっています。株価が高い企業の場合、まとまった資金がないと購入できない場合もあります。
しかし、持株会では1株から購入できる点が大きな利点です。毎月の拠出金が数千円程度からでも自社株への投資が可能で、少額から資産形成を始められます。
一般的な最低拠出額は1,000円~数千円程度と、比較的小さな金額から始められるため、投資初心者にもおすすめの制度と言えるでしょう。
中長期的な資産形成がしやすい
持株会は、毎月の給与から一定額が天引きされるため、継続的な資産形成が可能です。「給与の大半を使い込んでしまう」という人でも、天引きによって確実に資産形成に回すことができます。
「毎月の積み立てにより中長期的な資産形成ができる点も魅力といえるでしょう」と評価されています。また、「毎月一定の金額で自社株を購入できる」ため、時間分散投資の効果も期待できます。
配当金・キャピタルゲインを得られる
持株会を通じて自社株を保有することで、企業の業績に応じた配当金を受け取ることができます。また、株価が上昇した場合には、キャピタルゲイン(売却益)も期待できます。
「持株数が多いほど、業績が伸びたときに配当金を多く得られます」。持株会に長く加入し続けることで保有株式数も増えていき、配当金や将来のキャピタルゲインの可能性も高まるでしょう。
手間がかからない
持株会は、一度加入すれば給与天引きにより自動的に自社株式を購入できるシステムです。自分で買い時を判断する必要がなく、手間もかからないため、多忙な人や投資の知識が少ない人でも資産形成に取り組みやすいという特徴があります。
「自分で買い時を判断する必要がない」点は、特に投資初心者にとって大きなメリットと言えるでしょう。
企業側から見たメリット
従業員持株会は従業員だけでなく、企業側にも様々なメリットをもたらします。
安定株主の確保
持株会が株式を購入する際の資金は、会員となった従業員から集めた拠出金です。持株会では会員が継続して自社株を購入するため、株価の安定につながります。
従業員が自社株の多くを保有している状態では、自社株が外部へ流出しにくくなり、企業の経営も安定しやすくなります。また、「買収防止策などのさまざまな効果を生み出せます」とされており、敵対的買収に対する防衛策としても機能します。
従業員のモチベーション向上
従業員が自社の株主となることで、「自分たちの会社」という意識が高まり、モチベーションの向上につながります。自社の株価や配当に直接的な利害関係を持つことで、業績向上への意欲も高まるとされています。
「自社株を持つことで、直接的な利益だけでなく、会社とのつながりを深めることもでき、それが自分のビジネスをより良いものにする一助となるでしょう」と評価されています。
生産性の向上や離職率の低下、さらには採用力の強化にもつながる可能性があります。
福利厚生の充実
奨励金の支給など様々な支援を行い、従業員の中長期的な資産形成をバックアップする持株会は、企業が自主的に導入している法定外の福利厚生として位置づけられています。
福利厚生が充実していることは、対外的な評価や従業員の満足度の向上にもつながるでしょう。
経営の透明性向上
従業員持株会のメンバーが増えることで、企業の内部統制とガバナンスが強化されるという側面もあります。従業員が自社の株主となることで、企業経営に対する透明性が要求され、結果として健全な経営につながると言われています。
従業員側から見たデメリット
持株会には多くのメリットがある一方で、デメリットや注意点も存在します。ここでは、従業員側から見た持株会のデメリットについて解説します。
リスク分散ができず会社への依存度が高い
持株会の最も大きなデメリットの一つが、「リスク分散ができず、会社への依存度が高まる」という点です。投資において基本的なリスク管理の原則は「分散投資」ですが、持株会では自社株だけに投資することになります。
従業員は給与も自社からもらっているため、収入と資産の両方を同じ会社に依存することになります。これは非常に「やばい」状況になり得ます。もし会社の業績が悪化した場合、給与が減少するだけでなく、保有している自社株の価値も下落するという「ダブルパンチ」を受ける可能性があるのです。
「持株会では、収入と資産の両方を会社に依存する形となるため、従業員が十分なリスク分散ができなくなる点には留意しましょう」という指摘があります。
最悪のケースでは、「会社が倒産し、収入と資産を共に失う事態も想定されます」。このようなリスクがあるため、「持株会はやめとけ」というアドバイスを受ける従業員も少なくないようです。
自由に売買できない
持株会では自社株の購入タイミングが「月1回」などと決まっているため、好きなタイミングで自社株を買うことができません。
また、持株会で保有している自社株を売却したい場合も、簡単にはいきません。自社株は会社の証券口座で管理されているため、売却するためには以下のような手続きが必要になります。
- 勤め先の幹事証券会社で個人名義の証券口座を開設する
- 持株会事務局に口座移管の申請をする
- 個人の証券口座に自社株が移管されたら、市場で売却する
このような手順が必要なため、自社株を売却して現金を手に入れるまでに2週間~1か月ほどかかるケースが一般的です。まとまった資金が急に必要になった場合に、すぐに現金化できない点はおすすめしない要因の一つと言えるでしょう。
株主優待がもらえない
持株会で自社株に投資している場合、配当はもらえますが株主優待はもらえません。これは、持株会名義で自社株を保有しているためです。
「個人名義の証券口座で自社株を購入するのではなく、持株会の名義で行う制度です。従業員が持株会を通じて株式を購入しても株主優待は受けられない点に注意が必要です」。
多くの会社では、商品の割引券やサービス券、自社商品の詰め合わせなどの株主優待を実施しており、これを目的に株式投資をしている投資家も少なくありません。しかし、持株会では株主優待という魅力的な特典を受けられないという欠点があります。
企業側から見たデメリット
従業員持株会は企業側にもいくつかのデメリットをもたらす可能性があります。
運用コストの発生
持株会の運営には、事務委託手数料などのコストがかかります。これらのコストは会社側と従業員どちらが負担するか選択できますが、会社側が負担する場合は年々増加していく傾向にあり、企業の財務的負担となる可能性があります。
また、持株会が購入する株式には優先的に配当を行うケースも多く、業績が悪化した場合でもある程度の配当を捻出しなければならないという負担も生じます。「配当金の負担などのデメリットもあるため、その仕組みを理解したうえで慎重に導入するのが肝要です」。
会社支配権の低下
従業員持株会の導入により、従業員のモチベーションは高まる一方で、「会社の経営者である取締役などの役員の支配権が弱まる恐れがあります」。
「従業員持株会の会員である従業員の数が増えれば増えるほど、経営者陣の会社支配権は弱まります」。これは、「一定以上の株式を所有する株主に許された決議権」に関わる問題で、ガバナンスの観点からは良い面もありますが、意思決定の迅速性などに影響を与える場合もあるでしょう。
キャッシュフローの圧迫
従業員の退職や配当の支払いなどで、企業側のキャッシュフローを圧迫することがあります。特に業績が悪化している状況で多くの従業員が退職し、持株会から株式の買い戻しが発生した場合などは、企業の資金繰りに影響を与える可能性があります。
株式の流動性低下
従業員持株の増加により、公開株式の流動性が低下し、株価形成機能が損なわれる可能性もあります。株式市場での取引量が減少すると、適正な株価形成が難しくなり、結果として企業価値の評価にも影響を与える可能性があります。
持株会に関する口コミ・評判
実際に持株会に加入している、または加入を検討している従業員からは、様々な意見が寄せられています。ここでは、よく見られる口コミや評判を紹介します。
好意的な口コミ・評判
「奨励金のおかげで資産が増えている」 持株会の奨励金(5~10%)のおかげで、自分の拠出金以上の株を購入できているという声が多く見られます。長期で見れば、かなりの効果があるようです。
「強制的に資産形成ができるのが良い」 給与から天引きされるので、使い込む前に投資に回せるのが良いという意見もあります。自分で管理するよりも確実に積立できているようです。
「配当金が思った以上に嬉しい」 年2回もらえる配当金が、思った以上に嬉しいという声も。会社の業績が上がるとその分配当も増えるので、仕事へのモチベーションにもなっているようです。
否定的な口コミ・評判
「リスクが集中しすぎて不安」 給料も資産も同じ会社に依存していると思うと不安だという声があります。「社員持株会の最大のデメリットは、リスクが分散されていないことです。給与と資産の両方が同じ会社に依存するため、業績が悪化すると『給与の減少』と『株価の下落』という二重の影響を受ける可能性があります」という指摘もあります。
「売却の手続きが面倒」 急に資金が必要になった時に、持株会の株式をすぐに現金化できないのが不便だという意見もあります。移管の手続きなどで時間がかかるので、流動性の高い資産とは言えないようです。
「やめたほうがいいと言われたが判断に迷う」 「知人に、持株会よりも自分で資産運用したほうがいい、だから持株会はやめたほうが良い、と言われました」という相談も見られます。奨励金などのメリットもあるので判断に迷っているという声が多いようです。
これらの口コミからも分かるように、持株会の評価は個人の状況や会社の状況、リスク許容度などによって大きく異なります。一概に「良い」「悪い」とは言えず、自分の状況に合わせて判断することが重要と言えるでしょう。
持株会をやめるべきかどうかの判断ポイント
「持株会はやめとけ」というアドバイスを受けることもありますが、実際にやめるべきかどうかは個人の状況によって異なります。ここでは、持株会への加入や継続を検討する際のポイントをいくつか紹介します。
会社の将来性
自社の業績や成長性についてどう評価しているかは重要な判断材料になります。将来性に期待が持てる会社であれば、長期的に見て持株会に参加するメリットは大きいかもしれません。反対に、業界や会社の先行きに不安がある場合は、慎重な判断が必要でしょう。
資産全体におけるバランス
持株会で保有する自社株が資産全体に占める割合も重要です。一般的には、資産の分散投資が推奨されており、一つの資産(特に勤務先と同じ会社の株式)に集中投資することはリスクが高いと言われています。
自社株の比率が高すぎる場合は、NISA(少額投資非課税制度)やiDeCo(個人型確定拠出年金)などを活用して、他の資産への分散も検討すべきでしょう。
資金の流動性ニーズ
短期的に資金が必要になる可能性がある場合は、持株会のみに資金を集中させることは避けたほうが良いでしょう。持株会からの引き出しには時間がかかるため、緊急時の資金需要には対応しづらいという特徴があります。
奨励金の水準
会社が提供する奨励金の水準も重要な判断材料です。奨励金が10%など高水準であれば、それだけ投資効率は良くなります。しかし、奨励金が低い場合やまったくない場合は、他の投資手段と比較検討する価値があるでしょう。
やめる方法の選択肢
持株会をやめる場合、完全に退会する方法と、加入は継続しつつ一部資金を引き出す方法があります。また、持株会から口座移管して個人の証券口座で自社株を管理するという選択肢もあります。
口座移管することで、「自社株を好きなタイミングで自由に売買できる」「自社株以外にも投資できる」といったメリットが得られます。個人の状況に応じて最適な方法を選択することが重要です。
まとめ
従業員持株会は、企業と従業員の双方にメリットとデメリットをもたらす制度です。
従業員側のメリットとしては、奨励金の付与、少額から始められる株式投資、中長期的な資産形成のしやすさ、配当金・キャピタルゲインの獲得可能性、手間のかからない投資方法などが挙げられます。これらは資産形成を始めたい方におすすめの利点と言えるでしょう。
一方、デメリットとしては、リスク分散ができずに会社への依存度が高まる点、自由に売買できない制約、株主優待がもらえない点などがあります。「やばい」と感じる人もいるほど、特にリスク分散の問題は重要な欠点と言えます。
企業側にとっても、安定株主の確保、従業員のモチベーション向上、福利厚生の充実、経営の透明性向上などのメリットがある一方、運用コストの発生、会社支配権の低下、キャッシュフローの圧迫、株式の流動性低下などのデメリットも存在します。
持株会に加入するべきか、「やめとけ」というアドバイスに従うべきかは、個人の状況や会社の将来性、資産全体のバランス、資金の流動性ニーズ、奨励金の水準などを総合的に判断する必要があります。
最適な判断をするためには、持株会の仕組みやメリット・デメリットを十分に理解し、自分のライフプランやリスク許容度と照らし合わせて検討することが重要です。状況によっては、持株会に加入しつつ他の投資も並行して行うという選択肢も考えられるでしょう。
日本証券業協会のガイドラインによれば、従業員持株会の目的は「従業員の福利厚生の増進及び経営への参加意識の向上」と定義されています。この目的に沿って、従業員と企業がWin-Winの関係を築けるような持株会の活用が理想的と言えるでしょう。
従業員持株会は多くの人にとって資産形成の第一歩となる可能性がある一方で、リスク管理の面では注意も必要な制度です。この記事が、持株会についての理解を深め、より良い意思決定の一助となれば幸いです。


