確定拠出年金(iDeCoや企業型DC)のメリットとデメリットを比べてみた結果!
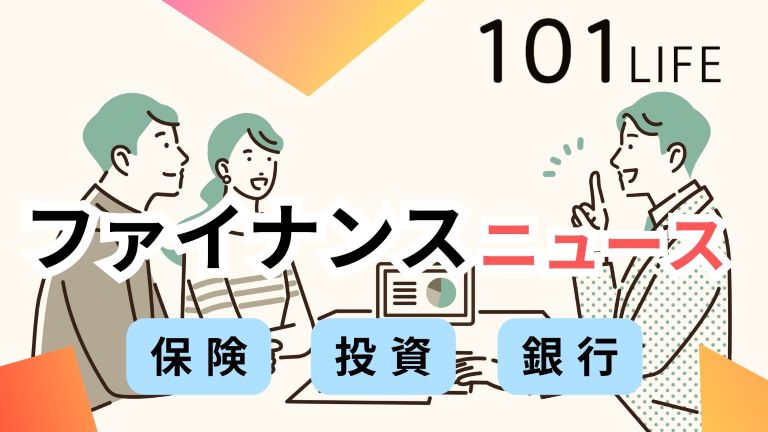
”だまされるな”、”入らない方がいい”という意見も、確定拠出年金のメリットとデメリット:口コミと評判から真相を掘り下げる
確定拠出年金について「やばい」「やめたほうがいい」という声もあれば、「老後の備えに最適」という声まで、さまざまな意見が飛び交っています。今回は確定拠出年金(iDeCoや企業型DC)のメリットとデメリットについてネットの口コミや評判から真相を掘り下げてみました。この記事では、実際の利用者の声や専門家の意見も踏まえながら、確定拠出年金が本当におすすめできる制度なのか、あるいは避けるべきなのかを徹底的に検証します。
確定拠出年金とは?基本的な仕組みを理解する
確定拠出年金は、老後の資産形成を目的とした私的年金制度のひとつです。大きく「企業型確定拠出年金(企業型DC)」と「個人型確定拠出年金(iDeCo)」の2種類に分けられます。
企業型確定拠出年金は、企業が掛金を拠出し、従業員が自ら資産運用を行う制度です。一方、iDeCoは個人が掛金を拠出し運用する制度となっています。両者とも積立・運用・受取の各段階で税制優遇があり、老後資金の形成を後押しする仕組みとなっています。
この制度は、以前は一部の勤労者のみが対象でしたが、2017年に専業主婦や公務員なども加入対象となり、より広く国民が利用できる制度へと変化してきました。
確定拠出年金の魅力的なメリット
1. 税制優遇が最大の利点
確定拠出年金の最大のおすすめポイントは、3つのタイミングで受けられる税制優遇です。具体的には以下の通りです。
- 積立時:所得税と住民税が軽減されます。iDeCoで拠出する毎月の掛金は全額所得控除の対象となり、拠出した掛金の年間総額が所得から差し引かれるため、所得税と住民税の負担が減ります。
- 運用時:運用で得た利息・利益に税金がかかりません(運用益が非課税)。
- 受取時:一定額までは税金がかからないよう控除が適用されます。
この3段階の税制優遇は、他の投資方法にはない確定拠出年金ならではの大きな利点と言えるでしょう。
2. 長期的な資産形成に効果的
確定拠出年金は、長期・分散・積立という資産運用の基本を実践するのに最適な制度です。運用実績の良い商品では「2018年10月31日から2024年10月4日の運用実績では年率18.44%と高水準」を記録したものもあるようです。
長期間継続して積み立てることで、運用による複利効果も期待できます。投資信託の価格変動を活用しながら、時間をかけて資産を育てていく仕組みとなっています。
3. 離職・転職しても継続可能
今の勤務先から転職したり、あるいは退職して専業主婦(夫)になるなど仕事を離れると、積み立てできる金額が変わることはありますが、基本的にはiDeCoでの積み立てや運用を続けられます。
転職先の企業年金などの理由でiDeCoをやめなければならない場合でも、運用していた資産は他の年金制度へ持ち運び(ポータビリティ)できるという利点があります。
確定拠出年金の意外なデメリット
1. 60歳まで原則引き出せないという大きな欠点
確定拠出年金のデメリットとして最も重要なのは、原則として60歳になるまで受け取りができないことです。フィデリティ投信の調査でも、DCの悪い点として「60歳まで引き出しができない」が最も多く挙げられており、DCに加入していない人の理由のトップも「60歳まで引き出しできないから」(23%)でした。
これは思わぬライフイベントや急な出費が必要になった時に、資金を引き出せないというリスクを伴います。このデメリットは「やめたほうがいい」「やめとけ」と言われる最大の理由の一つと言えるでしょう。
2. 運用次第で資産が減額するリスク
iDeCoは自身の資産運用の結果次第で、60歳以降に受け取れる給付金の額が増えることもありますが、逆に減額してしまう可能性もあります。
「運用する金融商品選びに失敗してしまうと、資産を増やすどころか減ってしまうリスクもある」という点は非常に重要なデメリットです。コロナショック時には-20.2%の下落を記録した商品もあり、リスクの高さが気になる人にはあまり向いていないと言えるでしょう。
3. 手数料がかかる
確定拠出年金では、加入時(初回1回のみ)や運用期間中(毎月)、受け取り時(振り込みの都度)に費用がかかります。約3000円の初期費用に加え、運営管理機関や商品によって異なる手数料が継続的にかかるため、少額投資の場合は特に注意が必要です。
これらの手数料は運用益を圧迫する要因となるため、「確定拠出年金はやばい」と評価される一因となっているようです。
4. 自分で運用商品を選ぶ難しさ
企業型DCを利用している人へのアンケートでは、困った点として「自分で運用商品を選ぶのが難しい」(34.1%)、「元本割れしないか不安」(26.7%)が上位に挙げられています。
投資初心者にとっては、どの商品を選べばよいかの判断が非常に難しく、この点でおすすめしにくい側面があります。特に「選択肢が多すぎて逆に迷う」という声も多いようです。
実際の口コミと評判から見る確定拠出年金の真実
良い評判:成功体験を得た人たち
フィデリティ投信の「確定拠出年金(DC)加入者意識調査」によると、運用状況について「うまくいっている」と回答した人は39%と全体の約4割を占めていました。「普通」とする回答も38%あり、「うまくいっていない」は10%と少数派でした。
運用がうまくいった理由としては、「市場環境が良かった」(35%)、「商品選択が良かった」(35%)、「長期運用を実践した」(34%)が上位となっています。
企業型DCを利用して良かった点としては「老後の不安が減った」(33.4%)、「老後資金を計画的に貯められている」(27.1%)という声が多く見られます。
悪い評判:「やめとけ」と言われる理由
一方で、「iDeCoはやらないほうがいい」「iDeCoはデメリットしかない」という噂も広がっています。その理由として挙げられているのは以下の点です。
- 運用次第で資産が減額してしまう
- 運用中の資金は原則60歳まで引き出せない
- 手数料がかかる
- 最低拠出額は5,000円と負担が大きい
特に「iDeCoは『60歳まで原則引き出しができない』『損をすることもある』などのデメリットがあるため、『やめとけ』という声が一部で上がっている」という意見もあり、流動性の低さがネックになっていると言えるでしょう。
中立的な意見:商品によって評価が分かれる
松井証券iDeCoの利用者からは、以下のような中立的な意見も見られます。
- コスト面や商品数は魅力的
- ネットを活用できる人には便利だが、対面サービスを好む人には向いていない
野村證券のiDeCoについては「サポート力のあるwebコールセンター」「初心者向けに厳選された商品ラインアップ」「高品質のサービスを低コストで利用可能」といった評価がある一方で、商品選択の難しさに対する不安の声も見られます。
確定拠出年金が向いている人・向いていない人
向いている人
確定拠出年金が特におすすめなのは以下のような方々です。
- 長期の積み立てができる20〜30代:一時的な大きな値下がりリスクを許容できる人にぴったりです。
- 給与所得者で税負担が大きい人:税制優遇のメリットを最大限に活かせます。
- 老後の備えを計画的に行いたい人:企業型DCを利用したきっかけとして最も多かったのは「老後へ向けた資産形成をしたかったから」(29.6%)という理由でした。
向いていない人:おすすめしない事例
逆に、確定拠出年金は以下のような方々にはおすすめしにくいと言われています。
- 運用中の資金を自由に引き出したい人:原則60歳以降にならないと引き出しができないため。
- 余剰資金があまりない人:急な出費に対応できなくなる可能性があります。
- 収入が安定していない人:「将来的な収入が安定していない人もiDeCoは不向き」と言われています。
- すぐに利益を出したい人:確定拠出年金は長期運用を前提とした制度です。
成功事例と失敗事例から学ぶ
成功事例:長期運用の力
ある40代女性の相談事例では、最初iDeCoの運用がマイナスで不安を感じていたものの、長期的な視点から投資を続けたところ、半年後にはプラス評価になり、その後も順調に資産を増やしていったケースが報告されています。
この事例からわかるのは、「長期・分散・積み立て」という資産運用の基本を実践することの重要性です。短期的な値動きに一喜一憂せず、長期的な視点で運用を続けることが成功の鍵と言えるでしょう。
失敗事例:リスク許容度との不一致
一方、リスクに対して消極的だったり、商品選択を誤ったりした場合は、期待通りの運用成果が得られない場合もあります。「うまくいかなかった」理由としては「リスクに対して消極的だった」(30%)「商品選択が悪かった」(26%)という回答が多く見られました。
また、運用内容を頻繁に変更することも必ずしも良い結果をもたらさないようです。調査では、「年1回未満」や「年1~2回」程度の変更を行う人の方が、「変更したことがない」人や「年6回以上」頻繁に変更する人よりも「運用がうまくいっている」と回答する割合が高かったことが報告されています。
専門家の見解
専門家は確定拠出年金について、どんなものにも良い面と悪い面があるという性質のものであり、デメリットもあればメリットもあると指摘しています。
企業型確定拠出年金の専門家は、「企業によっては、入社時に企業型DCへ加入するかどうかを選べるところがあります。お勤めの企業に企業型DCがあるのであれば加入した方がよいです」とアドバイスしています。
さらに、「もし加入しない選択をした場合、掛金が給与や賞与に上乗せされるため一見すると得をしたように見えますが、上乗せされた分に対しては税金や社会保険料がかかります。それを考えると、企業型DCへ加入したほうが老後の資産形成にとっては有利」だと説明しています。
まとめ:確定拠出年金は本当に「やばい」のか?
確定拠出年金に対して「やばい」「やめたほうがいい」という声があるのは事実ですが、それは主に以下の理由からのようです。
- 60歳まで原則引き出せない流動性の低さ
- 運用リスクによる元本割れの可能性
- 手数料の存在
- 運用商品選択の難しさ
しかし、長期的な視点で見れば、税制優遇という大きな利点があり、老後資金の形成には効果的な制度であることは間違いありません。実際に、運用状況について「うまくいっている」と回答した人が約4割に上るという調査結果もあります。
結局のところ、確定拠出年金が自分に合っているかどうかは、個人の状況(年齢、収入の安定性、資金の余裕など)とリスク許容度によって大きく異なります。長期的な視点で老後資金を形成したい方、特に税制優遇のメリットを活かせる方にとっては、確定拠出年金は非常におすすめの選択肢と言えるでしょう。
一方で、流動性を重視する方や、投資に不慣れな方は、他の資産形成手段と併用するなど、バランスの取れた資産形成計画を立てることが重要です。「デメリットと対策を事前に知っておくことで、確定拠出年金を安全にオトクに活用する方法が見えてくる」との指摘もあるように、確定拠出年金の特性をよく理解し、自分の状況に合わせて活用することが大切です。
最終的には、「どんなものにも良い面と悪い面がある」という原則を忘れず、自分のライフプランに合った選択をすることが何よりも重要なのではないでしょうか。確定拠出年金は決して「やばい」制度ではなく、正しく理解し活用すれば、老後の資産形成において強力な味方になり得る制度だと言えるでしょう。


