「リカーリング収益」って何? できるだけわかりやすく解説
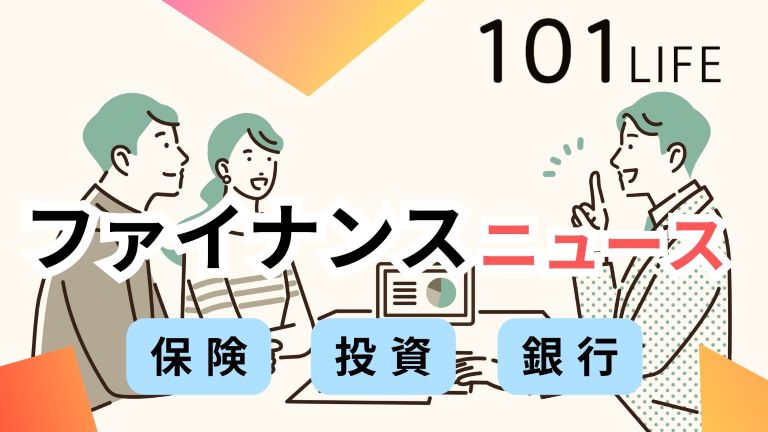
「リカーリング収益」って何? 従来のビジネスモデルとの違いやサブスクリプションとの違いなどをわかりやすく解説
経済のデジタル化と共に、ビジネスの収益モデルも大きく変化しています。かつては商品を一度販売して終わりというモデルが主流でしたが、現在では継続的に収益を得る「リカーリング収益」モデルが注目を集めています。2025年に入り、多くの企業がこのリカーリング収益の増加を重要な経営指標として公表するようになりました。
リカーリング収益とは、顧客との継続的な関係性から生まれる定期的な収入のことです。サブスクリプションサービスの月額料金や、プリンターのインクカートリッジのような消耗品販売など、様々な形で私たちの生活に浸透しています。この「売り切り」ではなく「継続的な関係」を重視するビジネスモデルは、企業にとって安定した収益基盤となり、顧客にとっては利便性の向上につながります。
この記事では「リカーリング収益」の概念から具体例、最新の市場動向まで、ビジネスパーソンが知っておくべき情報を徹底解説します。
この記事でわかること
- リカーリング収益の基本概念: 「繰り返される収益」の意味と従来のビジネスモデルとの違いについて理解できます。
- サブスクリプションとの違い: よく混同されるサブスクリプションとリカーリングの明確な違いが理解できます。
- 具体的なビジネスモデル例: 様々な業界でのリカーリングビジネスの実践例と成功事例を知ることができます。
- 企業と顧客双方のメリット: リカーリングモデルが注目される理由と、それがもたらす価値について理解できます。
- 最新の市場動向: 2025年現在のリカーリングビジネスの市場規模や成長している企業の事例を知ることができます。
リカーリング収益とは?
「繰り返される収益」の基本概念
リカーリング(Recurring)とは英語で「再発する」「繰り返される」という意味を持つ言葉です。ビジネスにおけるリカーリング収益(Recurring Revenue)とは、顧客との継続的な契約関係に基づいて、定期的・反復的に発生する収益のことを指します。
従来のビジネスモデルでは、商品やサービスを一度販売したら取引は完了し、次の収益を得るためには新たな顧客を獲得するか、既存顧客に再度購入してもらう必要がありました。これに対してリカーリングビジネスでは、一度獲得した顧客から継続的に収益を得る仕組みを構築します。
例えば、プリンターメーカーのキヤノンは、インクジェットプリンターを原価以下の低価格で提供し、専用インクを高額で販売するビジネスモデルを確立しました。本体ではなく消耗品によって継続的に安定した利益を生み出しているのです。
【用語解説】ARR(Annual Recurring Revenue) ARRとは「年間経常収益」を意味し、サービス導入時のみ発生する初期費用や一時的な売上を除いた、毎年継続して獲得する売上を示す指標です。主にSaaSビジネスの成長性を測るための重要な指標として活用されています。
「所有から利用へ」というトレンド
現代社会では「所有から利用へ」という価値観の変化が進んでいます。特に豊かな時代に生まれた若い世代を中心に、物欲や所有欲は薄れつつあります。
このような背景から、商品自体を売るのではなく、その商品やサービスを利用する権利や体験価値を提供するビジネスモデルが主流になりつつあります。カーシェアリングやサイクルシェアなどのシェアリングエコノミーもリカーリングビジネスの一形態と言えるでしょう。
また、デジタルコンテンツの普及により、新聞社や出版社のように認証システムを利用してデジタルコンテンツを月額料金で提供するモデルも増えています。こうしたコンテンツの課金は、継続課金だけでなく都度課金も含まれており、一つの契約で大きな利益を生み出す可能性を秘めています。
リカーリングとサブスクリプションの違い
定額制と従量制の違い
リカーリングビジネスとサブスクリプションビジネスは、どちらも継続的な収益を得るモデルですが、その課金方式に大きな違いがあります。
サブスクリプションビジネスは、利用期間中は固定料金を決められた頻度で支払うことにより、提供されているサービスが利用し放題になるビジネスモデルです。動画配信サービスのNetflixや音楽配信サービスのSpotifyが代表例で、利用量に関わらず一定の料金がかかります。サービスをまったく利用しなくても、契約している限り所定の料金を支払う必要があります。
一方、リカーリングビジネスは基本的に使用状況に応じた従量課金のビジネスモデルです。電気・水道・ガスなどの公共料金や、データ通信量に応じて料金が変動するスマートフォンの従量制プランなどが典型例です。基本料金に加えて、使用した分量に応じて請求金額が変化します。
ただし、広義にはサブスクリプションもリカーリング収益の一種とみなされることもあり、明確な定義は確立されていない部分もあります。
ストックビジネスの中での位置づけ
ビジネスモデルは大きく「フロー型」と「ストック型」に分類できます。「フロー型」は商品の購入により取引が終了する都度取引のことで、一度購入した顧客が次回も購入する保証はなく、購入時期も予測できません。
「ストック型」は契約を締結している期間内は継続的に収入を得られるビジネスモデルです。リカーリングとサブスクリプションはどちらも「ストック型」ビジネスに含まれます。
【用語解説】ストックビジネス ストックビジネス(またはストック型ビジネス)とは、顧客との契約によって長期的にサービスを提供することで継続的で安定した収益を確保するビジネスモデルを指します。定額制のサブスクリプションや従量制のリカーリングもこのストックビジネスに含まれます。
リカーリングビジネスの具体例
ハードウェア+消耗品型
ハードウェア+消耗品型のリカーリングビジネスは、初期投資としての本体(ハードウェア)を販売し、その後継続的に必要となる消耗品やサービスから収益を得るモデルです。
キヤノンのインクジェットプリンターは、この代表例です。キヤノンはインクジェットプリンターを原価以下の低価格で提供し、専用インクの高額販売でリカーリング収益を実現しています。趣味や写真プリント、在宅勤務をターゲットに、消耗品と保守サービスを継続的に提供することで、顧客の離脱を防ぎながら安定した利益を生み出しています。
また、ゲーム業界では本体(ハードウェア)とゲームソフト(コンテンツ)の組み合わせもリカーリングの一例です。ゲーム機を一度購入した顧客は、その後継続的にゲームソフトを購入し続けることで、メーカーに継続的な収益をもたらします。
プラットフォーム型
プラットフォーム型のリカーリングビジネスは、基盤となるプラットフォームを提供し、そこでのトランザクションや利用から継続的に収益を得るモデルです。
AppleのApp Storeは世界中の開発者がアプリを公開するプラットフォームです。開発者は年間登録料とともに、有料アプリやアプリ内課金から得た売上の15~30%を決済手数料としてAppleに支払います。iPhoneの普及に伴いユーザーが増加することで、App Storeからの収益も増大しています。
このモデルでは、プラットフォーム提供者は直接的なコンテンツ制作よりも、魅力的なエコシステムを構築することに注力します。利用者とコンテンツ提供者の両方を惹きつけることで、継続的な収益の流れを確保しています。
サービス型
サービス型のリカーリングビジネスは、製品ではなくサービスそのものを継続的に提供することで収益を得るモデルです。
KIRINの「ホームタップ」は、オーダーメイドのビールを届けるリカーリングサービスです。最低契約期間(12ヶ月)の継続利用を条件に、専用開発のビールサーバーを無料でレンタルでき、ビールは自由に選べるシステムになっています。2021年3月にサービスを開始し、同年8月には10万人の会員を獲得する成功を収めました。
SONYの「PlayStation Plus」は、会員制のリカーリングビジネスです。3つのプランを用意し、加入者限定のサービス割引やボーナスコンテンツなどを提供しています。SONYは2020年の連結決算で純利益を増やしており、その背景には全売上の4〜5割を占めるリカーリングの売上高があるとされています。
Amazonの「Amazonプライム」は、年会費または月会費を支払うことで利用できるプログラムです。配送料無料や会員限定セールの開催、「Prime Video」で会員特典対象動画が見放題になるなど、多くの特典をつけて会員数を増やしています。特典の多い会員制での集客によりECサイトの利用も促進されており、継続的収益と一時的な収益の好循環を生み出している成功事例です。
リカーリングビジネスのメリット
安定した収益基盤の構築
リカーリングビジネスの最大のメリットは「利用者がいる限り収益が続く」ことです。これまでは物やサービスが売れなければ収益が出ませんでしたが、リカーリングでは一度の契約で長期間収益を得ることができます。
例えば、コンタクトレンズの場合、高価なコンタクトレンズを1回購入してもらうより、毎月定期的に新しいコンタクトレンズを購入してもらうことで、継続的な収益が見込めます。
このモデルは、一旦軌道に乗ると長期的な視野で収益を見込むことができます。スーパーで食品を一度だけ購入した場合はそこで取引が終了しますが、自宅やオフィスへの定期配送サービスを利用する場合、配送のたびに購入分の売上が定期的に発生するようになります。
また、月額や年額のリカーリング料金を通じて安定したキャッシュフローを確保できることも大きな特徴です。財務の安定性を維持しやすく、突発的な売上変動が少ないため、安心して新しいプロジェクトへの投資や研究開発に資金を投入できます。
顧客との長期的な関係構築
リカーリングビジネスでは「より顧客ファーストなサービス」を展開し、顧客をつかんで離さないことでどんどん利益を上げていきます。例えば、コンタクトレンズを定期購入している場合、しかもそれが「定期便」で毎月自宅に届くのであれば、わざわざ新しいお店を苦労して探す必要がなくなります。
このようにリカーリングビジネスでは、顧客が自社のサービスを継続利用することが前提になるため、他社へのお客さまの流出が防げるというメリットもあります。すでに製品本体やプラットフォームを利用しているため、他社サービスへ乗り換えることが一定のハードルとなります。
結果として顧客ファーストの対応に徹し、顧客満足度の向上に専念しやすくなることも重要なメリットの一つです。顧客にとっては、より質の高いサービスを体験できる可能性が高まります。
【用語解説】顧客ロイヤリティ 顧客ロイヤリティとは、顧客が特定のブランドやサービスに対して持つ忠誠心や愛着のことです。ロイヤリティの高い顧客は、継続的に同じブランドを選び、価格が多少高くても他社製品に乗り換えにくい傾向があります。リカーリングビジネスは顧客ロイヤリティの構築・強化に有効なビジネスモデルとされています。
データ活用によるマーケティング精度の向上
リカーリングビジネスは、固定客との継続的な関係性を築けることから、マーケティング活動に必要とされるデータを収集しやすいというメリットもあります。一過性の断片的なデータではなく、顧客の行動や視聴データなど、顧客ニーズを正確に把握できるデータを継続的に収集できます。
継続的な顧客関係を通じて購買行動や利用履歴などのデータを容易に収集でき、それらを分析することで、顧客のニーズや嗜好を深く理解し、パーソナライズされたサービスや商品を提供できます。
例えば、音楽ストリーミングサービスのSpotifyは、ユーザーの聴取履歴に基づいて好みのプレイリストを自動作成し、顧客満足度を高めて集客力を強化しています。
さらに、収集したデータからパーソナライズされたサービスを提供することも可能です。収集したデータの分析結果を通じて、既存の顧客にオプションの追加や関連サービスの提案も可能になり、アップセルやクロスセルによって顧客単価の向上を図ることで、さらなる売上アップを目指せます。
事業計画の立てやすさ
リカーリングビジネスは、顧客を一定数獲得することで顧客の購買や視聴データを活用できるため、販売戦略を定めやすいというメリットがあります。
月額や年額のサブスクリプション料金を通じて安定したキャッシュフローを確保できるため、財務の安定性を維持しやすく、突発的な売上変動が少ないという特徴があります。そのため、安心して新しいプロジェクトへの投資や研究開発に資金を投入できます。
また、予測可能な収益モデルであるため、企業は将来の収益を見込んだ事業計画を立てやすくなります。収益の見通しが立てやすいため、投資判断も容易になるのです。
リカーリングビジネスの最新動向
企業のリカーリング収益事例
2025年現在、多くの企業がリカーリング収益の重要性を認識し、積極的な取り組みを行っています。ここでは最新の企業事例をいくつか紹介します。
unerry(ユナリー)は、2025年6月期第2四半期(2024年7月-12月)の決算において、売上高が前年同期比51.0%増の17.33億円、営業利益が1.03億円(前年同期は0.34億円の損失)となり、黒字転換を果たしました。特筆すべきは、リカーリング顧客売上高が15.98億円に達し、リカーリング顧客売上高比率が92.2%と非常に高い水準になっていることです。
ソラコムは、2025年3月期第3四半期の決算において、リカーリング収益が前年同期比21.2%増の47億8,000万円と2桁増収を達成しました。同社のグローバル売上は全体の4割を超え、好調な成長を続けています。さらに、通期でのリカーリング収益は前期比21.7%増と高い成長率を維持する見込みです。
ROBOT PAYMENTは、2025年2月度のプロダクト別月次リカーリング収益を開示しています。同社はリカーリング収益が積み上がるビジネスモデルであることを特徴としており、重要指標として位置づけています。
これらの事例からも、リカーリング収益が企業の安定的な成長と収益基盤の強化に大きく寄与していることがわかります。
リカーリングビジネスの成長戦略
企業がリカーリング収益を伸ばすために採用している主な成長戦略は以下の通りです。
クロスセルとアップセル 既存顧客に対して関連サービスや上位プランを提案することで、1人当たりの収益(ARPU)を向上させる戦略です。例えば、Amazonプライムでは、配送サービスだけでなく、動画配信、音楽配信、電子書籍などの様々なサービスを組み合わせることで、会員あたりの収益を最大化しています。
パートナーシップの活用 他業界の企業と提携し、サービス範囲を拡大する戦略です。例えば、ソラコムは丸紅と海外市場におけるIoT分野での協業に向けた合意書を締結するなど、パートナーシップを通じて事業拡大を図っています。
グローバル展開 国内市場だけでなく、海外市場にもサービスを展開することで収益基盤を拡大する戦略です。ソラコムの事例では、グローバル売上が全体の4割を超え、成長を続けています。世界的な調査会社によるChampionへの選出など、グローバルでの認知度も向上しています。
テクノロジーの活用 特に生成AIなどの最新テクノロジーを活用し、サービスの付加価値を高める戦略も注目されています。ソラコムは「生成AI×IoT(AI of Things)」を成長戦略に位置付け、「SORACOM Flux」などの新サービスでAIを活用したソリューションを提供しています。
リカーリングビジネスを導入する際のポイント
リカーリング収益モデルを導入する際には、以下の3つを特に意識することが重要です。
顧客中心の設計 顧客満足度を高めるため、ユーザーフレンドリーな仕組みを設けることが不可欠です。例えば、簡単な解約プロセスや柔軟な契約変更オプションを提供することで、顧客のストレスを軽減します。また、カスタマイズ性の高いサービスも魅力的です。
データ活用の強化 顧客の利用データを分析し、解約リスクを予測する仕組みを整備します。機械学習を活用して解約兆候を把握し、リテンション(継続率)向上に繋げるアプローチが有効です。
マーケティングの最適化 定期的なコミュニケーションで顧客との関係を維持します。例えば、メールマーケティングやキャンペーンの通知を活用して、サービスの価値を再認識させる取り組みが重要です。
また、リカーリングビジネスを導入する際の注意点としては、顧客維持の難しさ、価格競争への対応、初期コストの高さなどがあります。これらの課題に対応するためには、綿密な計画とデータ分析に基づいた改善が求められます。
リカーリングビジネスの課題
顧客維持の難しさ
リカーリングビジネスの大きな課題の一つは、顧客の継続利用をいかに確保するかという点です。定期的な支払いに対する価値を顧客が感じなければ、解約が発生する可能性があります。
特に競合サービスが増加する中で、顧客の継続的な支持を得るためには、常に価値を提供し続ける必要があります。例えば、サブスクリプション型の動画配信サービスでは、魅力的な新コンテンツを定期的に追加することで顧客の継続利用を促しています。
また、顧客のライフスタイルや状況の変化にも柔軟に対応できるサービス設計が重要です。例えば、一時的な休止オプションや、ニーズの変化に応じたプラン変更の容易さなど、顧客の状況に合わせた柔軟性が求められます。
競争の激化と差別化の難しさ
リカーリングビジネスモデルの有効性が認識されるにつれ、多くの企業が参入し競争が激化しています。同業他社のサービスとの差別化が難しい場合、価格競争に陥るリスクがあります。
差別化のポイントとしては、独自のコンテンツやサービス、使いやすいインターフェース、優れたカスタマーサポートなどが挙げられます。例えば、SONYの「PlayStation Plus」は独自のゲームタイトルやPS5向けのサービスなど、他社には真似できない価値を提供することで差別化を図っています。
また、単一のサービスだけでなく、複数のサービスを組み合わせたエコシステムを構築することも差別化戦略として有効です。Amazonは「Amazonプライム」を通じて、配送、映像、音楽、電子書籍など、多様なサービスを一つの会員資格で提供することで、顧客の離脱を防いでいます。
初期投資とシステム構築の課題
リカーリングビジネスを展開するためには、システム構築や顧客基盤拡大のための初期投資が必要です。特に決済システムや顧客管理システム、データ分析基盤などのIT投資は欠かせません。
また、継続的なシステムの改善や拡張も必要となります。顧客数の増加や機能追加に伴うシステムの拡張性(スケーラビリティ)も考慮した設計が重要です。
例えば、ROBOT PAYMENTのような決済サービス企業は、リカーリング収益を重要指標として位置づけ、継続的なシステム構築と改善に投資しています。こうした投資が結果的に安定したリカーリング収益を生み出す基盤となっています。
まとめ:リカーリング収益の今後
ビジネスモデル転換の重要性
経済環境や消費者の価値観が変化する中、従来の「売り切り型」から「継続収益型」へのビジネスモデル転換は、多くの企業にとって重要な課題となっています。特に「所有から利用へ」という価値観のシフトに対応するため、リカーリング収益モデルの導入は戦略的な意義を持ちます。
unerryやソラコム、ROBOT PAYMENTなどの企業事例からも明らかなように、リカーリング収益の比率が高い企業ほど、安定した財務基盤を構築し、持続的な成長を実現しています。今後も多くの企業が、一時的な売上に依存するビジネスモデルから、継続的な収益を生み出すリカーリングモデルへの転換を進めていくことが予想されます。
デジタル技術の進化との関係
リカーリングビジネスの拡大には、デジタル技術の進化が大きく貢献しています。クラウドサービスの普及、サブスクリプション管理プラットフォームの発展、データ分析技術の向上などにより、リカーリングビジネスの運営が容易になっています。
特に2025年現在では、生成AIなどの先端技術を活用したリカーリングサービスが注目を集めています。ソラコムが展開する「生成AI×IoT(AI of Things)」の取り組みは、世界的な調査会社であるFrost & Sullivanからも高い評価を受けており、今後の成長分野として期待されています。
消費者の価値観変化への対応
最後に、リカーリングビジネスの成功は、変化する消費者の価値観への適切な対応にかかっています。特にZ世代やミレニアル世代を中心に、「所有よりも体験」を重視する傾向が強まっています。
このような価値観の変化に対応するためには、単なるモノの提供ではなく、顧客体験全体の設計が重要になります。例えば、KIRINの「ホームタップ」は、単にビールを提供するだけでなく、自宅で専用サーバーから注ぎたてのビールを楽しむという体験を提供することで、10万人以上の会員を獲得する成功を収めました。
今後も消費者の価値観や行動様式は変化し続けるでしょう。こうした変化に柔軟に対応し、顧客にとって価値のある体験を継続的に提供できる企業が、リカーリングビジネスにおいて成功を収めることになるでしょう。
リカーリング収益の構築は一朝一夕にできるものではありません。しかし、顧客との長期的な関係構築を通じて安定した収益基盤を獲得することで、ビジネスの持続可能性を高めることができます。今後ますます多くの企業がリカーリングモデルへの転換を進め、より顧客中心のビジネス展開を図っていくことでしょう。

