東証グロース市場の上場維持基準厳格化が”やばい”といわれているのはなぜ?
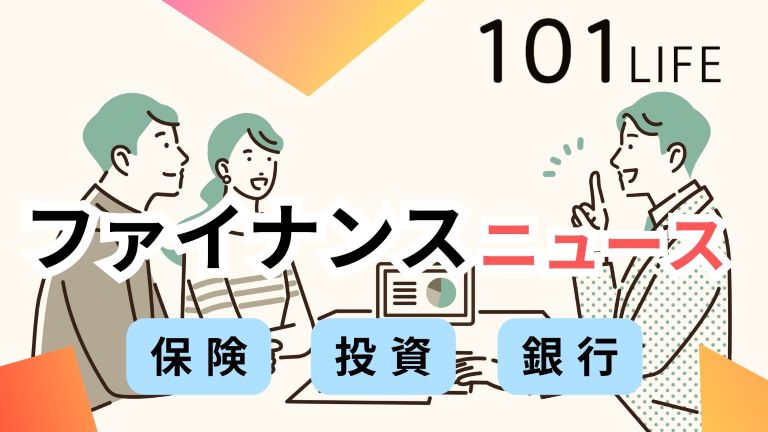
東証グロース市場の上場維持基準が厳格化されヤバイと話題に、口コミや評判で言われている原因について掘り下げて解説します
東証グロース市場の上場維持基準厳格化についてネットの口コミや評判から真相を掘り下げてみました。「やばい」という噂が広がる一方で、実際にはどのような変化が起きているのか、また企業成長促進という本来の目的から見れば「やばくない」側面もあるのではないかと考え、様々な観点から検証していきます。
東証グロース市場の概要と現状
東京証券取引所は2022年4月4日に市場区分を「プライム市場」、「スタンダード市場」、「グロース市場」の3つの新しい市場区分へと再編しました。この再編から約3年が経過し、特にグロース市場については様々な課題が表面化しているようです。
グロース市場は、高い成長可能性が期待できる新興企業向けのマーケットとして位置づけられています。しかし、実態は必ずしも成長とはほど遠い状況にあるようです。日経ビジネスの報道によれば、新規上場時から2023年末までの時価総額の成長率(中央値)は1.03倍にとどまり、全体の49%の企業が新規上場時の時価総額を下回っていました。また、時価総額の中央値は60億円と機関投資家の投資対象となる下限の100億~200億円を下回り、全体の31%は上場維持基準の40億円をも下回っている状況だと報告されています。
上場維持基準の現状と厳格化の動き
現行の上場維持基準
現在のグロース市場における上場維持基準には以下のような項目があります。
- 株主数:150人以上
- 流通株式に関する基準
- 月平均売買高:10単位以上
- 時価総額:40億円以上(上場10年経過後から適用)
- 純資産の額が正であること
特に注目すべきは時価総額の基準です。現行では上場後10年経過した企業に対して40億円以上という基準が適用されます。
厳格化の動き
東京証券取引所は、グロース市場の上場維持基準の見直しを検討しています。具体的には、以下のような変更が議論されているようです。
- 上場維持基準を「10年よりも短く、2段階程度で区切る」案の検討
- 「上場後5年50億円以上、10年100億円以上」といった基準の水準引き上げが議論されている
- 上場維持基準に適合しない場合、①上場廃止または②他社との統合の選択を迫られる可能性
これらの動きに関して、2023年1月30日に経過措置の終了時期が公表されました。2025年3月1日以後に到来する基準日から本来の上場維持基準が適用されることになっています。
「やばい」と噂されている理由
ネット上で東証グロース市場の上場維持基準厳格化が「やばい」と噂されている理由にはいくつかの要因があるようです。
1. 多くの企業が上場維持基準を満たせない可能性
現状でも全体の31%の企業が上場維持基準の40億円を下回っているという報告があります。基準がさらに厳しくなれば、より多くの企業が上場維持基準を満たせなくなる可能性があるのではないかと懸念されているようです。
2. 時価総額の基準引き上げの可能性
現在議論されている「上場後5年50億円以上、10年100億円以上」という基準は、現行の40億円から大幅な引き上げとなります。このハードルの高さが「やばい」と評価される一因になっていると考えられます。
3. 適合期間の短縮
現在は上場後10年経過してから時価総額の基準が適用されますが、この期間が短縮される可能性があります。より早い段階から厳しい基準に適合する必要が生じるため、企業の成長戦略にも大きな影響を与えると懸念されているようです。
4. 上場廃止のリスク増大
上場維持基準に適合しない状態となった場合、改善期間を経て、それでも基準を満たせない場合は上場廃止となります。基準厳格化により、このリスクが高まると危惧されているようです。
上場維持基準の厳格化が企業に与える具体的な影響について
東証グロース市場の上場維持基準の厳格化は、企業に以下のような具体的な影響を与えると考えられます。
1. 上場廃止リスクの増加
新たな基準では、上場後5年で時価総額100億円以上が求められる可能性があり、これまでの40億円基準から大幅に引き上げられます。この変更により、特に中小規模企業や成長が停滞している企業は基準を満たせず、上場廃止のリスクが高まるとされています。
影響例
- 現在、グロース市場の約3割の企業が既存の時価総額基準(40億円)を下回っており、新基準導入後はさらに多くの企業が適合できなくなる可能性があります。
- 上場廃止となる場合、投資家からの信頼低下や資金調達能力の制限など、企業経営に深刻な影響を及ぼすことが懸念されています。
2. 経営戦略の見直し
上場維持基準を満たすために、企業は経営戦略や事業計画を再構築する必要があります。特に以下の点が重要視されています。
成長戦略の強化
- 基準達成には売上や利益拡大が不可欠であり、これまで以上に積極的な成長戦略が求められます。
- 例えば、新規市場への進出や新製品開発など、収益向上を目的とした投資を進める必要があります。
資本政策と株式流通比率の見直し
- 創業者株式の一部売却などを通じて流通株式比率を高める必要があります。
- 自己株式買い入れや増資による資本政策も検討されるでしょう。
3. コーポレートガバナンス強化
新たな基準では、企業価値向上や透明性向上が求められるため、コーポレートガバナンス体制の強化が不可欠です。
具体的な取り組み
- 投資家への情報開示を充実させるため、英文開示やIR活動を強化する必要があります。
- 株主還元策として配当政策や株主優待制度の見直しも検討されるでしょう。
4. M&Aや統合戦略の加速
基準未達成の場合、他社との統合やM&Aによって規模拡大を図る動きが加速すると考えられます。これにより、市場全体で業界再編が進む可能性があります。
5. 投資家からの評価変化
基準厳格化により、市場全体で質の高い企業が選別されるため、投資家から見た魅力的な市場環境が形成される可能性があります。一方で、不適合リスクを抱える企業への投資は慎重になると予想されます。
まとめ:ポジティブな側面も存在
厳格化によって一部企業には厳しい影響があるものの、市場全体としては以下の利点も期待されます。
- 市場の質向上: 成長力ある企業のみが残り、市場全体の信頼性が高まります。
- 投資機会増加: 成長意欲を持つ企業への注目度が高まり、投資家にとって魅力的な市場となる可能性があります。
これらを踏まえると、新基準は短期的には課題となり得ますが、中長期的には市場活性化につながる「おすすめ」できる変革とも言えるでしょう。
誤解されている可能性のある点
一方で、「やばい」という評価には誤解も含まれている可能性があります。以下に誤解されやすい点を挙げてみます。
1. すべての企業がすぐに影響を受けるわけではない
経過措置の終了時期は2025年3月1日以後から適用されるため、すぐに全企業に影響が出るわけではありません。また、新たな基準案についてもまだ検討段階であり、最終決定ではないようです。
2. 改善のための猶予期間がある
上場維持基準に適合しない状態となった場合でも、すぐに上場廃止となるわけではなく、改善期間が設けられています。この期間内に基準を満たすための対策を講じることができます。
3. 成長促進という本来の目的が見落とされがち
市場区分再編の目的には①市場区分の明確化、②企業価値向上の動機付けが掲げられていました。上場維持基準の厳格化は、企業に成長を促す意図があるとも考えられます。
上場維持基準厳格化の肯定的な側面
「やばい」という噂が広がる一方で、上場維持基準厳格化には肯定的な側面もあるようです。
1. 市場の質の向上
グロース株のメリットとして、バリュー株に比べて値上がり益(キャピタルゲイン)が大きいことが挙げられます。基準厳格化により市場に残る企業の質が向上すれば、投資家にとってより魅力的な投資先となる可能性があります。
2. 成長への動機付け強化
上場企業役員を対象とした調査では、東証再編について73.5%とおよそ4人に3人がポジティブ(ポジティブである、どちらかと言えばポジティブである)と考えていることが分かっています。上場維持基準の厳格化は企業の成長意欲を高める可能性があります。
3. 企業価値向上への積極的な取り組みを促進
上場維持基準を満たすために、企業はより積極的に企業価値向上に取り組む必要があります。これにより、長期的には株主還元や事業拡大など、市場全体の活性化につながる可能性があるのではないでしょうか。
4. 戦略的M&Aの促進
基準厳格化により、企業間の統合やM&Aが促進される可能性があります。これにより、業界再編が進み、より競争力のある企業グループが形成されることが期待できるかもしれません。
企業と投資家への影響
企業への影響と対応策
上場維持基準の厳格化は、特に時価総額が小さい企業に大きな影響を与える可能性があります。対応策としては以下のようなものが考えられます。
- 成長戦略の再構築: より積極的な成長戦略を策定し、実行することが求められるでしょう。
- IR活動の強化: 投資家とのコミュニケーションを強化し、企業価値をより適切に評価してもらうための取り組みが重要になるでしょう。
- 資本政策の見直し: 公募増資などを活用した成長投資を検討する必要があるかもしれません。現状では上場後に公募増資を実施した企業はわずか14%にとどまっています。
- M&Aの検討: 自社だけでの成長が難しい場合は、M&Aによる規模拡大や事業シナジーの創出を検討する必要があるでしょう。
投資家への影響と投資戦略
投資家にとっては、以下のような影響と対応が考えられます。
- 銘柄選定の重要性が増す: 上場維持基準を満たせる成長力のある企業を見極めることがより重要になるでしょう。
- 長期投資視点の重要性: グロース市場は個人投資家が約6割を占めており、短期的な視点での投資が多いと言われています。しかし、企業の本質的な成長を見極める長期投資の視点がより重要になるかもしれません。
- リスク分散の必要性: 上場廃止リスクが高まる可能性があるため、ポートフォリオのリスク分散がより重要になるでしょう。
グロース市場の今後と投資家へのアドバイス
グロース市場の本来の趣旨は「高い成長可能性が期待できる新興企業向けのマーケット」です。上場維持基準の厳格化は、この趣旨に沿った市場へと変革するための取り組みとも言えるでしょう。
投資家にとっては、以下のような点が「おすすめ」できるかもしれません:
- 企業の成長ストーリーを重視: 単に時価総額だけでなく、企業の成長ストーリーや事業モデルの持続可能性を見極めることがおすすめです。
- 情報収集の徹底: 上場維持基準の動向や企業の対応策について、常に最新情報を収集することが重要でしょう。
- 長期的な視点での投資: グロース株の「利点」は長期的な成長によるリターンにあります。短期的な値動きに一喜一憂するのではなく、長期的な視点で投資することがおすすめです。
まとめ:東証グロース市場の上場維持基準厳格化は「やばくない」と考える理由
ネット上では「やばい」と噂されている東証グロース市場の上場維持基準厳格化ですが、以下の理由から「やばくない」と考えることもできるのではないでしょうか。
- 本来のグロース市場の趣旨に回帰: 成長企業のための市場という本来の趣旨に沿った変革であると言えるでしょう。
- 企業の成長促進: 上場維持基準の厳格化は、企業に対して成長を促す良いプレッシャーとなる可能性があります。
- 投資家保護の側面: 成長性の低い企業が市場から退出することで、投資家が本当の成長企業に投資できる環境が整うかもしれません。
- 経済全体の活性化: 企業の成長競争が促進されることで、日本経済全体の活性化につながる可能性もあるでしょう。
- 企業価値向上の取り組み強化: 上場企業役員の多くが東証再編についてポジティブに評価しているように、企業価値向上の取り組みが強化される可能性があります。
東証グロース市場の上場維持基準厳格化は、短期的には「やばい」と感じる企業や投資家もいるかもしれませんが、長期的な視点では市場の健全化と企業の成長促進につながる重要な取り組みであると言えるのではないでしょうか。企業も投資家も、この変化を前向きに捉え、それぞれの立場で最適な対応策を検討していくことが重要だと思われます。
最後に、上場維持基準厳格化の「利点」として、真に成長できる企業と停滞している企業の選別が進み、グロース市場本来の活力が復活する可能性があることを強調しておきたいと思います。投資家にとっては、より成長性の高い企業への投資機会が増える可能性もあり、長期的には好ましい変化と捉えることもできるでしょう。


