PERとPBRについて”高い”、”低い”どっちがいいか、2つの指標の関係性をわかりやすく解説
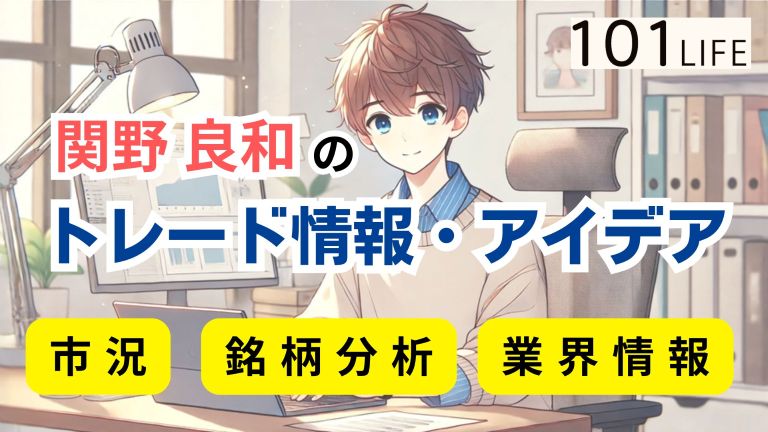
PERとPBRの関係性とどちらが重要か、投資判断における活用方法をわかりやすく解説
株式投資において、企業の株価が割安か割高かを判断する際に用いられる代表的な指標としてPER(株価収益率)とPBR(株価純資産倍率)が存在します。本報告書では、両指標の定義や計算方法を明確にした上で、数値の高低が示す意味や相互関係を実例を交えて詳細に分析します。さらに、業種特性や企業の成長段階に応じた解釈の差異についても考察を加え、総合的な投資判断のフレームワークを構築します。
1. PERとPBRの基本定義と計算方法
1.1 PER(株価収益率)の構造分析
PERは「Price Earnings Ratio」の略称であり、株価が1株当たり純利益(EPS)の何倍まで買われているかを示す指標です。計算式は以下の通りです。
PER=株価÷1株当たり純利益(EPS)=時価総額÷純利益
例えば、株価1,000円の企業でEPSが100円の場合、PERは10倍となります。この数値は、現在の利益水準を維持すれば10年で投資元本が回収できることを意味しますが、実際には将来の利益成長期待が反映されます。
1.2 PBR(株価純資産倍率)の本質的理解
PBRは「Price Book-value Ratio」の略称で、株価が1株当たり純資産(BPS)の何倍まで評価されているかを表します。計算式は次のとおり:
PBR=株価÷1株当たり純資産(BPS)=時価総額÷純資産
具体例として、株価500円でBPSが1,000円の場合、PBRは0.5倍となり、理論上は企業を清算すると投資額の2倍が返還される計算になります。この「解散価値」を基準に割安性を判断する特徴を持ちます。
2. 指標の高低が示す市場心理と実務的意味
2.1 PERの数値解釈における双方向的視点
PERが高い場合(例:30倍以上)は、市場が将来の利益成長を強く期待している状態を示します。例えば、AI技術を開発中のベンチャー企業では、現時点の利益が少なくても技術革新への期待からPERが高騰する傾向があります。逆にPERが低い場合(例:10倍以下)は、現状の利益水準に対して株価が割安と判断されますが、成長期待の乏しさを反映している可能性もあります。
ただし、業種による基準値の差異が顕著で、半導体製造装置メーカーでは平均PERが20倍前後なのに対し、地域銀行では5倍前後と大きな開きがあります。このため、同業他社比較が不可欠です。
2.2 PBRの数値が語る企業の実像
PBRが1倍を下回る場合、純資産に対して株価が割安であることを示します。2020年のコロナショック時には日経平均のPBRが0.82倍まで低下し、多くの企業が資産価値を下回る評価を受けました。しかし、PBRの低さが必ずしも投資機会を意味するわけではなく、業績悪化が継続する「バリュートラップ」のリスクも存在します。
逆にPBRが3倍を超える場合、企業の無形資産(ブランド力・技術力)への評価が高いことを示します。例えば、東京エレクトロンでは半導体需要拡大を受けてPBRが4倍を超える水準で推移しています。
3. 両指標の相互関係とROEを介した接点
3.1 会計的関連性の数理的考察
PERとPBRは以下の関係式で結ばれています。
ROE=純利益÷自己資本=PER÷PBR
この式から、ROEが10%の企業でPERが15倍の場合、PBRは1.5倍となることが導かれます。高ROE企業ではPERとPBRが連動して上昇する傾向があり、キーエンスの事例(ROE20%超、PER40倍、PBR8倍)が典型例です。
3.2 指標の組み合わせによる投資戦略の分類
- 低PER・低PBR型:三菱UFJフィナンシャルグループ(2024年3月時点PER6.3倍、PBR0.6倍)のように、伝統的バリュー銘柄に多いパターン
- 高PER・高PBR型:ディスコ(PER35倍、PBR4.2倍)のような成長期待の強いハイテク企業
- 低PER・高PBR型:自社株買いを積極化したホンダ(PER9倍、PBR1.3倍)などの特殊ケース
この組み合わせ分析により、市場がどのような企業特性を評価しているかを推測可能です。
4. 業種特性と企業成長段階に応じた解釈の差異
4.1 業種別基準値の比較分析
- 製造業:設備投資が多く有形資産比率が高いためPBR1.0~1.5倍が標準
- ITサービス:無形資産への依存度が高くPBR2.0~5.0倍、PER30~50倍が一般的
- 金融業:自己資本規制の影響でPBR0.5~1.0倍、PER5~10倍に集中
例えば、みずほフィナンシャルグループはPBR0.7倍ながら、デジタル化投資による中長期成長期待からPER12倍と金融業平均を上回ります。
4.2 企業ライフサイクルに伴う指標変動の実例
- 創業期:ソフトバンクグループ(通信事業開始当初)のPER100倍超、PBR8倍
- 成長期:メルカリのPER負数(赤字続き)、PBR4倍(将来期待反映)
- 成熟期:花王のPER20倍、PBR2.5倍(安定収益評価)
- 衰退期:某地方百貨店のPER5倍、PBR0.3倍(再生計画待ち)
このように、企業の成長段階に応じて適正とされる数値水準が大きく変化します。
5. 総合的な投資判断における実践的活用方法
5.1 時系列比較と業界平均対比の重要性
キヤノンの事例では、2023年度のPER15倍(業界平均18倍)、PBR1.2倍(業界平均1.5倍)という数値から、相対的割安性が読み取れます。ただし、直近3年間のPER推移(18倍→15倍→14倍)を確認し、収益悪化に伴う数値低下かどうかの分析が必須です。
5.2 財務諸表とのクロスチェック手法
- PER分析時:純利益の質(経常利益比率・リスク管理費用)を損益計算書で確認
- PBR分析時:純資産の内訳(のれん・固定資産評価)を貸借対照表で精査
例えば、PBR0.8倍でも固定資産の70%が減価償却済み設備の場合、実質的な資産価値は低いと判断されます。
5.3 マクロ経済環境との連動性分析
金利上昇局面では、将来利益の現在価値が低下するためPERの圧迫要因となります。2024年の米国利上げ局面では、日経平均PERが16倍から14倍へ低下しました。逆に金融緩和期には、成長株のPER拡大が顕著になります。
6. 主要事例に基づくケーススタディ
6.1 トヨタ自動車の指標分析(2024年度)
- PER10倍(自動車業界平均12倍)
- PBR1.1倍(同1.3倍)
- EVシフトへの投資が収益を圧迫するも、バッテリー技術の競争力からPBRが業界平均を下回る水準で安定
6.2 任天堂の指標変遷(2017-2024年)
- 2017年(Switch発売前):PER25倍、PBR2.8倍
- 2020年(コロナ特需):PER35倍、PBR4.2倍
- 2024年(後継機懸念):PER18倍、PBR3.0倍
- 製品ライフサイクルが指標変動に与える影響が顕著に表れています
7. 伝統的理論と現代市場の乖離に関する考察
7.1 PBR1倍神話の崩壊
従来、PBR1倍は株価の底値とされましたが、2023年現在では東証プライム市場の37%の企業がPBR1倍未満です。これはグローバル競争の激化で、有形資産の評価が相対的に低下したためと考えられます。
7.2 無形資産時代の新たな評価基準
ソフトバンクグループの事例では、時価総額の60%以上がのれん等の無形資産で構成され、伝統的なPBR分析が機能しにくい状況です。このため、知的財産権の評価を含む新たな指標の開発が急務となっています。
8. 投資戦略別指標活用の実際
8.1 バリュー投資における応用
PBR0.8倍以下・PER10倍以下・配当利回り3%以上をスクリーニング条件に採用した場合、2024年3月時点で85銘柄が該当します。ただし、この中から業績改善の兆候がある三井E&Sホールディングス等を選別する必要があります。
8.2 グロース投資の新しい潮流
従来の高PER重視から、PBRとPERのバランスを見る手法が台頭しています。例えば、PER30倍・PBR5倍以下の条件で、成長持続性と過大評価リスクを両立させた銘柄選択が行われています。
9. 国際比較から見る日本市場の特性
9.1 米国市場との比較分析
S&P500平均PER25倍・PBR4.2倍に対し、日経平均はPER15倍・PBR1.3倍と大きな開きがあります。この差は、日本企業の利益率の低さ(ROE8% vs 米国15%)に起因すると分析されます。
9.2 新興国市場の特異な事例
インド市場では若年人口を背景に消費関連株のPERが40倍を超える例も珍しくなく、成長期待の強さが如実に表れています。ただし、PBRは2~3倍台と日本より高水準で、資産効率の高さを示唆します。
10. 環境変化に対応した新しい分析手法の模索
10.1 ESG要素を組み込んだ修正指標
脱炭素化投資の進展を受け、環境対策コストを加味した「グリーンPER」や再生可能エネルギー資産を評価する「サステナブルPBR」の開発が進んでいます。
10.2 AIを活用した予測モデルの可能性
過去10年のデータを学習させた機械学習モデルでは、PER・PBRに加えて売上高成長率を組み込むことで、6カ月後の株価方向を68%の精度で予測できたとの実験結果があります。
結論
PERとPBRの分析を通じて、株式評価における多面的アプローチの重要性が明らかになりました。PERが企業の収益力に基づく未来志向の指標であるのに対し、PBRは現在の資産価値を反映する保守的な指標という本質的差異を理解することが、適切な投資判断の第一歩です。重要なのは、両指標を単独で評価するのではなく、業種特性・成長段階・経営環境などを総合的に勘案することにあります。特に、ROEを介した相互関係の分析や、国際比較による相対評価の実施が、現代の複雑な市場環境では不可欠です。今後の研究課題として、無形資産の適切な評価方法の確立や、AIを活用した新しい分析手法の開発が挙げられます。投資家は伝統的指標の限界を認識しつつ、常に進化する市場の実態を捉える柔軟な思考が求められています。
PERが高く、PBRが低い会社は投資家からどのように評価されているのかわかりやすく解説
PERが高く、PBRが低い会社の評価についてネットの口コミや評判から真相を掘り下げてみました。投資判断において重要な指標であるPERとPBRの組み合わせが示す意味や、東京証券取引所(東証)に上場している企業の実例を交えながら、投資家がこれらの企業をどのように見ているのかを解説します。
PERとPBRの基本的な意味と違い
まず、PERとPBRという2つの投資指標について理解しておきましょう。
PER(株価収益率)とは
PERは「Price Earnings Ratio」の略で、日本語では「株価収益率」と呼ばれています。株価が1株当たりの純利益(EPS)の何倍になっているかを示す指標です。
PERの計算式は以下の通りです。
PER = 株価 ÷ 1株当たり純利益(EPS)
例えば、株価が10万円、1株当たりの純利益が1万円の場合、PERは10倍となります。
PERは株価の割高・割安を判断する際によく使われる指標で、一般的にPERが低いほど割安、高いほど割高と考えられています。しかし、業種や企業の成長段階によって適正なPERの水準は大きく異なるため、単純な比較は危険です。
PBR(株価純資産倍率)とは
一方、PBRは「Price Book-value Ratio」の略で、日本語では「株価純資産倍率」と呼ばれています。株価が1株当たりの純資産(BPS)の何倍になっているかを示す指標です。
PBRの計算式は以下の通りです。
PBR = 株価 ÷ 1株当たり純資産(BPS)
PBRは企業の実態にもとづいた評価を反映していると言われています。一般的に、PBRが1倍を下回ると、その企業の本来の価値よりも安く取引されているため割安と判断される傾向があります。
PERとPBRの違い
PERとPBRはいずれも株価の割高・割安を評価するための指標ですが、判断の基準が異なります。
- PERは収益力に着目した指標で、企業の稼ぐ力に対して株価がどれだけ評価されているかを示します
- PBRは純資産に着目した指標で、企業が持つ財産に対して株価がどれだけ評価されているかを示します
つまり、PERが高いということは投資家がその企業の将来の成長性や利益に期待していることを示し、PBRが低いということはその企業の資産価値が株価に十分反映されていないことを示すと言えるでしょう。
PERが高く、PBRが低い状態とは何を意味するのか
PERが高く、PBRが低いという一見矛盾するような状態は、投資家にとってどのような意味を持つのでしょうか。
ROEの低さを示唆している可能性
PER、PBR、ROE(自己資本利益率)の間には以下のような関係があると言われています。
PBR = ROE × PER
この式から考えると、PERが高くPBRが低い状態は、ROEが低いことを意味している可能性が高いのです。
ROEが低いということは、企業が株主資本を効率的に使って利益を生み出せていないことを示しています。投資家から見ると、「多くの資本を投入しているわりに、得られる利益が少ない」と評価される可能性があるのです。
経営効率の問題を抱えている可能性
PERが高いということは、現在の利益に対して株価が高いことを意味します。一方、PBRが低いということは、会社が持つ資産に対して株価が評価されていないことを示します。
このような状態にある企業は、多くの資産を持っているにもかかわらず、それを効率的に活用して利益を生み出せていない可能性があります。いわゆる「資本効率の悪い企業」として投資家から評価されている可能性が高いのです。
投資家からの評価と見られ方
PERが高くPBRが低い企業は、投資家からどのように見られているのでしょうか。
1. 資本効率の改善余地がある企業
多くの投資家は、PERが高くPBRが低い企業を「資本効率の改善余地がある企業」として見ている傾向があるようです。特に近年は、日本企業のROE向上が重視されており、経済産業省の伊藤レポートでは「グローバルな投資家との対話では、8%を上回るROEを最低ラインとし、より高い水準を目指すべき」との報告がなされました。
そのため、現状ではROEが低くても、資本政策の見直しや事業ポートフォリオの再構築などを通じて、資本効率を改善する余地がある企業は投資対象として注目されることもあるようです。
2. バリュートラップの可能性
一方で、PERが高くPBRが低い企業は「バリュートラップ(割安に見えるが実はそうではない罠)」の可能性も指摘されています。表面的には純資産に対して株価が割安に見えても、その資産を効率的に活用できていない、あるいは将来的にその資産価値が毀損する可能性があると市場が判断している場合があるためです。
「PBRが低くて『割安だ、バーゲンセールだ』と思って買ったのに業績悪化や利益成長の低さを嫌われてさらに株価が下がってしまった」というケースは珍しくないと言われています。
3. 業種特性の反映
PERやPBRの評価は業種によっても大きく異なります。IT業界などの成長産業ではPERが高くなる傾向があり、素材や部品メーカー、商社などの景気敏感株はPERが低くなる傾向があると言われています。
また、銀行業や不動産業など、資産を多く保有する業種ではPBRが低くなる傾向があります。これらの業種特性も考慮して評価する必要があるでしょう。
PERが高くPBRが低い具体的な状況例
PERが高くPBRが低い状態になる具体的な状況をいくつか見ていきましょう。
1. 景気敏感株が景気の底にある場合
景気に左右されやすい総合商社や自動車などの景気敏感株は、景気の底では業績が悪化し、純利益が減少します。そのため、PERは反比例して高くなります。
「この場合、PERだけを見ると割高のように見えてその企業には手を出しにくくなるが、実は株価は底の安値圏で買いのタイミングであることが多い」と株式アナリストの鈴木一之さんは話しています。
このような企業は、純資産(資産価値)はあるものの、一時的に利益が低迷しているため、PERが高くPBRが低いという状況になる可能性があります。
2. 構造改革中の企業
事業再編や構造改革を進めている企業も、PERが高くPBRが低くなることがあります。改革の過程で一時的に利益が減少し、PERが高くなる一方、保有資産は十分にあるためPBRは低いという状況です。
このような企業は、改革が成功すれば将来的に利益が回復してPERが低下する可能性があるため、投資機会と見る投資家もいるようです。
3. 資産を持っているが収益化できていない企業
多くの資産(土地、設備、子会社など)を保有しているものの、それらを十分に収益化できていない企業もPERが高くPBRが低くなりがちです。
このような企業は、資産の有効活用や不採算事業の整理などを通じて収益力を高めることができれば、企業価値の向上につながる可能性があります。株主からの圧力で経営改革が進めば、投資リターンが期待できると考える投資家もいるようです。
投資判断への応用
PERが高くPBRが低い企業への投資を検討する際には、以下のようなポイントを確認するとよいでしょう。
1. ROEの確認と将来性の評価
ROEが低い原因を分析することが重要です。ROEの低さの原因には、ROIC(投下資本利益率)の低さと資本構成の歪みの2つがあると言われています。
特に、経営者の判断次第で迅速に是正できる資本構成の歪み(過剰な現預金や不要な資産の保有など)が原因であれば、資本政策の見直しでROEが改善する可能性があります。
2. 業種特性の考慮
業種によってPERやPBRの適正水準は異なります。同業他社と比較して、相対的な位置づけを確認することが大切です。
例えば、auカブコム証券は「PERは業種により高い業種と低い業種があり、何倍なら割高、何倍なら割安という絶対的な基準はありません。そのため、PERを使っての企業比較は、同業種間で行うのが良いとされています」と説明しています。
3. 資本政策や事業戦略の変化に注目
経営陣が資本効率の改善に取り組む姿勢を示しているかどうかも重要なポイントです。自社株買いや配当増額、不採算事業の整理、新規成長分野への投資など、ROE向上につながる施策が計画・実行されているかをチェックするとよいでしょう。
具体的な銘柄例と評価
実際にPERが高くPBRが低い企業の例をいくつか見てみましょう。ただし、市場環境は常に変化しており、これらの評価は執筆時点のものであることにご注意ください。
日本郵船などの海運株
2025年前半の時点では、海運大手の日本郵船(9101)などの海運株は、過去の好業績の反動で利益が減少し、PERが一時的に高くなっているものの、多くの資産を保有しているためPBRは低い水準にあると言われています。
このような企業は、海運市況の回復とともに利益が改善すれば、PERが低下する可能性があります。景気敏感株の特性を考慮した投資判断が必要でしょう。
銀行株
日本の銀行株の多くは、PBRが1倍を下回る水準で取引されています。これは、低金利環境が長く続いたことによる収益力の低下や、多額の不良債権処理を経験したことによる投資家の慎重な見方が背景にあるとされています。
しかし、2025年に入って日本銀行の金利政策変更により、銀行の収益環境は改善しつつあります。今後、利益が増加すればPERが低下し、株価上昇によりPBRも回復する可能性があるとの見方もあるようです。
不動産関連企業
不動産を多く保有する企業もPBRが低くなりがちです。特に、不動産価格が上昇しても、会計上の簿価は取得原価のままであるため、実質的な資産価値が貸借対照表に反映されていないケースがあります。
このような企業は、含み益を考慮した実質PBRでは割安でない場合もあるため、保有資産の実質価値を評価することが重要です。
投資指標の注意点と適切な使い方
PERとPBRを投資判断に活用する際には、いくつかの注意点があります。
PERの注意点
- 成長性を反映していない:PERは現在の利益に基づく指標であり、将来の成長性を直接反映していません。成長企業ではPEGレシオ(PER÷利益成長率)などを併用することが推奨されています。
- 特別損益の影響:純利益には特別損益も含まれるため、一時的な要因でPERが歪む可能性があります。「ノイズを除くには、特別損益を加味する前の経常利益に65%を掛けた数値を使い、”真のPER”を出す必要がある」と個人投資家の竹内弘樹さんは述べています。
- 業種による違い:IT企業など成長性の高い企業はPERが高くなる傾向があり、素材・部品メーカーなど景気敏感株はPERが低くなる傾向があります。
PBRの注意点
- 低PBRがすべて割安というわけではない:「PBRについても、低PBRがすべて割安ということではなく、低い状態が続くということは、投資家間ではその状態が本来の企業価値であると判断されているという見方もできます」とauカブコム証券は説明しています。
- 純資産の質:PBRは純資産の質を考慮していません。例えば、不良債権を多く抱える銀行や陳腐化した設備を持つ製造業では、貸借対照表上の純資産が実質価値を反映していない可能性があります。
- 業種による違い:IT企業など無形資産の比重が大きい企業はPBRが高くなりがちであり、製造業など有形資産の比重が大きい企業はPBRが低くなる傾向があります。
PERとPBRを組み合わせた投資戦略
PERとPBRを組み合わせて活用する投資戦略もあります。
PBR-ROEモデル
2017年に発表された投資戦略「PBR-ROEモデル」では、ROEの水準に応じてPBRの適正レベルが変わると考えられています。
「ROEが8%以下の銘柄は、バリュー投資が効果的となるが、ROEが8%超の銘柄は、ROEが高くなれば、それに応じたPBRの水準が許容される傾向」があるとされています。
つまり、ROEが高い企業ではPBRが高くても割高とは言えず、ROEが低い企業ではPBRが低くても必ずしも割安とは言えないという考え方です。
指標の組み合わせと経時的変化の確認
PERとPBRだけでなく、ROEや配当利回りなど複数の指標を組み合わせて総合的に判断することが重要です。
例えば、楽天証券のレポートでは「予想PER6倍台、PBR1倍割れ、配当利回り4%台と、株価指標から見て極めて割安な株」として日本郵船やINPEXなどの例が挙げられています。
また、一時点の指標だけでなく、過去からの推移や将来の予想値も確認することで、より深い分析が可能になります。「同業他社でもビジネスが全く同じ企業はなかなかなく、比較は参考程度にとどめる。それよりも同じ企業の過去のPERの平均と比べて今が割安・割高かを見るのが効果的」と複眼経済塾の小笹俊一さんは話しています。
PERとPBRから見る投資判断の目安
PERとPBRを組み合わせた際の一般的な投資判断の目安は以下のようになると言われています。
PER低・PBR低
伝統的なバリュー株の特徴で、割安と評価される傾向があります。ただし、成長性の欠如や構造的な問題を抱えている可能性もあるため、要注意です。
PER高・PBR高
典型的なグロース株の特徴で、成長への期待が高い企業に見られます。将来の高成長が実現しなければ株価が下落するリスクがあります。
PER低・PBR高
収益効率が高く、資産を効率的に活用して多くの利益を生み出している企業に見られます。優良企業の特徴とされることが多いようです。
PER高・PBR低
今回のテーマである「PER高・PBR低」の組み合わせは、ROEが低い可能性が高く、資本効率の改善余地がある企業や、一時的に業績が悪化している企業に見られます。改善の兆しがあれば投資機会となる可能性もありますが、慎重な見極めが必要でしょう。
高配当株投資における指標の使い方
高配当株投資を行う際のPERとPBRの使い方についても触れておきましょう。
「では、高配当株投資において何に注意しなければならないかというと、PERやPBRが高すぎないことという点を最重要視してください」と投資家のかつをさんは述べています。
具体的な目安としては、「PERは15倍以下、PBRは1.5倍以下が望ましい」「大型の成熟企業ならPER12倍以下、PBR1.2倍以下が妥当」「PERが20倍以上、PBRが2倍以上の株はよほどの高成長が望めないと高配当株投資には不向き」とされています。
高PER株が高配当株になりにくい理由
「PERが高いということは1株あたりの利益に対して株価がすでに高いということ。そうなると、配当性向を相当高くしないと配当利回りが高くなりません。高PER株が高配当株になるのは至難の業でハードルが高いのです」と説明されています。
また、「高PBR株が無理して高配当利回りを続けると、純資産を食いつぶしてしまう恐れも出てきます」という点も指摘されています。
まとめ:PERが高くPBRが低い企業への投資アプローチ
PERが高くPBRが低い企業への投資を検討する際には、以下のようなアプローチが有効かもしれません。
- ROEの分析:ROEが低い原因を特定し、改善余地があるかを評価する
- 業種特性の考慮:景気敏感株や特定の業種では、PERが高くPBRが低い状態が正常な場合もある
- 一時的要因の見極め:特別損失や一過性の業績悪化など、一時的要因でPERが高くなっている可能性を検討
- 経営改革の可能性:資本効率の改善に向けた経営陣の取り組みや株主からの圧力があるかを確認
- 複数の指標を組み合わせる:PERとPBRだけでなく、ROE、配当利回り、ROIC、自己資本比率などの指標も確認
- 時系列での変化を確認:一時点の指標だけでなく、過去の推移や将来の予想値も考慮
投資は常にリスクを伴うものであり、指標だけで判断するのではなく、企業の事業内容や経営戦略、市場環境など総合的な分析が重要であることをお忘れなく。PERが高くPBRが低い企業の中には、経営改革によって大きく成長する企業もあれば、長期的に低迷し続ける企業もあるでしょう。投資家自身の投資哲学や時間軸に合わせた判断が求められます。
最後に、指標はあくまで投資判断の材料の一つであり、他の要素と組み合わせて総合的に判断することが大切です。また、市場環境や企業の状況は常に変化するため、定期的な見直しも忘れないようにしましょう。
PERが高くPBRが低い企業への投資は、チャレンジングな面もありますが、適切な分析と見極めができれば、魅力的な投資機会となる可能性もあります。ぜひ、本記事の内容を参考に、ご自身の投資判断にお役立てください。
PERが低く、PBRが高い会社は投資家からどのように評価されているのかわかりやすく解説
株式投資において、企業価値を測る様々な指標が存在していますが、今回は特に「PERが低くPBRが高い」という少し変わった特徴を持つ企業が、投資家からどのように評価されているのかについてネットの口コミや評判から真相を掘り下げてみました。東京証券取引所(東証)プライム市場やスタンダード市場に上場している企業の中には、このような指標の特徴を持つ会社が存在し、独特の投資判断を必要とするようです。
PERとPBRの基本:似ているようで異なる2つの指標
まず最初に、PERとPBRの基本的な意味を確認しておきましょう。
PER(Price Earnings Ratio:株価収益率)は「株価÷1株あたりの純利益」で計算される指標です。簡単に言えば、企業の稼ぐ力(利益)に対して株価が何倍になっているかを示しています。例えば、PERが10倍であれば、現在の利益水準が続いた場合、10年間で投資金額を回収できると理論的に考えることができます。
一方、PBR(Price Book-value Ratio:株価純資産倍率)は「株価÷1株あたりの純資産」で計算される指標です。こちらは企業が保有する純資産(資産から負債を差し引いた金額)に対して株価が何倍になっているかを示しています。PBRの目安は一般的に1倍とされ、1倍を下回ると純資産よりも株価が安く、理論上は「割安」と判断されるようです。
これら2つの指標は、どちらも株価の割安感・割高感を示すものですが、PERは「収益力」を基準とし、PBRは「純資産」を基準としている点で大きく異なります。
PERが低くPBRが高い企業の特徴とは
では、PERが低くPBRが高い企業とは、具体的にどのような特徴を持つのでしょうか。
PERが低いということは、1株あたりの利益に対して株価が相対的に低いことを意味します。つまり、現在の収益性の観点からは「割安」と評価できる状態です。
一方で、PBRが高いということは、純資産に対して株価が相対的に高いことを意味します。つまり、企業の保有資産の観点からは「割高」と評価される状態です。
この一見矛盾するような状態は、「少ない資産で多くの利益を生み出している企業」に見られる特徴だと言われています。資本効率が非常に良く、ROE(Return On Equity:自己資本利益率)が高い企業に多く見られる傾向があるようです。
ROEとの関係性:資本効率の良さを示す指標
PERが低くPBRが高い企業を理解する上で、ROE(自己資本利益率)という指標が重要なカギとなるようです。ROEは「当期純利益÷自己資本×100」で計算され、企業が株主から預かった資本をどれだけ効率よく利益に変換できているかを示します。
日本経済新聞の記事によれば、PBRとROEには明確な関係があり、「低ROE&高PBR」の企業は単に割高と評価される一方で、「高ROE&高PBR」の企業は成長株の特徴を持つと言われています。つまり、PERが低くPBRが高い企業の中でも、特にROEが高い企業は、少ない資産で効率よく利益を生み出している「優良企業」として投資家から評価される傾向があるのです。
一般的に、ROEが10%を上回る企業は投資価値のある優良企業と言われており、PERが低くPBRが高い特徴を持つ企業がこのROE水準を達成している場合、資本効率の良さから積極的な投資対象となるケースが多いようです。
PERが低くPBRが高い企業の業種別特徴
PERが低くPBRが高い企業は、業種によっても特徴が異なるようです。
IT・情報通信業
IT業界や情報通信業では、物理的な資産(工場や設備など)をあまり必要とせず、人的資本やソフトウェア、知的財産などの無形資産で高い利益を上げる企業が多く存在します。そのため、純資産は相対的に少なくても高い利益率を実現できることから、PERが低くPBRが高い特徴を持つ企業が見られるようです。
東証プライム市場の情報・通信業のPBR平均値は2.3倍と、他業種に比べて高い傾向にあると報告されています。このような業種では、高いPBRが必ずしも割高を意味せず、むしろ業種特性の表れとして理解される傾向があるようです。
サービス業
飲食・小売・コンサルティングなどのサービス業も、物理的な資産よりも人的資本やブランド力で収益を上げる業態が多いことから、PERが低くPBRが高くなる傾向があると言われています。
特に、フランチャイズビジネスを展開している企業では、自社で多くの不動産や設備を持たずに事業拡大できるビジネスモデルを持つため、少ない純資産で高い利益を上げられることがあります。ファーストリテイリング(ユニクロ)などの企業は、高いROEを実現していることで知られており、投資家からも高い評価を受けていると言われています。
製造業の中の高収益企業
製造業は一般的に工場や設備などの固定資産を多く保有するため、PBRは低くなる傾向があります。しかし、その中でも特殊な技術や圧倒的なシェアを持ち、高い利益率を実現している企業は、PERが低くPBRが高いという特徴を持つ場合があるようです。
例えば、独自の技術や特許を多く持ち、高い参入障壁を築いている企業などが該当します。このような企業は、物理的な資産の価値以上に、技術力やブランド力などの無形資産が評価され、PBRが高くなる傾向があると言われています。
投資家からの評価の視点
PERが低くPBRが高い企業は、投資家からどのように評価されているのでしょうか。いくつかの視点から分析してみましょう。
資本効率重視の視点
近年の投資環境では、企業の資本効率を重視する傾向が強まっていると言われています。東京証券取引所も2023年3月に「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」を要請しており、企業側も資本効率の向上に取り組む姿勢を強めているようです。
このような背景から、PERが低く(収益性が高く)、ROEも高い企業は、たとえPBRが高くても投資家から前向きに評価される傾向にあるようです。特に、機関投資家や海外投資家は資本効率を重視する傾向が強く、そのような企業への投資を積極的に行っていると言われています。
成長性と持続可能性の評価
PERが低いことは現在の収益性が高いことを示していますが、投資家は「その収益性が持続可能かどうか」という点も重視しています。PBRが高いことは、純資産以上に企業価値が評価されていることを意味するため、将来の成長期待も込められていると解釈できるようです。
したがって、PERが低くPBRが高い企業の中でも、その高い収益性が一時的なものではなく、持続可能な競争優位性に基づいていると判断される企業は、投資家から高い評価を受ける傾向があるようです。例えば、強固な参入障壁や独自のビジネスモデルを持つ企業などが該当します。
リスク要因の分析
一方で、PERが低くPBRが高い企業には、いくつかのリスク要因も存在します。
まず、PERが低い(割安に見える)理由が、単に「投資家から今後の業績に不安がある」と見なされているケースもあります。例えば、現在は高い利益を上げていても、将来的に競争環境の激化や事業モデルの陳腐化などによって収益性が低下すると予想される場合、PERは低くなる傾向があります。
また、PBRが高いということは、純資産が少ない状態で事業を行っているため、万が一の業績悪化時には財務的な余力が少ない可能性もあります。このような企業は、不測の事態に対する耐性が低いと判断されることもあるようです。
日本株調査会社TIWの藤根靖晃氏によれば、高PBR銘柄の中にはスタートアップ企業など、まだあまり利益が出ていないためROEも低い企業が含まれることがあり、そのような企業は成長性などを個別に判断する必要があると指摘しています。
具体的な事例分析
では、実際にPERが低くPBRが高い特徴を持つ企業の事例を見てみましょう。
ファーストリテイリング(東証:9983)
ユニクロを展開するファーストリテイリングは、過去に高いROEを実現していたことで知られています。同社はフランチャイズ展開や自社工場を持たないビジネスモデルを採用し、少ない資産で高い収益を上げる資本効率の良さが特徴です。このような特性から、時期によってはPERが相対的に低くPBRが高い状態となることがあるようです。
IT・SaaS企業
IT企業、特にSaaS(Software as a Service)モデルを展開する企業の中には、物理的な資産はほとんど持たないものの、ストック型の収益モデルで安定した高い利益を上げている企業が存在します。このような企業は純資産に対して利益率が高く、PERが低くPBRが高いという特徴を持つことがあります。
高収益な食品・日用品メーカー
ブランド力を持つ食品メーカーや日用品メーカーの中にも、工場などの資産は比較的少なくても高い利益率を誇る企業があります。特に、独自の技術やブランド力で高い参入障壁を築いている企業は、少ない資産で高い収益を上げることが可能で、PERが低くPBRが高いという特徴を持つ場合があるようです。
投資判断のポイント
PERが低くPBRが高い企業に投資する際、どのようなポイントに注目すべきでしょうか。
ROEの確認
先述の通り、PERが低くPBRが高い企業の評価において、ROEは重要な指標となります。ROEが継続的に高水準(一般的には10%以上)を維持している企業は、資本効率の良さが評価されやすいと言われています。
特に、PBRが高い(1.5倍以上など)にもかかわらず投資対象として検討する場合は、ROEの水準に注目することが重要だと考えられています。
収益の持続可能性
PERが低いということは現在の収益性が高いことを示していますが、その収益が持続可能かどうかを見極めることが重要です。業界の競争環境、参入障壁の高さ、技術革新への対応力などを分析し、現在の高い収益性が一時的なものではなく、長期的に維持できるかどうかを判断する必要があるようです。
例えば、売上高営業利益率の推移や、過去のROEの安定性などをチェックすることで、収益力の持続可能性を評価することができると言われています。
業種特性の理解
PBRの評価は業種によって大きく異なります。日経の記事によれば、2024年4月末時点のプライム市場では、情報・通信業のPBR平均は2.3倍である一方、鉄鋼業は0.7倍と大きな差があったと報告されています。
そのため、PERが低くPBRが高い企業を評価する際には、同業他社との比較が重要だと言われています。山和証券の志田憲太郎氏によれば、「工場など多くの固定資産を持つ製造業ではPBRは低くなる。このように業種ごとの特性を知り、同業他社間で比較することが有効だ」とのことです。
株主還元方針
PERが低く収益性が高い企業の場合、その利益をどのように活用するかという点も重要な評価ポイントです。株主還元(配当や自社株買い)に積極的な企業であれば、投資家にとっても直接的なリターンが期待できます。
特に、PBRが高く純資産が相対的に少ない企業の場合、「無理して高配当利回りを続けると、純資産を食いつぶしてしまう恐れ」もあるため、配当性向(純利益に対する配当金の割合)なども確認することが重要だと言われています。
ネットキャッシュ倍率の活用
PBRの弱点を補う指標として、「ネットキャッシュ倍率」の活用も提案されています。複眼経済塾の小笹俊一氏によれば、「『確実に換金して売れる』資産である流動資産を使って株価の割安性を計算する『ネットキャッシュ倍率』を併用して、その弱点を補完することも効果的」とのことです。
この指標を使うことで、純資産の質も加味した評価が可能になると言われています。
市場環境による評価の変化
PERが低くPBRが高い企業への評価は、市場環境によっても変化するようです。
成長期待の高い相場環境
全体的に株価が上昇している強気相場(ブル・マーケット)では、投資家はより成長性を重視する傾向があります。このような市場環境では、現在の収益性(PERの低さ)よりも、将来の成長期待が込められたPBRの高さが評価される傾向があるようです。
特に、テクノロジー企業や成長産業に属する企業などは、たとえPERが相対的に低くても、PBRの高さが将来の成長期待として前向きに評価されるケースが多いと言われています。
割安性重視の慎重な相場環境
一方、市場全体が調整局面や下落相場(ベア・マーケット)の場合、投資家はより慎重になり、割安性を重視する傾向が強まります。このような環境では、PERの低さ(割安性)が評価される一方で、PBRの高さはリスク要因として慎重に見られる傾向があるようです。
特に、PBRが高い企業は「純資産に対して割高な株価」と判断され、株価下落リスクが高いと見なされることもあります。ただし、ROEが高く資本効率の良さが市場に認められている企業であれば、そのような環境下でも相対的に評価される可能性が高いと言われています。
日本企業のPBR改善への取り組み
近年、日本企業の間ではPBR改善に向けた取り組みが活発化しているようです。東京証券取引所は2023年3月に「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」を要請しており、特にPBR1倍割れ企業の多さが課題として指摘されています。
マーケット・キャスターの叶内文子氏は、「資本効率の改善によるPBR1倍割れ解消を狙うなら、むしろPBRが低すぎない銘柄が狙い目」と述べています。「0.8倍など比較的1倍に近い銘柄は、様々な解消策を打ってくると考えられるが、極端にPBRが低い企業は何らかの問題を抱えていると考えられ、改善や株価の上昇を期待できない」とのことです。
このような市場環境の中、PERが低くPBRが高い企業は、すでに資本効率の良さを実現している企業として、投資家から前向きな評価を受ける傾向があるようです。
PERが低くPBRが高い企業の見極め方:まとめ
PERが低くPBRが高い企業を評価する際のポイントをまとめると以下のようになります。
- ROEの確認: 高いROE(10%以上)を継続的に達成しているかを確認する
- 収益の持続可能性: 現在の高い収益性が持続可能かどうかを分析する
- 業種特性の理解: 同業他社と比較して相対的な位置づけを把握する
- 株主還元方針: 配当や自社株買いなど、株主還元への姿勢を確認する
- 収益構造の分析: 高い収益性の源泉が何かを理解する(独自技術、参入障壁、ブランド力など)
- 市場環境の考慮: 全体的な市場環境によって評価が変わることを意識する
PERが低くPBRが高い企業は、一般的には「少ない資産で効率よく利益を生み出している企業」として評価される傾向がありますが、その評価は業種特性や市場環境、企業固有の状況によって大きく異なります。投資判断を行う際には、これらの要素を総合的に考慮することが重要だと言われています。
終わりに:投資判断は総合的な視点から
PERとPBRはどちらも重要な投資指標ですが、これらはあくまで企業評価の一側面を示すものに過ぎません。PERが低くPBRが高いという特性を持つ企業が必ずしも良い投資対象とは限らず、また逆にそのような企業が常に避けるべき対象というわけでもありません。
最終的な投資判断は、これらの指標に加えて、企業の成長戦略、競争環境、経営陣の質、財務健全性、株主還元方針など、多角的な視点から総合的に行うことが重要だと言われています。
株式投資において絶対的な正解はなく、各投資家の投資スタイルや時間軸、リスク許容度に合わせた判断が求められるのです。PERとPBRという2つの指標の関係性を理解することは、投資判断の一助となりますが、それだけで投資判断を行うのではなく、より包括的な分析を心がけることが大切だと言えるでしょう。


