雇用保険被保険者資格取得届の記入例についてわかりやすく解説
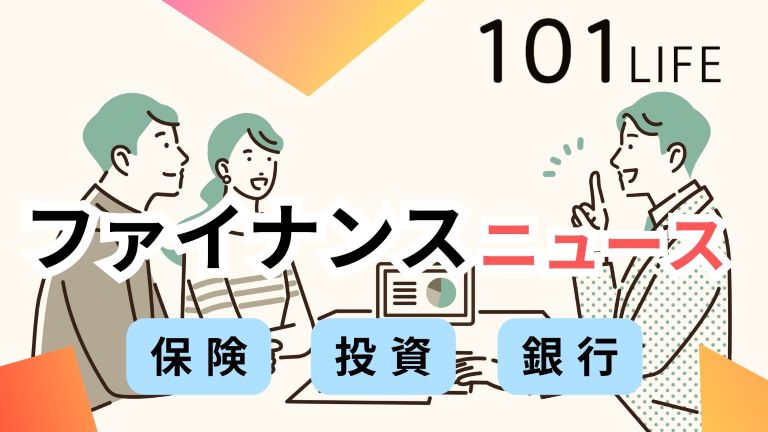
雇用保険被保険者資格取得届の記入例と書き方ガイド
雇用保険被保険者資格取得届についてネットの口コミや評判から真相を掘り下げてみました。企業担当者から「記入項目が多くて迷う」「初めての提出で不安」という声が多く聞かれます。この書類は従業員を雇用保険に加入させるための重要な手続きであり、記入ミスがあると受理されず手続きが遅れるリスクがあります。本記事では届出の基本情報から具体的な記入例、注意点まで詳しく解説していきます。
雇用保険被保険者資格取得届とは?
雇用保険被保険者資格取得届とは、従業員を新たに雇用保険に加入させる場合に企業が提出する書類です。一般的に「資格取得届」と略されることも多く、労務担当者にとっては入社手続きの際に必ず処理する重要書類となっています。
前職で雇用保険に加入していた従業員も含め、自社で雇用保険の加入条件を満たす場合は必ず提出しなければなりません。被保険者番号は就職先が変わっても基本的に同じ番号が使われるため、転職者の場合は本人から被保険者証を預かって書類を作成するケースが多いです。
提出先と提出期限
【提出先】 事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)です。
【提出期限】 新たに被保険者となる事実が発生した月の翌月10日までに提出する必要があります。例えば4月1日付けで雇用した従業員分の提出期限は5月10日となります。期限を過ぎると罰則の対象となる可能性もありますので、必ず期限内に提出しましょう。
雇用保険被保険者資格取得届が必要な場面
雇用保険被保険者資格取得届が必要なのは、従業員が新たに雇用保険の対象となる場合です。具体的には、採用や労働条件変更などに伴い、下記の条件を満たすときに提出が必要になります。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
- 31日以上の雇用が見込まれること
「31日以上の雇用が見込まれること」とは、明らかに31日以上継続して雇用しない場合以外は基本的に該当します。また、雇用開始時に31日以上の雇用が見込まれていなかったとしても、途中から31日以上が見込まれるようになれば、その時点から雇用保険に加入できます。
要件を満たせば、事業主や従業員の希望の有無に関わらず、被保険者として加入する必要があります。雇用形態が契約社員、パートタイマー、アルバイトの方も、正社員と同様に被保険者となります。
雇用保険被保険者資格取得届の記入項目と書き方
それでは、雇用保険被保険者資格取得届の具体的な書き方について項目ごとに解説します。書類はハローワークの窓口で入手したり、ハローワークのホームページ「ハローワークインターネットサービス」の「帳票一覧」からダウンロードしたりできます。
1. 個人番号(マイナンバー)
個人番号には被保険者のマイナンバーを記入します。マイナンバーを記入する際は、必ず本人確認を行う必要があります。個人番号を従業員から取得する際は、個人番号の利用目的を提示し、番号確認と本人確認を実施します。
2. 被保険者番号
転職者などで本人が被保険者証を持っている場合、被保険者証に記載されている被保険者番号を転記します。初めて被保険者となる従業員の場合は空欄で問題ありません。被保険者番号は11桁(4桁-6桁-1桁)で記載します。
3. 取得区分
新たに被保険者番号を取得する場合、あるいは被保険者でなくなった日から7年以上が経っている場合は「新規」に該当する「1」を記入します。それ以外は「再取得」に該当する「2」を記入します。
4. 被保険者氏名
被保険者氏名欄にフルネームを記載のうえ、右側にあるフリガナ欄にカタカナでフリガナを記載します。
フリガナ欄は姓と名の間を1マス空け、濁点なども1文字分とします。例えば「山田 太郎」の場合、「ヤマダ□タロウ」(□は空白を表す)と記載します。
5. 変更後の氏名
すでに被保険者証を持っている場合で、そこに記載された氏名との変更があれば記載します。
この欄を記入している場合は別途氏名変更届を出す必要はありません。氏名変更届は2020年5月31日に廃止になり、資格取得届、資格喪失届、育児休業給付金等の書類提出時にあわせて氏名変更することになりました。
氏名の変更がなければ空欄にします。
6. 性別
被保険者の性別を番号で記入します。男性は「1」、女性は「2」を記入します。
7. 生年月日
生年月日を和暦で記載します。元号は該当するものの番号を記載し、年月日の年、月、日が1桁の場合はそれぞれ10の位に0を付けて2桁で記載します。
例:昭和51年5月6日の場合、「3-510506」と記入します。 例:平成8年7月1日の場合、「4-080701」と記入します。
8. 事業所番号
自社の事業所番号を記入します。適用事業所台帳に記載されている事業所番号11桁(4桁-6桁-1桁)を記載します。
9. 被保険者となったことの原因
被保険者となった原因について、選択肢の中から選んで記入します。主な選択肢は以下の通りです。
- 新規雇用(新規学卒):新規学校卒業者のうち、卒業年の3月1日から6月30日までの間に雇い入れた場合
- 新規雇用(その他):中途採用者を雇い入れた場合など
- 日雇からの切り替え:日雇い従業員が雇用保険の適用となったとき
- その他:被保険者の雇用される事業所が新たに適用事業となった場合など
- 出向元への復帰等(65歳以上):65歳以上の者が出向元に復帰した場合など
10. 賃金
その従業員への支払い体系(月給・週給・日給・時間給・その他)と賃金月額を記入します。
雇い入れ日時点の賃金の支払態様を以下の番号で記載します。
- 月給
- 週給
- 日給
- 時間給
- その他
賃金の金額は、月額を千円単位で記載します。賃金には、賞与、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金、残業代は除きます。
例:月給で、月の賃金が30万円の場合、「1-0300」と記載します。
11. 資格取得年月日
被保険者となった始まりの日のことで、基本的には雇入れの日となります。試用期間、研修期間も含みます。
例えば令和6年10月1日付け採用であれば資格取得年月日は令和6年10月1日です。初日が日曜日や祝日など事業所の所定休日に当たる場合も、初日を記入します。
12. 雇用形態
被保険者となる従業員の雇用形態を選択肢の中から数字で記入します。主な選択肢は以下の通りです。
- 日雇
- 派遣
- パートタイム
- 有期契約労働者
- 季節的雇用
- 船員
- その他(正社員の場合はこちらを選択)
13. 職種
被保険者の職種について、選択肢の中から該当する番号を記入します。主な職種は以下の通りです。
- 管理的職業(会社や団体の役員および管理職員)
- 専門的・技術的職業(教育関係、医学関係、芸術関係など)
- 事務的職業(経理事務、総務事務、テレフォンオペレーターなど)
- 販売の職業(販売店員、販売外交員、保険外交員など)
- サービスの職業(理容・美容、調理人、ホールスタッフなど)
- 保安の職業
- 農林漁業の職業
- 生産工程の職業
- 輸送・機械運転の職業
- 建築・採掘の職業
- 運搬・清掃等の職業
14. 就職経路
どのような経路で就職したかを記入します。
15. 1週間の所定労働時間
1週間の所定労働時間を記入します。
16. 契約期間の定め
契約期間の有無や期間を記入します。
雇用保険被保険者資格取得届作成時の注意点
雇用保険被保険者資格取得届の作成は決して難しいものではありません。しかし、正確さやていねいさが求められます。ここでは、作成時の注意点について説明します。
明確かつ正確に記入する
雇用保険被保険者資格取得届は、機械(OCR)で読み取って処理されます。そのため、枠内に記入する文字は、エラーが起きないよう、枠からはみ出さず、ていねいに記入してください。
また、ダウンロードした様式を印刷する際には以下の点に注意が必要です。
- 第1面と第2面の両方を印刷する(片面印刷でも両面印刷でも可)
- A4の白色用紙に等倍(倍率100%)で印刷する
- OCRで読み取るため読取時の基準マーク(用紙の端の3点の■)が印刷できていることを確認する
- 印刷面が指定されている紙(片面専用の印刷用紙など)を使用する場合は指定された印刷面に印刷していることを確認する
- 印刷した様式が用紙に対して極度に傾いていないことを確認する
- 印刷した様式の文字や枠線にかすれがないことや2重に印刷されていないことを確認する
正しく印刷されていないと受理してもらえない場合がありますので、事前に印刷設定を確認すると共に印刷後にも再度確認することが大切です。
資格取得日に気をつける
雇用保険の資格取得日は、雇用契約期間の初日です。初日が日曜日や祝日など事業所の所定休日に当たる場合も、初日を記入します。
また、試用期間がある場合、資格取得日は試用期間の初日になります。本採用の日ではないため、気をつけましょう。
契約内容が変更された場合も注意が必要です。週所定労働時間が20時間未満だった従業員が、契約変更により所定労働時間が増加し、週20時間以上就労するようになった場合、資格取得日は雇入日ではなく、契約変更日です。
雇用保険被保険者資格取得届の提出手続き方法
雇用保険被保険者資格取得届は、要件を満たす従業員を雇い入れた日の翌月10日までに、事業所の所在地を管轄するハローワーク(公共職業安定所)に提出します。
提出方法は、ハローワークの窓口に持参、郵送、電子申請の3つがあります。
窓口持参
ハローワークに持参する方法は、専門の職員が窓口で受けつけてくれるため、雇用保険事務に慣れていない場合でも安心です。ただしハローワークによっては非常に混雑し、待ち時間が長いことがあります。
郵送
管轄のハローワークに郵送することもできます。雇用保険被保険者資格取得届にはマイナンバーなどの個人情報が記載されているため、簡易書留や特定記録で郵送してください。切手を貼付した返信用封筒も同封します。
電子申請
雇用保険被保険者資格取得届は、電子申請もできます。電子申請とは、e-Govや労務管理ソフトを利用し、オンラインで申請する方法です。
事前に電子証明書を取得する必要がありますが、そうした電子申請の環境を整えてしまえば、ハローワークに行く時間や郵送コストをかけることなく、迅速な手続きが可能となります。
添付書類
添付書類は原則として不要です。ただし「初めて従業員を雇用するなど事業主として初めての被保険者資格取得届を行う場合」は、賃金台帳や出勤簿(タイムカード)、労働者名簿などの添付が必要になることがあります。
また、兼務役員や同居の家族などが資格取得する場合、資格取得届とは別に雇用実態証明書を添付する必要がありますので、要件の確認についても所轄ハローワークに相談するとよいでしょう。
提出後のプロセス
ハローワークに雇用保険被保険者資格取得届を提出し、加入手続きが完了すると、雇用保険被保険者証が交付されます。雇用保険被保険者証は雇用保険に加入した証明書です。
交付される書類には会社が保管するものと従業員へ交付するものがあります。被保険者のしおり以外はA4サイズ1枚に印字されていますので切り分けることになります。
【交付される書類】 会社で保管するもの:
- 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)
- 被保険者証 ※退職時に離職票と一緒に本人へ渡す。
従業員へ渡すもの:
- 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(被保険者通知用)
- 被保険者のしおり
雇用保険被保険者証は、勤務先のほうで本人の退社まで預かっていることも多く、あまり見る機会がない場合もあります。
提出後の修正が必要な場合
資格取得届や資格喪失届(離職証明書含む)等を管轄ハローワークに提出後に内容に誤りがあることがわかった場合、「雇用保険被保険者資格取得・喪失等届訂正・取消願」に必要事項を記載し、管轄ハローワークに提出する必要があります。
なお、訂正した内容が確認できる資料等が必要となる場合がありますので、内容に誤りがあることがわかった場合は、提出方法についてあらかじめ管轄ハローワークに相談することをおすすめします。
よくあるQ&A
Q1. アルバイトでも雇用保険に加入できますか?
A1. はい、雇用保険は以下の条件を全て満たすことで加入となります。
- 週の労働時間が20時間以上
- 1か月(31日)以上働く見込みの場合
- 学生ではない(通信教育や定時制、夜間学生、休学中の学生等を除く)
法律の要件に達する場合加入となり、自分の希望や会社の方針で、加入する・しないを選ぶものではありません。
Q2. 雇用保険の加入を忘れていた場合はどうすればいいですか?
A2. 雇用保険の加入条件を満たしているにもかかわらず、雇用保険に未加入の状態で退職してしまった場合、離職日から2年以内であれば遡って加入手続きが可能です。
Q3. 雇用保険被保険者証で何がわかりますか?
A3. 雇用保険被保険者証でわかるのは、前職の勤務先名と資格取得年月日(入社時期)のみです。そのため、退職時期までは分かりません。
Q4. 雇用保険の加入を拒まれた場合はどうすればいいですか?
A4. 雇用保険の保険料は雇い主と労働者自身です。あなた自身が雇用保険に加入する条件を満たしているのに、対応してくれない場合は直接ハローワークで加入の手続きを行うこともできます。
まず自分の雇用保険の手続き状況を照会するために、ハローワークで配布されている「雇用保険被保険者資格取得届出確認照会票」に必要事項を記入、所在地管轄のハローワークへ提出します。雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書で照会結果が通知されます。
まとめ
雇用保険被保険者資格取得届は、従業員を雇用保険に加入させるために企業が提出する重要な書類です。記入項目は多いですが、ポイントを押さえて丁寧に記入することが大切です。
提出期限は従業員を雇い入れた月の翌月10日までとなっていますので、期限内に漏れなく提出するよう心がけましょう。提出後は雇用保険被保険者証が交付され、従業員に渡す必要があります。
また、雇用保険は週20時間以上、31日以上の雇用見込みがある従業員であれば、雇用形態に関わらず加入が必要です。アルバイトでも条件を満たせば加入でき、失業手当などの給付を受けることができます。
雇用保険被保険者資格取得届の記入や提出に不安がある場合は、管轄のハローワークに相談するとよいでしょう。正確な記入と適切な提出により、従業員の雇用保険加入手続きをスムーズに進めることができます。

