保険入ってないと”やばい”といわれているのはなぜ?
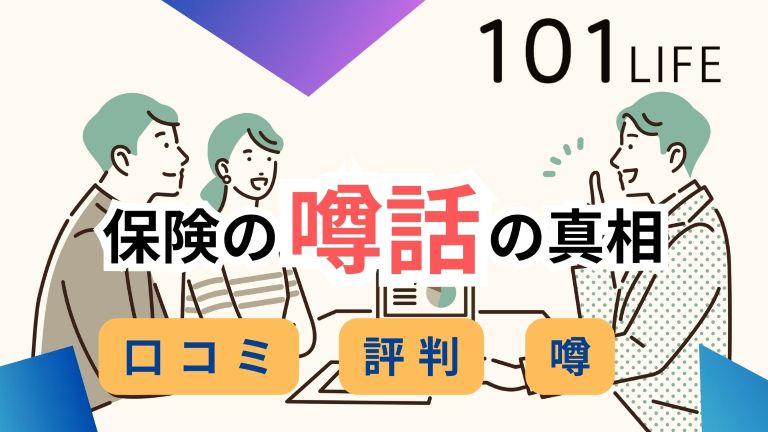
”保険入ってないのはやばい”と口コミや評判で言われている原因と真相について掘り下げて解説します
保険に入らないと”やばい”と噂される理由や原因についてネットの口コミや評判から真相を掘り下げてみました。私たちの生活において保険は重要な安全網とされていますが、実際にどのようなリスクがあるのか、また「保険不要論」の背景にある考え方は正しいのでしょうか。医療保険、自動車保険、国民健康保険、社会保険、生命保険など様々な保険について、入らないことによるリスクと良い評判の両面から検証していきます。
保険の種類と「やばい」と言われる背景
保険には様々な種類があり、それぞれに異なる役割や特性があります。一般的に「保険に入らないとやばい」と言われる背景には、万が一の事態に備えるという保険本来の役割が反映されているようです。主な保険の種類には以下のようなものがあります。
- 医療保険:病気やケガによる入院・手術などの医療費をカバー
- 自動車保険:事故による対人・対物賠償や自身の車両損害をカバー
- 国民健康保険:自営業者や無職の方などが加入する公的医療保険
- 社会保険:企業が従業員のために加入する健康保険・厚生年金等
- 生命保険:死亡や高度障害時の保障を提供
それぞれの保険について、入らないことで生じるリスクや問題点、また保険に関する誤解や良い評判について詳しく見ていきましょう。
医療保険に入らないことによるリスク
医療保険に加入しないことでどのようなリスクがあるのでしょうか。検索結果を基に詳しく見ていきます。
医療保険に入らないと後悔する瞬間
医療保険に入らなくて一番後悔する瞬間は「医療保険に入ろうと思っても、入れなかった時」だと言われています。実際に「体調不良が続いている」「健康診断で再検査や要治療の判定を受けた」などをきっかけに、保険への加入を検討する人は少なくないようです。
しかし、一般的にまだ病気と診断されたわけではない段階でも、保険会社ごとの審査基準をクリアできなければ保険には加入できないようです。服用している薬や血液検査等の数値、エコー検査で影が見えただけで診査に通らないこともあります。
特にがんに罹患するとほとんどの保険への加入が難しくなるとされています。保険に入っておけば良かったと後悔する瞬間として多く挙げられるのが「がんが発覚した時」だとされています。
医療保険に入らないと後悔する5つのケース
医療保険に入らなくて後悔するケースとしては、以下のようなものが挙げられています。
ケース1:入院した際に個室を希望したら自己負担費用が多かった
公益財団法人生命保険文化センターの「2022(令和4年度)生活保障に関する調査《速報版》」によると、直近の入院時の自己負担費用の平均額は19.8万円だったとされています。この金額には公的医療保険制度の対象外である差額ベッド代、個室代なども含まれています。
プライバシーの確保や他人の生活音、就寝時の明かりなどによるストレスを軽減するため個室を利用したいと考えている人も少なくはないようですが、自分から個室や少人数部屋を希望した場合は、本来の治療費に上乗せして1日あたり3000円〜1万円程度の追加費用がかかることがあるようです。
ケース2:先進医療を受けようとしたら全額自己負担だった
先進医療は公的医療保険制度の対象外となるため、費用は全額自己負担となります。先進的な治療法を選択したい場合、医療保険に入っていないと大きな経済的負担になる可能性があります。
その他のリスク
その他にも、医療保険に入らないことで以下のようなリスクがあるとされています。
- 継続的な治療が必要となる場合に貯金だけでは賄いきれない可能性がある
- 入退院を繰り返したり、退院後も投薬治療を続けるなど「終わりの見えない治療」による経済的負担
- 生活習慣病の場合、食生活の見直しや住環境の変更など日常生活でかかる追加費用の負担
- 大きな事故の場合、後遺症によっては何年もかけてリハビリが必要になる可能性
自動車保険(任意保険)に入らないことによるリスク
自動車保険には、加入が法律で義務付けられている「自賠責保険(強制保険)」と、任意で加入する「任意保険」の2種類があります。
自賠責保険と任意保険の違い
自賠責保険は対人補償のみで、死亡時は最高で3,000万円、高度障害時には最高で4,000万円、ケガの場合は最高120万円が補償の上限となっています。
一方、任意保険はこれらの基本補償に加えて、以下のような補償を提供しています。
- 対人賠償の上乗せ(無制限にすることも可能)
- 対物賠償(相手の車や物への損害)
- 自分や同乗者のケガの補償
- 自分の車の修理費用の補償(車両保険)
- ロードサービスなどの各種サポート
任意保険の加入率
日本損害保険協会のデータによると、任意保険の加入率には地域差があり、東京は8割近くが加入していますが、沖縄は54.4%とおよそ半分となっています。
しかし、各種共済を含めると、ベスト5の都道府県はすべて90%超え、最も加入率の低い沖縄県でも79%となっており、実際にはかなり多くの人が何らかの形で自動車保険に加入しているようです。
任意保険に入らないリスク
任意保険に入らないことで、以下のようなリスクがあると言われています。
- 事故の際の賠償責任
- 自賠責保険だけでは対物賠償(相手の車や物への損害)は補償されません
- 高額な修理費や物的損害の賠償を自己負担する必要があります
- 人身事故で相手に重傷を負わせた場合、自賠責保険の限度額を超える部分は自己負担になります
- 自分自身や同乗者のケガ
- 自分や同乗者のケガは自賠責保険では補償されません
- 治療費や休業補償を自己負担する必要があります
- 自分の車の損害
- 自分の車の修理費用は任意保険の車両保険がないと全額自己負担になります
- 事故や災害による高額な修理費用がかかる可能性があります
無保険車にぶつけられた場合のリスクも指摘されており、「必ず払いますから待ってください〜」と言われながら実際には支払われないケースや、人身事故で大怪我をさせられても十分な補償が受けられないケースがあるようです。
任意保険が”やばい”と言われる理由
一方で、「任意保険がやばい」という噂も存在するようです。その主な理由としては以下のような点が挙げられています。
1. 事故対応に関する不満
ある口コミサイトでは、「過失割合が10:0だと、一方的に保険金を払わない方向で、処理しようとする史上最悪の保険会社です。被害者がケガをしていても、そうです」という厳しい批判があったとされています。
また、「被害者のことなど何も思っていない、自分の成績(早い処理、保険金を払わない)だけ、考えている社員が多いです」「物損担当から紹介された修理会社で、修理をしてはいけません。適当に修理されてしまう可能性があります」といった具体的な指摘もあるようです。
2. 保険金の支払い査定の厳しさ
加害者側の保険会社が被害者に低い慰謝料を提示することがあるという指摘もあります。その理由として以下のような要因が考えられています。
- 治療期間が短い
- 通院日数が少ない
- 正しい後遺障害等級が認定されていない
- 被害者の過失割合が大きく設定されている
- 被害者が自力・単独で示談交渉している
3. 苦情件数の多さ
日本損害保険協会や外国損害保険協会が公表している苦情件数のデータによると、一部の保険会社は他社と比較して苦情発生率が高いとされています。
4. 契約途中での解約の多さ
一部の保険会社では、契約途中での解約率が高いという指摘もあります。例えば、あるネット記事ではチューリッヒ保険が「例年、自動車保険の解約が飛び抜けて多い」と報告されているようです。
任意保険に関する良い評判
一方で、任意保険に関する良い評判も存在します。ソニー損保の例では、外部機関による顧客満足度調査で非常に高い評価を得ているとされています。「価格コム」「オリコン」「JD POWER」などの調査において、以下のような好成績を収めているようです。
| 年 | 価格コム | オリコン | JD POWER |
|---|---|---|---|
| 2020年 | 1位 | 1位 | 1位 |
| 2019年 | 3位 | 1位 | 1位 |
| 2018年 | 4位 | 1位 | 3位 |
このデータからは、少なくとも一部の保険会社では高い顧客満足度を維持していることがわかります。
国民健康保険の問題点と評判
国民健康保険(以下、国保)は、国民皆保険の中核的役割を担うとともに、医療のセーフティネットとして国民の健康を支えている制度です。
国民健康保険の現状
国保は各市町村が運営する医療保険で、自営業者とその家族、無職の世帯などを対象としています。現在は全世帯の4割にあたる約2000万世帯、約3600万人が加入していると言われています。もともとは農林水産業や自営業を中心として発足しましたが、現在では無職や非正規雇用などの低所得者の割合が増えてきているようです。
国民健康保険が”やばい”と言われる理由
国保が「やばい」と言われる理由は、検索結果に具体的に挙げられていませんでしたが、一般的に以下のような問題点が指摘されているようです。
- 保険料の高さ(特に自営業者や低所得者にとって負担が大きい)
- 滞納者の増加
- 財政悪化による持続可能性への懸念
- 加入者の高齢化と医療費の増加
- 保険料の地域格差
国民健康保険の良い面や評判
国保に対しては厳しい意見が多く見られますが、以下のような良い点もあると考えられます。
- 職業や年齢、健康状態に関わらず加入できる(医療のセーフティネット)
- 所得に応じた保険料設定(負担能力に配慮)
- 高額療養費制度による医療費負担の軽減
- 出産育児一時金や葬祭費などの各種給付
国民健康保険においても無保険状態は様々なリスクをもたらします。加入が必要な方は必ず手続きを行うことが重要です。
社会保険未加入の問題点
企業が社会保険(健康保険・厚生年金および労災保険・雇用保険)に加入しないことで生じる問題についても見ていきましょう。
社会保険の加入義務
法人の事業所の場合、業種や従業員数にかかわらず、必ず健康保険・厚生年金に加入しなければなりません。また、適用業種の事業を行い、かつ常時5人以上の従業員を使用する個人事業主の事業所にも加入義務があります。
労災保険・雇用保険ともに、経営者・個人事業主および労働者の意思に関係なく、一部事業を除いて加入が義務付けられています。
社会保険未加入のリスク
社会保険に加入しない場合、以下のようなリスクがあると言われています。
- 従業員からの賠償請求
- 従業員の病気や怪我、事故などで多額の賠償金を請求されるおそれがあります
- 万一従業員が死亡した場合、倒産の危機に陥るほどの大問題に発展しかねません
- 行政からの強制加入
- 現在国は社会保険の未加入企業に厳しく指導をしています
- 社会保険加入の勧奨を無視し続けた場合、強制加入させられることに加え、最大2年分の社会保険料を強制徴収されるリスクがあります
- ビジネス上の不利益
- 社会保険未加入の場合、ハローワークに求人を出すことができないなどのデメリットがあります
- 取引先から社会保険の加入証明を求められるケースも増えています
社会保険は健康保険・厚生年金および労災保険・雇用保険ともに、法人・個人事業主を問わず、ほとんどの事業所で加入が義務付けられています。加入しないことによるリスクやデメリットを考慮すると、法人または個人事業主の義務と責任から、必ず社会保険に加入することが推奨されています。
生命保険に関する誤解と真実
生命保険に関しては、様々な誤解が存在するようです。生命保険が「やばい」と噂される背景には、こうした誤解も影響しているかもしれません。主な誤解とその真相について見ていきましょう。
誤解1:保険は損
保険に加入しても利用しないことがあるため、加入そのものを経済的に損であると考え、否定する人々がいるようです。しかし、あくまで保険は万が一のリスクに備えるためのものであり、損得で考えるものではないとされています。
これは、大地震が起きない可能性があるから、食料などの備蓄は不要であると言っていることと同じだという指摘もあります。リスクに備えることは、それを結果的に使用しない場合も想定しています。家計への配慮も大事ですが、損失が甚大となる万が一の事態のために、保険に加入しておくことは必要だとされています。
誤解2:独身や共働きは保険不要
「保険は損」という意見と関連したものとして、独身や共働きの人は保険が不要という話もよく耳にするようです。確かに、独身や共働きであれば、万が一の事態における遺族保障の必要性は、一般的に乏しいとされています。
しかし独身でも、例えば、両親を経済的に支えていることもあるでしょう。また、ケガなどで働けなくなった場合、健康保険の傷病手当金以外の保障が必要になる可能性もあります。
共働きの場合、インカムがダブルからシングルになるため、大幅に世帯収入が減少する恐れもあるでしょう。そのリスクには、備える必要があるとされています。あくまで、生活形態ではなく、必要保障額から保険の要否を考えることが重要なのだと指摘されています。
誤解3:貯金が少ないから保険に入らない
日々の生活費の捻出に苦労している人なら、「保険は損」と考えるかもしれません。その場合は確かに、保険への加入により家計を圧迫しないような配慮が必要だとされています。
しかし、貯金が少なければ、万が一の事態に陥った場合、貯蓄で対処できない分を保険でカバーする必要性がむしろ高まるとされています。目先の生活とのバランスを踏まえつつ、最低限の必要保障額の確保のため、保険への加入は検討したいところだと指摘されています。
誤解4:保険はお守り
保険をネガティブに捉える方向性の誤解とは反対に、保険を過度に頼る誤解の典型として、「保険はお守り」という考え方が挙げられています。
確かに、保険への加入は精神的な安定にも繋がり、その効果も否定はできません。しかし、あくまで保険は、万が一の場合の必要保障額に備えるためのものであるとされています。
そもそも保険で、そのすべてのリスクへ完璧に備えることは不可能だとされています。あらゆるリスクを想定して、必要保障額を算定するのはナンセンスなのであり、特に医療保険は、この安心感を得るために加入しがちなので注意したいと指摘されています。
誤解5:保険は一度加入すれば安心
保険加入時にはあれこれ考えるが、加入後に見直しをする人は多いとは言えないようです。その結果、生活形態の変更などで不要となった保険にも引き続き加入し続けるケースがあるとされています。
保険は定期的な見直しが必要であり、ライフステージの変化に合わせて適切な保障内容に調整することが重要だと考えられています。
保険選びで重要なポイント
保険選びにおいて重要なポイントをまとめてみましょう。
1. 必要保障額を明確にする
実際にリスクを洗い出し、それに対してどの程度の保障が必要かを計算することが重要です。公的保障制度(健康保険や年金など)でカバーされる部分を考慮した上で、不足する部分を民間保険でカバーするという考え方が基本となります。
2. シンプルな保険を選ぶ
保険の仕組みが複雑なほど、誤解や期待と現実のギャップが生じやすくなります。シンプルで理解しやすい保険を選ぶことが重要です。
3. コストパフォーマンスを重視する
保険料と保障内容のバランスを考慮することが大切です。不要な特約は外すなど、必要最低限の保障にとどめることでコストを抑えることができます。
検索結果のネット完結型の保険会社などは、保険料の安さが魅力とされています。
4. 定期的に見直す
ライフステージの変化(結婚、出産、住宅購入など)に合わせて保障内容を見直すことが重要です。不要になった保険は解約または減額を検討するべきでしょう。
結論:保険未加入のリスクと真相
保険に入らないと「やばい」と言われる理由について、以下のようにまとめることができます。
保険未加入のリスク
- 医療保険未加入の場合
- 入院・手術など高額な医療費の自己負担
- 先進医療を受ける際の全額自己負担
- 差額ベッド代などの追加費用負担
- 健康状態悪化後に加入できなくなるリスク
- 自動車保険(任意保険)未加入の場合
- 対物賠償責任を負った際の高額負担
- 自分や同乗者のケガの治療費自己負担
- 自分の車の修理費用の全額負担
- 無保険の相手からの賠償が得られないリスク
- 社会保険未加入の場合(企業)
- 従業員からの高額賠償請求リスク
- 行政からの強制加入と遡及徴収
- ビジネス上の信用低下や不利益
保険に関する誤解
一方で、「保険は損」「独身や共働きは保険不要」といった保険に関する誤解も多く存在します。保険は損得で考えるものではなく、リスクに対する備えとして捉えることが重要です。
生命保険文化センターの2022年度「生活保障に関する調査」によれば、生命保険に加入している人は全体で、男性は77.6%、女性は81.5%となっています。この数字からも、多くの人が保険の必要性を認識していることがわかります。
適切な保険選びの重要性
保険未加入が「やばい」のと同様に、不適切な保険選びも問題となる可能性があります。過剰な保障は家計を圧迫し、不足する保障はリスクへの対応が不十分になります。
重要なのは、自分自身のリスクや必要保障額を正確に把握し、それに見合った適切な保険に加入することです。特に若い世代は、将来のライフプランを見据えた上で、必要な保障を考えることが大切です。
保険は「使わないことが最も幸せな金融商品」かもしれませんが、万が一の時に自分や家族を守るセーフティネットとしての役割は依然として重要です。「やばい」という噂に惑わされず、冷静に自分に合った保険を選ぶことが、後悔のない保険加入への道と言えるでしょう。
まとめ
保険に入らないと「やばい」と言われる理由には、実際の経済的・社会的リスクと、一部の誤解や偏った情報が混在しているようです。重要なのは、各個人や家庭の状況に応じた適切な保険選択であり、「すべての保険が必要」でも「すべての保険が不要」でもないという点です。
自分自身のリスクを冷静に分析し、必要な保障を見極めた上で、コストパフォーマンスの高い保険を選ぶという姿勢が、結果的に最も賢明な選択につながるのではないでしょうか。

