学資保険が”やばい”といわれているのはなぜ?
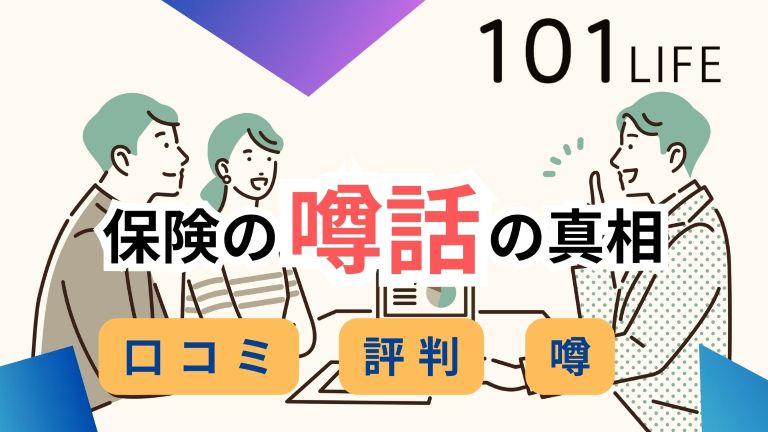
”学資保険がやばい”と口コミや評判で言われている原因と真相について掘り下げて解説します
子どもの教育資金を準備するための金融商品として広く知られている学資保険についてネットの口コミや評判から真相を掘り下げてみました。近年、インターネット上では学資保険に対して「やばい」「おすすめしない」などのネガティブな評価が見られることがあります。果たしてこれらの評価は妥当なのでしょうか、それとも誤解に基づいているのでしょうか。本記事では、学資保険の仕組みから良い評判・悪い評判までを幅広く分析し、その真相に迫ります。
学資保険の基本的な仕組み
学資保険とは、子どもの教育資金を準備することを目的とした貯蓄型保険です。親(契約者)が毎月一定額の保険料を支払い、子どもが大学進学などのタイミングで学資金を受け取る仕組みになっています。
一般的に学資保険では、子どもが契約時に定めた年齢になると祝い金や満期保険金を受け取ることができます。また、多くの場合、契約者である親に万が一のことがあった場合でも、保険料の払い込みが免除され、子どもは予定通りの学資金を受け取れるという特徴があります。
学資保険の大きな特徴として、契約者が支払った保険料の総額に対して受け取ることのできる「満期保険金 + 祝い金」の割合(返戻率)が、一般的に100%以上になるとされています。ただし、複数の特約を付けると返戻率が100%を下回る場合もあるようです。
“やばい”と言われる主な理由
インターネット上では学資保険に対して「やばい」「おすすめしない」という評価が見られることがあります。その主な理由として以下のような点が挙げられているようです。
1. 途中解約による元本割れリスク
学資保険は満期より前に解約をすると、「元本割れ」が起きる可能性が高いと言われています。預貯金の場合、途中でやめても損をすることはありませんが、学資保険の場合は解約返戻金が支払った保険料より下回り、元よりも少ないお金しか手元に戻らないリスクがあるようです。
ある事例では、家計が苦しくなったために学資保険を途中で解約せざるを得なくなった方が、元本を大きく下回る金額しか受け取れなかったということが報告されています。これは学資保険が保険料払い込み期間中に解約すると、解約返戻金は払込保険料の総額を下回る仕組みになっているためのようです。
2. インフレに対する脆弱性
学資保険は固定金利で運用するため、インフレの恩恵を受けることができないとされています。インフレが進むと物価が上昇し、教育費も増加する可能性がありますが、学資保険の満期保険金や祝い金は契約時に決まった金額のままであり、増額されることはありません。
ある事例では、子どもの大学進学費用に備えて20年後に200万円受け取れる学資保険に加入したものの、予想以上にインフレが進んだことで実際に必要な費用が300万円になり、不足が生じたというケースが報告されています。
3. 保険会社の破綻リスク
保険会社が破綻した場合の保障についても懸念が示されています。金融機関が破綻した場合、預貯金は預金保険機構により一般預金等は元本1,000万円まで全額保護されますが、保険会社が破綻した場合には「生命保険契約者保護機構」が保険金や給付金の支払いを行うものの、補償の範囲は責任準備金の9割までとなるようです。可能性は低いかもしれませんが、ここにも元本割れするリスクがあると指摘されています。
4. 資金の流動性の低さ
学資保険で払込んだ保険料は途中で自由に引き出すことができないという点も、デメリットとして挙げられています。金融機関での預貯金と違って、急にお金が必要になった場合に対応が難しいとされています。
一方で、この特徴は自由に引き出せない不便さがある反面、払込期間の途中で安易に使ってしまう心配が少ないため、確実に教育資金を準備できるという見方もあるようです。
5. 返戻率の誤解
学資保険を選ぶ際に最も気にされるポイントとして「返戻率」が挙げられていますが、この返戻率に対する誤解も「やばい」と評価される一因になっているようです。
返戻率は支払った保険料の総額に対して受け取れる保険金の総額を示すものですが、時間の価値を考慮していないため、実質的な利回りは低いとされています。例えば、返戻率が同じ100%でも、明日受け取れる100円と10年後に受け取れる100円では価値が異なりますが、返戻率だけではこの違いが見えてこないと指摘されています。
ある分析によれば、返戻率108%の学資保険と返戻率109%の学資保険を比較した場合、実際の年間利回りはそれぞれ0.743%と0.444%と大きな差があったとのことです。
6. 税金による手取り減少
学資保険の受取時に税金が引かれることで、手元に残る金額が予想より少なくなることもあるようです。ある事例では、高い返戻率に魅力を感じて加入したものの、受取時に税金が引かれることを知らず、思ったよりも手元に残る金額が少なくなってしまったというケースが報告されています。
7. 営業方法への不満
学資保険の加入を相談しに行ったところ、いつの間にか別の保険を勧められていたというケースも報告されています。保険会社側の都合で終身保険など他の保険商品を勧められることがあり、これが不信感につながっている可能性があるようです。
学資保険の良い評判・メリット
一方で、学資保険には良い評判もあり、多くの家庭で利用されています。そのメリットとして以下のような点が挙げられています。
1. 計画的な教育資金の準備
学資保険はコツコツと自分で貯金するのが苦手な人にとって、確実に子どもの教育資金を作ることができるという点で安心だとされています。毎月一定額の保険料を支払うことで、着実に教育資金を積み立てることができるようです。
2. 保険料払込免除特約
学資保険の大きな特徴として、契約者(親など)に万が一のことがあった場合、保険料の払い込みが免除になるという点が挙げられています。たとえ1年分しか保険料を支払っていなくても、契約者に万一のことがあれば、その後の保険料は免除され、子どもの年齢に応じた学資金が受け取れるというのは、大きな安心だとされています。
預貯金で教育資金を積み立てる場合は、保護者に万が一のことがあると、積み立てを継続するのが難しくなる可能性がありますが、学資保険ならその心配がないとされています。
3. 税制優遇
学資保険の保険料は、所得税・住民税額の計算において生命保険料控除の対象となり、2012年以降の契約の場合、所得税で最大4万円、住民税で最大2万8,000円が、契約者のその年の所得から差し引かれるようです。預貯金にはない税制上のメリットが得られる点が評価されています。
4. 高評価を受ける学資保険商品
2025年のオリコン顧客満足度調査では、東京海上日動あんしん生命が学資保険部門で総合1位を獲得しています。ソニー生命やアフラックも高評価を受けており、実際に利用したユーザーからは「支払いまでのスキームが簡単」「何年かごとにまとまった祝金があるのが将来助かりそう」などの声が寄せられているようです。
また、富国生命の「みらいのつばさ」は特に評判が良く、「ママリ口コミ大賞2023」学資保険部門で大賞を受賞したという報告もあります。兄弟割や貯金するよりも高い利率に満足したという声も聞かれるようです。
学資保険に関する実態
NTTコム リサーチの調査によれば、10歳未満の子どもがいる人のうち、学資保険に加入しているのは57.2%で、半分以上を占めています。年代別では20代の加入率が最も高く63.4%となっています。
学資保険に加入したきっかけは「必要性を感じていたので」が最も多く84.1%を占めており、未加入者でも「学費のために預貯金をしているから」(35.6%)、「必要だと思うが保険料を支払う余力が無いから」(31.5%)といった理由が上位に挙げられています。これらから、学資保険の加入・未加入を問わず、小さな子どもを持つ家庭では学費に備える必要性を認識していることがわかるようです。
学資保険を選ぶ際に重視しているポイントについては、1位は「返戻率」で、金融商品としての価値を求められているといえるようです。また、学資保険を選ぶ際に複数商品を比較検討している人は約6割で、その情報源として最も多いのは「インターネット」(約5割)となっています。
学資保険に対する誤解と真相
学資保険が「やばい」と評価される背景には、いくつかの誤解や期待と現実のギャップがあるようです。
誤解1:学資保険は詐欺である
学資保険そのものには違法性も詐欺の要素もなく、合法的な金融商品です。しかし、契約内容が複雑であったり、十分な説明がなされないまま契約に至ったりすることで、「だまされた」という印象を持つケースがあるようです。
誤解2:必ず元本割れする
学資保険は満期まで継続すれば、一般的に返戻率が100%以上となり、元本割れしないと言われています。ただし、途中解約した場合や特約を多く付けた場合には元本割れする可能性があるようです。
誤解3:学資保険は万能である
学資保険は教育資金を準備するための一つの選択肢に過ぎず、万能ではないと言われています。インフレリスクや途中解約リスクなどのデメリットも考慮し、自分の状況に合った教育資金準備方法を検討することが重要だとされています。
どんな人に学資保険が向いているか
学資保険は以下のような人に向いているとされています。
- 自分で貯金するのが苦手な人
- 契約者(親)に万が一のことがあった場合の保障を重視する人
- 長期間にわたって継続的に保険料を支払える余裕がある人
- 税制優遇のメリットを活用したい人
一方、以下のような人には向いていない可能性があるとされています。
- 途中で資金が必要になる可能性がある人
- より高い運用利回りを期待している人
- インフレリスクに備えたい人
- 柔軟な資金運用を希望する人
学資保険選びのポイント
学資保険を検討する際には、以下のポイントを押さえることが重要だとされています。
- 返戻率だけでなく実質的な利回りも確認する
- 途中解約した場合の解約返戻金についても把握しておく
- 保険料払込期間と満期金受取時期が自分のライフプランに合っているか確認する
- 特約を付ける場合は、その分返戻率が下がることを理解しておく
- 複数の保険会社の商品を比較検討する
- 税金の影響も考慮する
まとめ:学資保険の真相
学資保険が「やばい」と評価される理由は、主に商品性の理解不足や期待と現実のギャップ、あるいは自分の状況にマッチしない使い方をした場合のデメリットが大きく取り上げられていることにあるようです。
学資保険自体は違法でも詐欺でもなく、適切に理解して利用すれば子どもの教育資金準備に役立つ金融商品の一つと言えるでしょう。ただし、インフレリスクや途中解約時の元本割れリスク、資金の流動性の低さなどのデメリットもあるため、自分の状況やニーズに合っているかどうかを十分に検討することが重要です。
また、学資保険だけに頼るのではなく、預貯金や投資など他の資産形成手段と組み合わせることで、よりバランスの取れた教育資金準備が可能になるかもしれません。
最終的には、複数の選択肢を比較検討し、自分の状況に最も適した方法で子どもの教育資金を準備することが大切だと言えるでしょう。インターネットの情報だけでなく、必要に応じて専門家にも相談しながら、納得のいく選択をすることが望ましいとされています。
いずれにせよ、子どもの将来のために計画的に教育資金を準備するという意識自体は非常に重要であり、学資保険はそのための一つの選択肢として検討する価値があるのではないでしょうか。
学資保険の最新トレンド
最近の学資保険市場では、従来の学資保険の課題を解決するような新しいタイプの商品も登場しています。例えば、柔軟な受取時期設定が可能な商品や、インフレに対応するための機能を持つ商品なども見られるようです。
2025年のオリコン顧客満足度調査によれば、東京海上日動あんしん生命が総合1位、ソニー生命とアフラックが2位タイを獲得しており、各社とも顧客ニーズに合わせた商品開発を進めているようです。
また、保険会社だけでなく、銀行や証券会社なども教育資金準備のための商品を提供しており、消費者の選択肢は広がっているとされています。
学資保険を含む教育資金準備の方法は、今後も社会環境や経済状況の変化に応じて進化していくことが予想されます。常に最新の情報を収集し、自分のニーズに合った選択をすることが大切だと言えるでしょう。
教育は子どもの将来を左右する重要な投資です。それを支える教育資金の準備方法についても、十分な検討と理解を深めることが、子どもの可能性を広げることにつながるのではないでしょうか。

