国民健康保険が”やばい”といわれているのはなぜ?
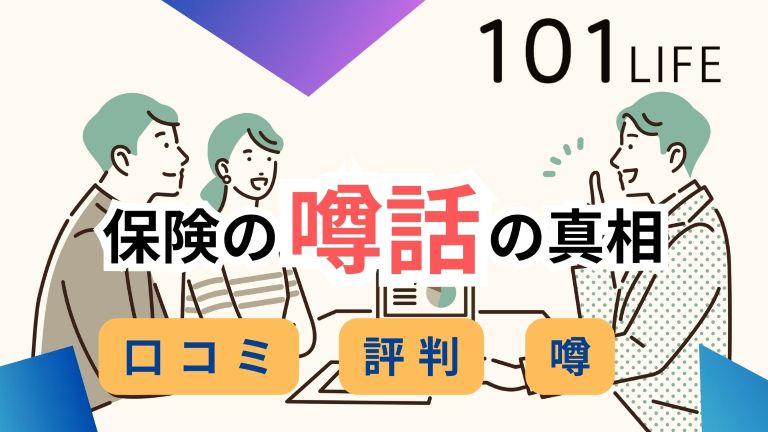
”国民健康保険がやばい、高すぎて払えない”と口コミや評判で言われている原因と真相について掘り下げて解説してみました
国民健康保険が”やばい”といわれる現状についてネットの口コミや評判から真相を掘り下げてみました。保険料の高さや滞納者の増加、財政悪化など様々な問題が指摘される一方で、それらが誤解に基づくものなのか、また国民健康保険の良い面はないのかについても調査しました。日本の医療保障の根幹を支える国民健康保険制度の実態と課題について、多角的な視点からご紹介します。
国民健康保険の現状と基本的な仕組み
国民健康保険(以下、国保)は、国民皆保険の中核的役割を担うとともに、医療のセーフティネットとして国民の健康を支えている制度です。もともとは農林水産業や自営業を中心として発足しましたが、現在では無職や非正規雇用などの低所得者の割合が増えてきているようです。
国保は各市町村が運営する医療保険で、自営業者とその家族、無職の世帯などを対象としています。現在は全世帯の4割にあたる約2000万世帯、約3600万人が加入していると言われています。
しかし近年、この国保をめぐっては「やばい」という評判が広がっているようです。では、なぜ国保が「やばい」と言われているのでしょうか。
国民健康保険が”やばい”と言われる主な理由
1. 保険料の高さと負担感
国保が「やばい」と言われる最大の理由は、その保険料が高すぎる点にあるようです。特に年収に対する負担割合の大きさが多くの批判を集めています。
ある事例では、2021年度の国保料が約88万円で、前年(2020年)の所得約640万円(年収は890万円)をもとに算出されていたとのことです。この場合、年収の約10%が国保料として徴収されることになります。
「いま国保に加入している者の生の声をお伝えしたい。はっきり言って泣き言だ。だが本当に保険料が高い。低所得者はもちろん、年収1000万円以下は所得の1割以上の保険料を支払っているわけだから、誰にとっても重すぎる負担なのだ」という声もあります。
国保の1世帯当たり平均保険料は、2009年度時点で年約14万8000円でした。低所得世帯には軽減措置がありますが、それでも負担感が重いことが多く、滞納の原因になっているようです。
「1年に1、2回しか病院に行っていないのに、保険料は月に約10万円の支払いでしょう。さすがに高いですよ。僕が保険証を返したい、自由診療がいいと言うと、窓口では『日本は皆保険制度ですから、保険証を返されても困ります。相互扶助、つまり助け合いの仕組みなんです』と繰り返し言われました」という声もあります。
2. 前年所得ベースの算定方法の問題
国保料が高いと感じる理由の一つに、前年の所得をもとに保険料が算定される仕組みがあるようです。特にフリーランスや自営業者にとっては、年ごとの収入変動が大きいため、この仕組みが負担感を増している場合があるとの指摘があります。
「特にフリーランスをはじめ自営業者は、今年の収入を来年も得られる保証はどこにもない。保険料を安定的に徴収するためにも、せめて『前年度の収入をもとに国保料を算定する』仕組みを見直す必要があるのではないかと思う。翌年の収入の目処がたちにくいのだから、該当する年度から引かれるほうがいい」という意見もあります。
税理士の服部修氏も、「国保料も所得税のように源泉徴収を取り入れるべきです」と提言しているようです。
3. 国保財政の悪化と市町村の負担
国保は高齢層の増加による医療費の上昇のため、国保特別会計が赤字となる市町村が続出しているという状況があります。
全国の市町村で、赤字の穴埋めなどのため住民の税金が年約3600億円も投入されているが、それでも半数以上は赤字だというデータもあります。
被保険者数の減少は、国保内の高齢化を促進し、一人当たり医療費を高めるという負のスパイラルに陥っているようです。
4. 滞納の増加と制裁措置
国保では、保険料の滞納が深刻な問題となっています。保険料収納率は、2009年度に88.01%と過去最低を更新したとの報告があります。
滞納が長引くと、市町村はそれまでの保険証の代わりに、有効期間が数か月の「短期保険証」を発行します。更新のため窓口に来る回数を増やし、納付を促すのが狙いだと言われています。
それでも滞納が続くと、保険証を回収し、「資格証明書」を渡されます。そうなると、高校生以下の子どもを除けば、医療機関の窓口でかかった費用をいったん全額払わなければならなくなります。この結果、病気になっても受診しにくくなり、重症化するケースも問題になっているようです。
5. 行政側の問題(試算誤りなど)
国保に関しては、行政側の対応にも問題が指摘されています。例えば、区役所での国民健康保険料の試算誤りによる賠償事例が報告されています。
ある事例では、会社を辞めた市民が、国民健康保険に入るべきか、任意継続で社会保険を続けるべきか悩み、区役所の国民健康保険の窓口で保険料の試算について相談しました。職員が収入を聞き取り、所得減少による減免が適用された場合の試算した概算保険料を書面で提示したため、その市民は国民健康保険の方が安かったので加入しました。しかし、実際には職員の試算が誤っていたため、任意継続より10万円以上も負担額が大きくなってしまったとのことです。
また、「会社を退職後に国民健康保険に加入した方は申請により保険料の減免を受けることができますが、その減免は1年限り有効であり、次年度は再度申請する必要があるそうですが、最初に職員がその説明をしていないケースや、職員が忙しいとの理由で減免をしていない方に減免申請の通知を送らないケースが多々あり、かなりの人が翌年度減免申請をせずに損をしていると聞きました」という市民の声もあります。
国民健康保険に関する誤解と実態
国民健康保険が「やばい」と言われる背景には、様々な誤解も存在しているようです。
1. 「助け合いの仕組み」という誤解
「相互扶助、助け合いの仕組み」という説明に対して、佛教大学社会福祉学部准教授の長友薫輝氏は「よく誤解されるのですが、国保は”助け合い”で運営しているわけではありません」と述べています。
「例えばテレビコマーシャルでおなじみの民間保険は、サービスを受けたいのであれば保険料を納めなさいという保険原理ですよね。しかし国保を含む公的医療保険、年金保険、雇用保険、労災保険、介護保険の5つは社会保険といわれ、個人への保険料だけでなく、事業主にも負担を求め、国が公費を投入し、運営に責任をもつ、国民に加入を義務づけるという面も持ち合わせます。これは自己責任や家族・地域の助け合いだけでは対応できない貧困、病気、失業などのさまざまな問題に対して、社会的施策で対応していきましょうということなのです。ですから加入者に”助け合い”ばかりを強調して過酷な負担を強いるのは、社会保険として考えた時に問題なのです」と長友氏は説明しています。
2. 外国人の不正利用に関する誤解
国保に関しては、外国人による不正利用が多いという報道もありますが、実態は異なるようです。
ある報道では、外国人が国民健康保険に加入して半年以内に80万円以上の高額な治療を受けたケースが、1年間に1,597件あったと報じられました。しかし、厚生労働省の調査によれば、「不正な在留資格による給付である可能性が残るもの」はわずか2名(他に出国により確認できなかったものが5名)しか確認されなかったとのことです。
外国人年間レセプト総数(推計)は14,897,134件であることを考えると、「偽りの手段で在留資格を取得し、高額の治療を受けている」事案はほとんど確認されていないということになります。
3. 地域格差の問題
国民健康保険では、保険給付費等に応じた保険料を各市町村において設定しますが、医療費と保険料の地域格差が大きく、被保険者間の公平性の観点から問題となっているという指摘もあります。
国民健康保険の良い面や評判
国保に対しては厳しい意見が多く見られますが、良い評判や支持する声もあります。
1. 医療のセーフティネットとしての役割
国民健康保険は、国民皆保険の中核的役割を担うとともに、医療のセーフティネットとして国民の健康を支えています。
特に無職や低所得者、非正規雇用の労働者など、職場の健康保険に加入できない人々にとっては、最後の砦となる重要な制度であると言えるでしょう。
2. 業務として関わる良さ
国民健康保険団体連合会で働いた経験のある方からは、「レセプトの審査をしていましたが、主に算定の知識や一部負担金の計算方法、請求方法を仕事をしながら学べるので、私にとってはそこはとても良い職場でした。特に一部負担金の求め方など、難しいものができたときの達成感は大きかったです」という声も聞かれます。
国民健康保険の問題に対する解決策や代替手段
国保の問題に対して、いくつかの解決策や代替手段が模索されています。
1. 社会保険削減サービスの存在
フリーランスや個人事業主向けに、国民健康保険より負担の少ない形で社会保険に加入できるサービスが登場しています。「国社保険料リサーチ」や「社保サポ」などと呼ばれるこれらのサービスについて、「扶養家族含めて、社会保険料が定額43,906円になる」「厚生年金に加入できる」「所得税・住民税も下がる可能性がある」などのメリットが紹介されています。
利用者からは「国民健康保険に毎月25,000円以上支払っている方や扶養家族がいる方は絶対お得です、是非お問合せを!」「もっと社保サポ早く知りたかった。。税金だけでもつらいのに国保支払いかなりへりました」などの声が寄せられているようです。
ただし、こうしたサービスについては「グレーゾーンであるリスクを含む」との指摘もあります。「仕組み上の理屈は社会保険が削減できますが、少々グレーゾーンであるリスクを含むことは理解しておきましょう」「マイクロ法人を使わせてもらうような手法ですから」と注意喚起されています。
2. 民間医療保険との組み合わせ
国保の補完として、民間の医療保険に加入するという選択肢もあります。2025年のオリコン顧客満足度調査による医療保険ランキングでは、楽天生命が総合1位という結果となっています。
利用者からは「退院後の保険金申請に際し、とてもスムーズに手続きが完了し、メールではありましたが、都度確認の連絡があり、とても助かりました」「ネットで全て完結。診断書もいらず保険請求が出来、入金も早かった。わからない事は担当者に電話で聞けたし丁寧だった」といった評価の声が寄せられています。
ただし、生命保険に関しては「やばい」という評判もあり、その背景には営業方法の問題、保険商品の複雑さ、誤解や勘違い、期待と現実のギャップなど、様々な要因が絡み合っているようです。
3. 制度改革への期待
国保の問題を解決するためには、制度自体の改革も必要だという声が多く聞かれます。前述の税理士・服部氏の「国保料も所得税のように源泉徴収を取り入れるべき」という提言や、前年所得ベースの算定方法の見直しなどが挙げられています。
また、「国保料の減免は直近3ヵ月の収入や家賃の金額などトータルで判定しますが、生活保護を受けられるかどうかというほど困窮している世帯が対象になります」という現状に対して、もう少し基準を緩和してほしいという声もあります。
様々な世帯の国保加入実態
国民健康保険の加入者の構造は、産業構造の変化や人口の高齢化等によって大きく変化しているようです。その象徴的な現象が、国民健康保険加入世帯における所得無し世帯や無職世帯の割合の増加だとされています。
所得無し世帯の分析によると、世帯主が高年齢である世帯の割合が高く、その中では女性単独世帯の割合が高くなっているという特徴があるようです。高齢女性の単独世帯の所得の状況をみると、公的年金に依存する割合が高く、それ以外の所得のウエイトは小さいとされています。
「高齢女性の単独世帯が多いというのは、女性の平均寿命が男性よりも長いことから、もともとは夫婦のみであったものが夫が先に死亡するケースが多く、かつ、そういった場合、自分の老齢基礎年金を受給するとともに、夫が加入していた年金制度によってはさらに遺族年金を受給することになるが、遺族年金は国民健康保険税(料)課税対象所得からは除外され、老齢基礎年金は公的年金等控除を行うとゼロとなることによって、国民健康保険制度としては所得無しとなる」というメカニズムが指摘されています。
今後、さらに高齢化が進行するとともに、国民健康保険加入世帯の中で、高齢女性の単独世帯がますます増加していくことが予想されるため、国民健康保険制度のあり方、特に保険料負担のあり方を考える上でこういった状況も考慮する必要があると考えられています。
国民健康保険の職場環境に関する評判
国民健康保険に関連する職場環境についても、様々な声が聞かれます。
兵庫県国民健康保険団体連合会の社員からは、「人間関係が劣悪。虐め、パワハラ多い。中途採用の正規職員をみんなで暗に虐めて辞めさせるような組織でした。女性の管理職が多く、管理職が職員や非正規のアルバイトを日常的に虐めている。女性管理職だからセクハラは無くてもパワハラがとても多いです」という厳しい評価もあります。
一方で、「レセプトの審査をしていましたが、主に算定の知識や一部負担金の計算方法、請求方法を仕事をしながら学べるので、私にとってはそこはとても良い職場でした」というポジティブな声もあります。
東京土建国民健康保険組合に関しても、「非常に幼稚な人が多かった印象。ロジカルシンキングができる人が少なかったと思う」という批判的な意見がある一方、「健康保険証は協会けんぽ。特に手厚い福利厚生があるわけではない」といった声もあります。
無保険の危険性
国民健康保険料が高いからといって、保険に加入しないという選択は非常に危険です。無保険状態でいることのリスクについて見ていきましょう。
無保険とは「自賠責保険に加入しているが、任意保険に未加入の状態」や「自賠責保険、任意保険の両方とも未加入の状態」を指しますが、健康保険においても無保険状態は様々なリスクをもたらします。
加入が義務付けられている健康保険に未加入の場合、病気やケガをした際に医療費を全額自己負担しなければならなくなります。高額な医療費がかかる治療を受けた場合、経済的な負担が非常に大きくなる可能性があります。
国民健康保険は高いと感じる人も多いですが、無保険でいることのリスクと比較すると、保険に加入するメリットは大きいと言えるでしょう。
国民健康保険二重加入の問題
国民健康保険と社会保険の二重加入問題も存在します。ある事例では、「ある会社に正社員として採用されることにより国民健康保険から脱退し社会保険に加入する予定だった。しかし、事情により正社員ではなく短時間のパート契約に変更したので、結局は社保に加入せず国保を継続したままだった。ところがある日、市から『国民健康保険の資格確認について(社会保険等との重複加入確認)』という書面が届いた」というケースが報告されています。
二重加入を避けるため、就職や退職の際には適切な手続きを行うことが重要です。
結論:国民健康保険の真相
国民健康保険が「やばい」と噂される背景には、保険料の高さや前年所得ベースの算定方法、国保財政の悪化、滞納の増加、行政側の対応問題など、様々な要因が存在しているようです。
特に保険料の負担感については、年収の1割超が保険料として徴収されるケースもあり、多くの加入者にとって大きな負担となっていることが伺えます。
一方で、「助け合いの仕組み」という説明や外国人の不正利用に関する報道など、誤解に基づく批判も存在しています。国保は単なる「助け合い」ではなく、国が公費を投入し運営に責任を持つ社会保険制度であり、外国人の不正利用も実際にはごく少数であることが指摘されています。
国保には、国民皆保険の中核としての役割や医療のセーフティネットという重要な機能があります。特に職場の健康保険に加入できない人々にとっては、最後の砦となる制度です。
問題解決のためには、社会保険削減サービスの利用や民間医療保険との組み合わせといった個人レベルの対策だけでなく、源泉徴収方式の導入や前年所得ベースの算定方法の見直しなど、制度自体の改革も必要だという声が多く聞かれます。
今後さらに高齢化が進行する中で、国民健康保険加入世帯の構造も変化していくことが予想されます。特に高齢女性の単独世帯の増加など、社会構造の変化を踏まえた制度設計が求められているようです。
国民健康保険は確かに課題を抱えていますが、無保険でいることのリスクを考えると、保険に加入することの重要性は変わりません。制度の持続可能性を高めつつ、加入者の負担感を軽減するバランスの取れた改革が望まれます。
参考文献
本記事は、信頼性の高い情報源に基づいて作成していますが、個別の状況によって適用される内容は異なる場合があります。国民健康保険に関するお問い合わせは、お住まいの地域の窓口にご相談ください。

