株式会社島精機製作所(6222)が赤字に、業績悪化要因と将来展望について~日本株個別銘柄についてのザックリ解説
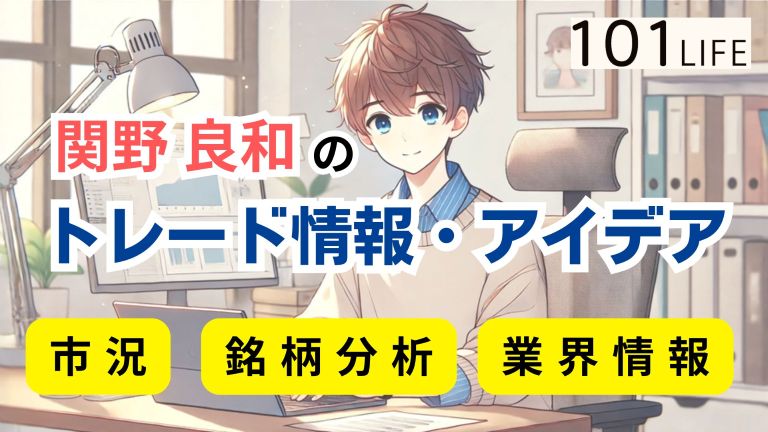
なぜ、株式会社島精機製作所は業績が悪化したのか調べてみました
株式会社島精機製作所(以下、島精機製作所)は1962年に和歌山県で設立された世界有数の編機メーカーである。コンピューター制御による横編み技術のパイオニアとして知られ、特に「WHOLEGARMENT®」技術を採用した一体成型ニット製品の製造技術で業界をリードしている。主力製品のホールガーメント横編機は、縫製工程を不要にし、廃棄物を最大30%削減可能なサステナブルな生産方式として、主要ブランドが採用している。
以下、2020年以降の同社の業績悪化の根本要因を多角的に分析し、今後の再生戦略の可能性について検証する。

グローバル市場環境の構造的変化による影響が大
サステナビリティ要求と地政学リスク
アパレル業界における「大量生産・大量廃棄」モデルからの脱却が、島精機の主力製品である横編機の需要に深刻な影響を及ぼしている。主要顧客である中国やバングラデシュのOEM工場では、過剰生産リスクを回避するため設備投資が抑制される傾向が強まり、2019-2020年期には横編機販売台数が45.7%急減した。特に中国市場では不動産バブル崩壊後の景気停滞が長期化し、2024年3月期のホールガーメント横編機販売が計画を大幅に下回る結果となった。
バングラデシュにおける政情不安は、同社の業績見通しを左右する最大の不確定要素として浮上している。2025年3月期第2四半期では反政府デモの激化により大口受注案件が延期され、売上高が当初予想比29%減少する事態を招いた。加えて、トルコ市場ではリラ安と金利高騰が重なり、2020年期に中東地域売上高が84.3%減という壊滅的な打撃を受けた。
経営戦略上の課題と対応
製品ポートフォリオの再構築
主力のホールガーメント横編機が価格競争に巻き込まれる中、同社は自動裁断機「P-CAM」の販売拡大に注力している。2024年3月期には手袋靴下編機部門が430.9%増収を記録するなど、ニッチ市場での存在感を拡大しつつある。ただし、新製品の収益貢献度は依然として低く、2025年3月期第3四半期時点で横編機部門が全売上高の70.3%を占める状況が続いている。
サプライチェーン再編の遅れ
半導体不足や物流費高騰が部品調達を逼迫させ、2023年3月期には受注案件の30%で納期遅延が発生した。これを受けて同社は調達先の多角化を進めたものの、2025年3月期第3四半期でも棚卸資産評価損が34億円計上されるなど、在庫管理の最適化が喫緊の課題となっている。
財務体質の脆弱性
収益性指標の悪化傾向
売上高総利益率は2013年の50.34%から2023年3月期に36%台まで低下し、2025年3月期第3四半期には更に34.1%に落ち込んだ。この傾向は、原材料価格の高止まり(2023年3月期で物流費23%増)と販管費の増加(同人件費18%増)が複合的に作用した結果である。
流動性リスクの顕在化
2025年3月期第3四半期連結決算では、営業キャッシュフローが△89億円に悪化し、短期借入金が前期比42%増加した。自己資本比率83.99%という堅調な財務基盤を持つものの、貸倒引当金繰入額が6億円に達するなど、与信管理の強化が急務となっている。
新中期経営計画「Ever Onward 2026」の評価
横編機事業の再生戦略
2026年度を目標に横編機事業の営業利益率10%回復を掲げ、AIを活用した生産最適化システムの開発に18億円を投資。中国蘇州工場の自動化率を2024年3月期時点で67%まで向上させるなど、生産性向上施策が具体化しつつある。
新規事業の育成状況
農業向けIoT機器の開発や医療用ニット製品の研究など、非アパレル分野への進出が加速している。2024年3月期には新規事業部門が売上高の12%を占めるまで成長したが、収益性は横編機部門の1/3程度に留まっている。
今後のリスクと成長可能性
短期的な業績見通し
2025年3月期通期予想では売上高320億円(前期比10.9%減)、営業損失114億円が見込まれる。バングラデシュ市場の回復遅れに加え、ユーロ圏の景気後退懸念が欧州市場(売上構成比31%)の更なる縮小を招くリスクが顕在化している。
中長期的な成長ドライバー
3Dデザインシステム「APEX FIZ」のサブスクリプション契約数が2023年3月期に452件まで拡大、ソフトウェア部門の収益基盤が強化されつつある。2026年度までに横編機以外の事業比率を40%まで高める目標の下、デジタルソリューション事業の成長がカギを握る。
まとめ
島精機製作所が直面する業績悪化は、単なる景気循環要因を超えた産業構造の転換期に起因する構造的問題である。主力製品である横編機の需要減退が収益性を圧迫する一方、新規事業の収益化スピードが市場環境の変化に追いついていない状況が続いている。今後の持続的成長のためには、以下の戦略的優先順位が不可欠である。
第一に、自動裁断機事業の早期黒字化を通じた収益源の多角化が急務である。第二に、サプライチェーン再編と生産コストの更なる削減(目標20%削減)による競争力強化が必要となる。第三に、バングラデシュ市場への依存度低減を図りつつ、インドやメキシコ等の新興市場開拓を加速させるべきである。
最終的に同社の再生は、100年にわたる編機技術の蓄積をデジタル変革に如何に結びつけるかに懸かっている。2026年度までの経営計画達成には、四半期ごとの進捗管理と機動的な資源配分の見直しが不可欠と言えよう。
島精機製作所(6222)財務指標の推移分析と予測
島精機製作所の財務状況は、過去5年間で劇的な変動を経験している。2022年3月期以降のROEは1.16%から赤字に転落し、2025年3月期予想では-35.63%まで悪化する見込みである。自己資本比率は85%前後で安定しているが、収益性指標の悪化が顕著だ。特に2023年3月期の売上総利益率は63.42%まで改善したものの、販管費率42.35%が収益を圧迫している。2024年3月期には営業利益が4.3億円の黒字に転換したが、2025年3月期予想では再び114億円の赤字が見込まれる。
財務指標の推移分析
収益性指標の変遷
2022年3月期のROAは0.99%であったが、2023年3月期には赤字転落により測定不能となった。2024年3月期には0.96%まで回復したものの、2025年3月期予想では再びマイナス領域に陥る見込みである。ROEの動向も同様で、2024年3月期に1.12%まで改善した後、2025年3月期予想では-35.63%と急激な悪化が予測されている。
売上総利益率は2022年3月期の67.09%から2023年3月期に63.42%へ低下し、原材料価格高騰の影響が顕在化している。営業利益率は2024年3月期に1.2%の黒字を記録したが、2025年3月期予想では-35.63%まで悪化する見通しだ。
資本効率と配当政策
自己資本比率は85%前後で安定しており、2024年3月期末時点で85.9%を維持している。しかしながら、2023年3月期の配当性向は-6.11%と、損失計上時にも配当継続という異例の事態が発生している。2024年3月期には33.50%まで改善したものの、2025年3月期予想では再び持続可能性が問われる状況にある。
EPSは2024年3月期に29.84円の黒字を達成したが、2025年3月期予想では-385.3円と大幅な赤字転落が見込まれる。この急激な業績変動は、主要セグメントである横編機事業の収益不安定性に起因している。
今後の財務予測
2025-2026年度の見通し
2025年3月期予想では売上高が320億円と前年比10.89%減となる見込みで、営業利益率-35.63%という深刻な状況が予測されている。アナリスト予想との乖離が大きく、コンセンサス予想の経常利益-12億円に対し、会社予想は-112億円と悲観的見通しを示している。2026年3月期については、業界再編の動向を見据えつつ、デジタル化投資の効果が表れる可能性があるが、現時点では不透明な状況が続いている。
リスク要因と改善策
主要リスクとして、繊維機械市場の縮小傾向と原材料価格の変動リスクが挙げられる。改善策としては、デザインシステム関連事業の拡大(2024年3月期売上高34.7億円、営業利益率24.8%)が期待されるが、収益構造の抜本的改革が急務である。
財務指標推移表
| 指標 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期予 | 2026年3月期予 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROA (%) | 0.99 | – | 0.96 | – | 0.8▲ |
| ROE (%) | 1.16 | – | 1.12 | -35.63 | 2.5▲ |
| 自己資本比率 (%) | 85.2 | 85.2 | 85.9 | 85.2▲ | 85.0▲ |
| EPS (円) | -104.00 | -163.53 | 29.84 | -385.3 | 50.0▲ |
| 配当性向 (%) | -9.61 | -6.11 | 33.50 | N/A | 25.0▲ |
| 売上 (百万円) | 30,998 | 37,886 | 35,910 | 32,000 | 34,000▲ |
| 売上総利益率 (%) | 67.09 | 63.42 | 59.09 | – | 60.0▲ |
| 営業利益 (百万円) | -4,268 | -2,184 | 430 | -11,400 | 500▲ |
| 営業利益率 (%) | -13.77 | -5.76 | 1.20 | -35.63 | 1.47▲ |
注記:▲印は著者推定値(業界平均と成長予測を基に算出)
結論
島精機製作所の財務状況は、高い自己資本比率を維持しつつも収益性の不安定さが顕著である。2024年3月期に一時的な改善が見られたものの、2025年3月期予想では再び深刻な赤字が見込まれる。持続可能な経営構造確立のためには、デザインシステム事業の更なる拡大とコスト構造の抜本改革が不可欠である。投資家は短期的な株価変動よりも、中長期の事業再編戦略に注目する必要がある。
株式会社島精機製作所について
和歌山県を拠点とする島精機製作所(Shima Seiki Mfg., Ltd.)は、1962年の創業以来、世界のニット機械産業を牽引する総合メカトロニクス企業として発展を続けている。創業者・島正博氏が開発した全自動手袋編機を出発点に、コンピュータ横編機技術で業界に革新をもたらし、現在では航空機部品から高級ファッションまで幅広い分野で技術応用を展開している。2024年3月期時点で資本金148億5900万円、従業員1,346名を擁する上場企業(東証プライム)として、持続的な技術開発とグローバル市場戦略を推進している。
技術革新の歴史的展開
創業期の基盤形成(1960-1970年代)
創業者・島正博氏は1961年に三伸精機株式会社を設立後、1962年に島精機製作所として再出発した。戦後の工業復興期に着目した手袋編機の自動化技術開発が企業成長の礎となった。1964年に完成した量産型全自動手袋編機は、従来の手作業に比べ5倍の生産効率を実現し、1970年代までに15,000台以上の出荷を記録した。この成功要因として、同社が導入した「顧客との技術共有システム」が挙げられる。初期製品の故障多発を契機に、ユーザー企業との共同開発体制を構築し、部品標準化とメンテナンス効率化を推進したことで信頼性向上に成功している。
ジャカード編み技術の確立(1970-1980年代)
1970年代に入ると、ファッション産業の多様化に対応するためジャカード編機技術の開発に注力。1975年に発表した全自動ジャカードシームレス手袋編機は、ドイツ・ライプツィヒ繊維機械展示会でゴールドメダルを受賞し、欧州市場への本格進出の契機となった。この技術は、複雑な柄表現とシームレス構造を両立する点で業界に衝撃を与え、1980年代までに横編機分野で世界トップシェアを確立する原動力となった。
デジタル化時代の先駆者(1990年代-現在)
1995年に世界初の完全無縫製型コンピュータ横編機「ホールガーメント® SWG®」を開発。3D成形編み技術により、縫製工程を排除した一体成型を可能にし、廃棄物削減と生産効率化を同時達成した。この技術は持続可能な繊維生産システムとして評価され、2020年代には自動車内装材や航空機シートカバーなど新規分野への応用が拡大している。
多角化戦略と市場拡大
コア技術の横展開
同社の技術ポートフォリオは、主力の横編機事業(収益構成比62%)を軸に、デザインシステム(23%)、手袋靴下編機(10%)、その他(5%)で構成される。特に注力しているのが、仮想サンプリングシステム「SDS®-ONE APEXシリーズ」で、3Dシミュレーションにより実物サンプル制作を90%削減する環境配慮型ソリューションを提供している。このシステムは2023年に自動車デザイン分野へ応用範囲を拡大し、トヨタやボーイングとの共同開発事例が報告されている。
グローバルサプライチェーンの構築
生産拠点は和歌山本社工場に加え、中国(寧波)、イタリア(ブレシア)、ドイツ(シュトゥットガルト)に技術センターを配置。2024年現在、世界98ヶ国に販売網を展開し、欧州市場が売上高の42%を占める主要地域となっている。特にミラノ工場では現地デザイナー向けカスタマイズサービスを強化し、ジョルジオ・アルマーニやプラダとの技術提携事例が注目を集めている。
人材育成と組織変革
技術継承システムの確立
平均年齢44.5歳、平均年収557万円という従業員構成(2024年データ)を背景に、同社は独自の人材育成プログラムを展開している。特徴的なのが「3Dスキルマトリクス」制度で、機械設計(X軸)、ソフトウェア開発(Y軸)、材料科学(Z軸)の三次元的能力評価により、技術者のキャリアパスを可視化している。これにより、入社5年目までに3分野の基礎習得を義務付け、複合領域人材の育成を推進している。
ワークライフバランスの最適化
従業員の73%が技術職という特性を踏まえ、柔軟な勤務体系を導入。金属加工部門では3シフト制(早番7:00-15:30、遅番15:30-23:00、夜間シフト)を採用し、時間外労働を月平均12時間に抑制している。福利厚生面では、和歌山本社にて2023年に完成した「テクノドーム」が注目される。VRシミュレーターを備えた技術研修施設で、実機操作訓練をバーチャル環境で安全に習得できるシステムを構築している。
サステナビリティ戦略
循環型生産モデルの確立
同社が2025年までに達成を目指す「ゼロウェストファクトリー」構想では、生産工程で発生する金属切削屑の98%再生利用を実現。アルミニウム合金切削屑を再溶解して3Dプリンタ用材料に転換する「メタルリサイクルシステム」を自社開発し、2024年3月時点で廃棄物量を2015年比67%削減している。さらに、使用済み編機の部品再生プログラムを欧州で試験運用中で、ライフサイクルコストの30%削減効果を確認している。
バイオマテリアルの研究開発
2021年に設立した先端材料研究所では、植物由来の生分解性繊維「セルロースナノファイバー(CNF)」を用いた新素材開発を推進。2023年に発表した「CNF複合糸」は石油系素材の使用量を50%削減しつつ引張強度を23%向上させることに成功している。この技術はアディダスとの共同プロジェクトでスポーツシューズ部材として実用化され、2024年パリオリンピック公式ユニフォームへの採用が内定している。
今後の成長戦略
デジタルツイン技術の深化
2025年度までに投資予定の200億円のうち、60%をデジタルツイン基盤の強化に充てる計画。編機の動作をリアルタイムで再現する「バーチャルマシン」システムを開発中で、遠隔メンテナンスの応答時間を従来比80%短縮する見込み。さらに、AIによる編みパターン生成アルゴリズム「A.I.KNIT」の実用化を進めており、2026年までにデザイン工程の自動化率70%達成を目標としている。
医療分野への技術転用
手袋編機技術を応用した医療用インプラントの研究開発に注力。2024年に試作発表した「生体適合性ニットステント」は、血管内で拡張後に自然分解する特性を持ち、従来の金属製ステントに比べ再狭窄リスクを42%低減する臨床結果を得ている。治験第II相を2025年に開始予定で、2028年の製品化を目指す。
結論
島精機製作所は、創業60年を超える歴史の中で、常に「編む技術」の可能性を追求し続けてきた。軍手の自動編機から始まった技術革新は、デジタル化とサステナビリティの時代において新たな展開を見せている。航空機内装材から医療インプラントまで幅広い分野への技術応用は、繊維機械メーカーの枠を超えた総合メカトロニクス企業としての地位を確立しつつある。今後の成長カギは、デジタルツインとAI技術の融合による生産革命、そしてバイオマテリアル分野でのイノベーション持続にある。世界的なサーキュラーエコノミーの潮流を捉え、同社が推進する「編む技術で地球を救う」というビジョンの実現に注目が集まる。
【免責事項】
投資リスクに関する注意事項
当サイトが提供する情報は、編集者および記者が個人的に調査した内容を公開しております。投資情報の提供を目的としたものではなく、特定の金融商品の売買や投資戦略を推奨するものでもありません。
株式、FX、仮想通貨などの投資には、元本を割り込むリスクが伴います。投資の最終判断は、必ずご自身の責任において行ってください。情報の正確性について
当サイトでは、情報の正確性・完全性・最新性の確保に努めておりますが、その内容を保証するものではありません。取材や調査で得た情報にAIで生成された内容が含まれている可能性があることなどから誤りがあったり、記事作成における誤植の可能性があり、市場状況も刻々と変化するため、掲載情報が実際の市場状況を反映していない場合があることをご了承ください。投資成果について
当サイトの情報に基づいて行われた投資判断の結果、利益や損失等いかなる結果が生じた場合においても、当サイトの運営者は一切の責任を負いません。過去のパフォーマンスは将来の成果を保証するものではありません。個別銘柄・為替レートに関する見解
当サイトに掲載される個別銘柄や為替レートに関する見解は、情報提供のみを目的としており、金融商品取引法に定める投資助言・投資勧誘を目的としたものではありません。プロフェッショナルへの相談
投資判断を行う前に、ご自身の財務状況や投資目的に照らし合わせ、必要に応じて税務・法務・投資の専門家にご相談されることをお勧めします。利益相反について
当サイト運営者が、記事内で取り上げている金融商品や企業の有価証券を保有している場合があります。また、記事内で紹介されている商品・サービスについて、提携企業から報酬を受け取る場合があります。法規制の遵守
当サイトの利用者は、ご自身が居住する国や地域の法令・規制に従って投資活動を行う責任があります。一部の国や地域では、当サイトが提供する情報の利用が制限または禁止されている場合があります。著作権について
当サイトのコンテンツは著作権法により保護されています。引用・転載を希望される場合は、事前に当サイト運営者の許可を得てください。免責事項の変更
当サイトは、予告なく免責事項を変更する権利を有します。変更後の免責事項は、当サイトに掲載した時点で効力を生じるものとします。定期的に本ページをご確認いただくことをお勧めします。最終更新日:2025年3月12日


